オウンドメディアのSEO対策!効果的な方法など解説【2025年最新】

「オウンドメディアのSEO対策はどうすればいい?」
「オウンドメディアのメリットってなに?」
オウンドメディアとはきいても、どう扱えばいいか、よくわからないですよね。。
本記事では、オウンドメディアに効果的なSEO具体策、オウンドメディアのメリット、2025年からのSEOトレンドなどについてお伝えします。
ぜひご一読いただき、貴院のSEO対策にお役立てください。
Contents
- 1 オウンドメディアとは
- 2 オウンドメディアのメリット
- 3 オウンドメディアを作る際の事前準備
- 4 オウンドメディアの内部SEO対策ですべきこと
- 5 オウンドメディアの外部SEO対策ですべきこと
- 6 オウンドメディアのコンテンツSEOですべきこと
- 7 2025年からのSEO対策:トレンドから対策方法を解説
- 8 まとめ
オウンドメディアとは

オウンドメディアとは、医療機関や企業が自社で所有し、独自にコントロールできるメディアのことを指します。
具体的には自社のウェブサイトやブログ、広報誌などが該当します。
これらは無料で利用できるSNS(アーンドメディア)や広告枠を購入して露出する媒体(ペイドメディア)とは異なる特性を持ちます。
オウンドメディアのメリット

本項目では、オウンドメディアのメリットについてお伝えします。
知名度や信頼性アップが期待できる
オウンドメディアを通じて、医療機関の理念や専門性を継続的に発信することができます。
専門的な医療情報や治療事例をわかりやすく解説することで、読者は「この医療機関には確かな専門知識がある」「このドクターは信頼できる」という印象を持ちやすくなります。
これにより、医療機関としての知名度向上と信頼性の確立が期待できます。
潜在患者へのアプローチができる
多くの患者は症状や疾患名、治療方法などをインターネットで検索して情報収集を行っています。
オウンドメディアにこうした情報を網羅的にまとめ、適切なSEO対策を実施することで、まだ受診を決断していない潜在的な患者層との接点を生み出すことができます。
読者の悩みを解決するコンテンツを多数展開し、複数回ウェブサイトに訪問してもらう、あるいは、検索エンジン上で医院名などを目にすることで、症状が現れた際になどに問い合わせや予約行動につながりやすくなります。
患者獲得が期待できる
オウンドメディアを通じて医療情報を求める読者を実際の受診や検査予約といった行動に結びつけることで、新規患者の獲得が期待できます。
医療分野における具体的な活用例としては、コンテンツの流れの中で自然に診療メニューを紹介する方法があります。
例えば「肩こりと首の痛みを緩和するセルフケア」を解説した記事の中で「当院では症状に合わせた専門的リハビリプログラムを提供しています」といった案内を適切に配置することで、違和感なく受診を促すことができます。
人材獲得が期待できる
オウンドメディアを採用活動に活用する「オウンドメディアリクルーティング」が、近年注目が高まっています。
医療機関の働き方や組織理念を詳細に発信することで、その価値観に共感した医師、看護師、その他のコメディカルスタッフからの応募が増える可能性があります。
医療分野での具体例として、まず病院やクリニックの独自のビジョンや教育プログラムの発信が挙げられます。
「地域密着型の医療提供を目指している」「最新医療機器の研修機会を定期的に設けている」など、自院ならではの特徴や学びの機会を紹介することで、自分に適した職場環境を求めている医療従事者の関心を引きやすくなります。
また、実際に勤務するスタッフの日常業務を追ったルポルタージュ記事やインタビュー記事も効果的です。
実際の業務内容や職場の雰囲気が具体的に伝わるため、求職者は入職後の自分の姿をより明確にイメージしやすくなり、入職後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
コンテンツが資産として蓄積され、広告などのプロモーション費用削減が期待できる
オウンドメディアに掲載したコンテンツは、ストック型の資産として長期間にわたって読者に価値を提供し続けます。
有料広告は停止してしまえば、効果も消えてしまうのに対し、蓄積した専門的な医療情報や診療実績は繰り返し活用することが可能です。
こうしたコンテンツが検索エンジンで上位表示されるようになれば、広告出稿に依存せずとも自然検索からの継続的な流入を獲得できるようになり、結果としてプロモーション費用の削減につながります。
オウンドメディアを作る際の事前準備
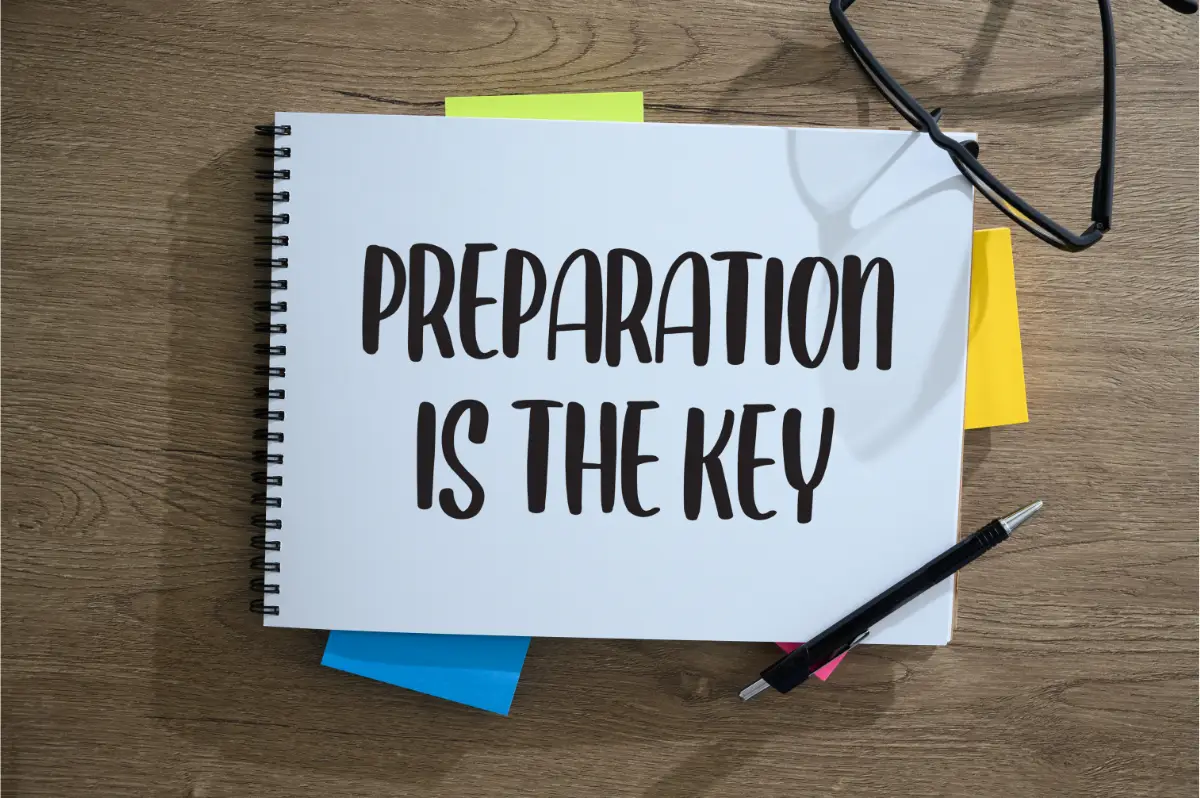
本項目では、オウンドメディアを作る際の事前準備について詳しくご説明します。
オウンドメディアの運営目的を明確にする
オウンドメディアを立ち上げる前に、「なぜオウンドメディアを運営するのか」という根本的な目的を明確にすることが大切です。
医療分野における具体的な目的としては、例えばまず、患者への正確な医療情報提供が挙げられます。
生活習慣病の予防啓発や専門診療科の治療手法をわかりやすく解説するなど、患者やその家族が求める情報を体系的に集約し、インターネットを通じて信頼性の高い医療知識を発信することができます。
また、病院やクリニックの認知度向上も重要な目的となります。
地域住民に向けて診療科の特徴や医療スタッフの紹介、最新医療設備の導入情報などを積極的に公開することで、受診先の候補として認識してもらうことが可能になります。
これらの運営目的を事前に明確化することで、「どのようなコンテンツを中心に掲載するべきか」「どの程度の頻度で更新していくか」など、オウンドメディア運営の具体的な方向性が定まりやすくなります。
目標、予算、期間を明確にする
運営目的が定まったら、次にそれを達成するための具体的な「目標設定(KPI/KGI)」「予算計画」「運営期間」を決定し、計画的に進めることが重要です。
目標を数値化する
まず、アクセス指標の設定が基本となります。
「月間3万PVの達成」「半年以内に主要キーワードで検索順位を上位10位以内に上げる」などの具体的な数値目標を定めることで、オウンドメディアの成果を客観的に測定することができます。
また、お問い合わせ数や来院数の目標設定も重要です。
電話予約やウェブからのオンライン予約件数、問い合わせフォームを通じた相談件数などを定期的に計測し、一定の目標値を設定することで、オウンドメディアが実際の患者獲得にどの程度貢献しているかを把握できます。
予算を決定する
制作費用の計画が必要です。
サイトのデザインや構築費用、システム導入コストなどの初期投資を想定します。
医療専門のライターや監修を行う医師への報酬なども含めた予算を準備しましょう。
運用費用も重要な要素です。
定期的な記事作成やコンテンツ更新のためのライター費用、運用担当者の人件費、医療現場の撮影費用、広告宣伝費などを継続的に見込んでおく必要があります。
さらに、各種ツールやシステム利用料も考慮します。
アクセス解析ツール(Googleアナリティクスなど)やSEO順位チェックツールの利用料、サーバー費用、コンテンツ管理システム(CMS)の利用料なども予算に含めておきましょう。
期間を設定する
制作から公開までのスケジュールを明確にします。
「3か月でプロトタイプを公開」「半年後には定期的な更新体制を整える」など、段階的なスケジュールを立てることで、プロジェクト全体の進捗管理がしやすくなります。
ターゲット層、ペルソナを明確にする
オウンドメディアを通じて情報を届けたい対象者を事前に明確化することも重要です。
ターゲットによって内容や表現方法が大きく変わります。
ターゲット層の設定
例えば総合病院の場合、主なターゲット層としては地域住民(一般患者)、他医療機関からの紹介患者、他の医療機関の医師やコメディカルスタッフ、就職先を探している医療従事者などが考えられます。
ペルソナの具体化
ターゲット層をより具体的に描くための「ペルソナ設定」が効果的です。
ペルソナ設定を行うことで、「記事の難易度や専門性」「使用する専門用語の程度」といった具体的な方向性が明確になり、読者にとって真に価値のあるコンテンツ作りに近づきます。
患者向けのペルソナ例としては、45歳の女性事務職で、慢性的な腰痛に悩んでおり、自宅や職場での痛み軽減方法を探しているケースが考えられます。
病院選びの決め手としては「リハビリの実績」と「女性スタッフの在籍状況」を重視し、情報収集は主にインターネット検索(「腰痛 リハビリ」「女性医師 腰痛専門」など)で行っているといった具体的な人物像を想定します。
テーマとコンテンツの方向性を決める
医療分野に限ったことではありませんが、方向性をぶらさないようテーマに一貫性を持たせることが重要です。
テーマがあちこちに散らばると、読者も混乱し、検索エンジンからも評価されにくくなります。
ともなって、オウンドメディアのテーマやコンテンツの方向性を決める必要があります。
例えば、整形外科なら「リハビリ」や「関節疾患」、内科なら「生活習慣病」や「糖尿病管理」など、特定の領域に絞って定期的に情報発信するとよいでしょう。
また、Q&A形式や患者向けの連載企画として「インフルエンザ予防接種Q&A」や「腰痛改善シリーズ」など、読者が求めやすい単位でテーマを設定することも有効でしょう。
内製・外注や担当者など運営体制を整える
オウンドメディアの継続的な運営には、初期のサイト構築だけでなく、記事の執筆・編集、公開後の管理など多岐にわたる作業が必要です。
効率的な運営のためには「誰がどの工程を担当するのか」「内部リソースで対応するか外部委託するか」を事前に明確にしておく必要があります。
内製か外注かを決める
内製で運営する場合、院内スタッフや組織内の医療系ライターのスキルを活用して自前でコンテンツを作成することになります。
運営コストを抑えながら医療専門性を直接反映できるメリットがありますが、執筆担当者や監修者を確保する必要があり、一定の人的リソースが求められます。
外注を選択する場合は、ウェブ制作会社や専門ライターへ依頼することで、質の高いコンテンツやデザインを比較的短期間で構築できます。
費用は増加しますが、医療知識を持つライターや編集者を選定することで情報の正確性も担保しやすいでしょう。
チームや担当者を明確にする
まず、プロジェクト全体の責任者が必要です。
制作スケジュールや予算管理、コンテンツの方向性を最終決定する役割を担い、多くの場合、病院の広報担当者や院長補佐などが適任とされます。
次に、監修担当者として医師や専門スタッフの確保が重要です。
記事の医学的根拠をチェックし、専門用語の使用方法や誤記がないかを確認する役割は、オウンドメディアの信頼性確保において不可欠です。
また、ライターや編集者は、ターゲットとするペルソナに合わせた文章を作成し、情報を読みやすく構成するなど、コンテンツの質を直接左右する重要なポジションとなります。
さらに、デザイナーやコーダーは、視覚的に理解しやすいサイト設計、バナーやイラストの制作、スマートフォンなどでも表示が崩れないレスポンシブ対応などを担当します。
このように運営体制を明確に構築しておくことで、責任範囲や業務分担が曖昧になることを防ぎ、長期的にスムーズな運営が可能になります。
プラットフォームの選定やコンテンツ作成
オウンドメディアで利用するプラットフォーム(WordPressなどのCMS、各種ブログサービスなど)は、目的や予算規模、更新頻度に応じて適切に選択することが基本です。
その上で、具体的な記事制作から公開までのプロセスを設計します。
プラットフォームの選定
WordPressなどのCMSを活用すれば、デザインの自由度やSEO対策の実施も比較的容易です。
技術的な知識が必要な面もありますが、長期的な運用を考えると最も汎用性が高いでしょう。
クラウド型のオウンドメディア構築サービスも選択肢の一つです。
専門的な技術知識がなくても比較的簡単にデザインや管理ができるメリットがありますが、細部のカスタマイズには制限がある場合もあります。
また、Amebaなどのブログサービスを利用する方法もあります。
初期費用をほとんどかけずに立ち上げられる利点がありますが、デザインや機能面での制約が多く、本格的なSEO対策やコンテンツ展開には限界がある可能性があります。
コンテンツ作成のポイント
医療機関のオウンドメディア運営では、適切なキーワード選定から始めることが重要です。
自院の強みと患者ニーズを考慮し、潜在顧客向け、顕在顧客向けに分けてコンテンツを用意するとよいでしょう。
次に、検索意図の理解が重要です。
「知りたい」意図には解説や事例を、「行きたい」意図には院内案内や予約ページなどの実用情報を提供します。
競合分析も効果的です。
上位表示されている医療サイトのコンテンツ構成を参考にしながら、自院だけの独自性(医師の専門資格、最新設備など)を打ち出すことで差別化を図ります。
さらに、医療情報は特に正確性と信頼性が求められます。
検索意図に合わせた記事構成と専門家による監修明示で、EEAT(専門性・権威性・信頼性)を高めることが大切です。
例えば腰痛関連なら、症状の程度・原因を整理し、医師監修のリハビリメニューを提案するなど具体的な価値を提供します。
(運用開始後)成果測定と改善
オウンドメディアの公開はゴールではなく、むしろスタート地点です。
実際に運営を始めた後は「成果を測定し、継続的に改善していく」というサイクルを回すことが成功への鍵となります。
成果指標(KPI)の計測
Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのアクセス解析ツールを活用して、様々なデータを収集・分析します。
ページビュー数に関しては、どの記事がよく読まれているか、どのキーワードからの流入が多いかなどを確認します。
また、サイト上での滞在時間や直帰率を分析することで、読者が記事を最後まで読んでいるか、途中で離脱していないかなどを把握できます。
コンバージョン計測も重要です。
オンライン予約や問い合わせフォームからの連絡数が増加しているか、オウンドメディア経由で応募してきた医療従事者がどの程度いるかなど、具体的な成果指標を計測します。
分析結果をもとにコンテンツを改善
収集したデータを元に、コンテンツの追加・修正を行います。
アクセス数が少ない記事については内容を見直し、患者がより興味を持ちそうなトピックや専門性を深める情報を追加することで、記事の価値を高めることができます。
検索キーワードの再検討も効果的です。
専門的な医学用語だけでなく、「腰痛 原因 病院」「頭痛 いつ受診」など、患者が実際に検索しそうなキーワードを新たに選定し、それに対応する記事を作成します。
サイトの導線やユーザーインターフェースの調整も重要です。
実際の来院や問い合わせにつながりやすい導線設計やボタン配置、問い合わせフォームのわかりやすさなどを継続的に改善していきます。
このように継続的な検証とアップデートを行うことで、患者や医療従事者など、ターゲットとする読者にとって真に価値ある情報発信が可能になります。
オウンドメディアの内部SEO対策ですべきこと

SEO対策は3種類に大別することができ、それぞれ、内部SEO対策、外部SEO対策、コンテンツSEOと呼ばれます。
本項目では、オウンドメディアの内部SEO対策ですべきことについて、詳しくご説明します。
URL名を簡潔にする
オウンドメディア内の各ページURLは、内容を端的に表す英単語や短いフレーズを使用することで、ユーザーと検索エンジンの双方にとって理解しやすいものになります。
複雑なパラメータや意味のない数字列だけのURLを使用していると、患者がURLを見ただけでは目的のページかどうか判断しづらくなります。
また、検索エンジンにとってもページの主題を認識しにくくなり、検索順位に悪影響を及ぼす可能性があります。
医療分野における具体例としては、整形外科紹介ページの場合、「/department/orthopedics」のように診療科名を簡潔に英語表記することで、URLだけで整形外科のページだと一目でわかるようになるでしょう。
キーワードを設定する
メインキーワードを決める
医療系のオウンドメディアでは、主に以下のようなカテゴリーからキーワードを検討するとよいでしょう。
疾患名については、「糖尿病」「高血圧」「肺炎」などの病名が代表的です。
症状に関しては、「腰痛」「頭痛」「不眠」といった患者が実際に感じる症状がキーワードになります。
検査・治療法としては、「MRI検査」「心臓カテーテル治療」などの医療行為が挙げられます。
また、予防策や健康管理の観点からは「免疫力アップ」「骨粗鬆症予防」などのキーワードも重要です。
適切なサブキーワードを組み合わせる
メインキーワードだけでは情報の範囲が広すぎる(検索意図が曖昧)ことが多いため、より具体的な検索クエリに対応することが推奨されます。
例えば「糖尿病 初期症状」「腰痛 原因」など、患者が実際によく検索する疑問形式のキーワードを組み合わせることで、検索意図に沿った的確なコンテンツを提供しやすくなります。
キーワードの入れ過ぎに注意
例えば「糖尿病の原因・治療・食事・薬の情報すべて」を1つの記事に詰め込むアプローチは避けるべきです。
記事内容が散漫になり、読者が真に求める情報にたどり着きにくくなります。
特定のテーマに焦点を絞った複数の記事に分割することで、それぞれの記事の目的が明確になり、ユーザー体験と検索エンジン評価の両方が向上します。
TDHを最適化する
TDHとは「title(タイトルタグ)」「description(メタディスクリプション)」「hタグ(見出しタグ)」の略であり、検索エンジンやユーザーにページ内容を正確に伝えるために不可欠な要素です。
title(タイトルタグ)
患者、検索エンジン目線でわかりやすいタイトル設定が重要です。
例えば「腰痛の原因と対処法|早めに知っておきたい治療のポイント【医師監修】」といったタイトルでは、「腰痛」「原因」「対処法」というキーワードを含めることで、コンテンツの信頼性と内容を一目で伝えることができます。
キーワード挿入に加え、内容を簡潔に表し、クリックしたくなるようなフックを含める、30文字前後で作成するなどが要点です。
検索キーワードをタイトルに含める、内容を簡潔に表すことで、検索エンジンもページの主題を理解しやすくなり、関連する検索クエリでの表示確率が高まります。
description(メタディスクリプション)
ページの要点を簡潔に伝えることが重要です。
一般的に120文字程度の長さで、ページ内容(症状、治療法、期待できる効果など)を簡潔に示します。
キーワード挿入も忘れないようにしましょう。
読者の興味を引く表現も重要です。
患者や家族が「このページを読めば知りたい情報が得られそう」と感じる内容にすることで、クリック率の向上につながります。
hタグ(見出しタグ)
多くの場合、h1タグはタイトルとして機能します。
「腰痛の原因と改善策|医師が解説」といったシンプルな文言で、ページ全体の主題を明確に示すことが重要です。
h2、h3タグは、いわば大見出し、正味だしといった具合で、情報を段階的に整理するために使用します。
h2タグの例としては「腰痛の主な原因」「腰痛の治療法」「自宅でできるセルフケア」など、大きな区分けを行います。
h3タグはさらに詳細な項目として、例えば「骨格の歪み」「筋力低下」など原因を細分化した項目を入れます。
また、関連キーワードを見出しに適切に盛り込みつつ読みやすさを保つことも重要です。
タイトルに含めたキーワード以外にも、患者が検索する可能性のある関連用語や症状を見出しに活用することで、検索エンジンのコンテンツ理解が深まりやすくなります。
これら3つの要素を適切に最適化することで、検索エンジンからより評価されやすく、患者が求める情報にスムーズにアクセスできる質の高いオウンドメディアを構築することができます。
適切な内部リンクを設置する
オウンドメディア内で関連する記事間をリンクで結ぶことは、読者が求める情報へスムーズに誘導するための重要な施策です。
医療分野における具体例としては、まず症状や治療法に関する関連記事への誘導が挙げられます。
例えば「腰痛の原因」を解説するページから「効果的なリハビリテーション方法」「適切な痛み止めの選び方」など、内容が関連する記事へ内部リンクを設置することで、患者にとって有益な情報を体系的に提供できます。
また、医療スタッフ紹介ページから診療実績ページへのリンク設定も効果的です。
医師や看護師、専門スタッフの紹介記事に「担当診療科の治療実績紹介ページ」へのリンクを組み込むことで、医療機関の信頼性を高めることができるでしょう。
こうした内部リンク構造を整理しておくことは、検索エンジンのクローラーの巡回効率も高め、結果的にサイト全体の評価向上につながります。
altタグを最適化する
altタグ(代替テキスト属性)は、画像の内容を説明するテキスト情報であり、検索エンジンやスクリーンリーダーを利用する視覚障がいのある方にとって、情報を正確に伝えるために有効です。
医療分野においては、例えば、医療機器や院内設備の写真に、「最新型の内視鏡検査室の設備」「2023年導入の64列CTスキャン装置」など、写真を見ただけではわからない情報をaltに設定するとよいでしょう。
altタグを適切に設定することには複数のメリットがあります。
画像が表示されない環境や通信速度の遅い状況でも読者が内容を理解できるだけでなく、画像検索からの流入増加にもつながります。
さらに、アクセシビリティ向上という観点からも、医療情報を広く届けるためによい施策となります。
URLを正規化する
同一または類似のコンテンツが複数のURLで存在する場合、Googleなどの検索エンジンに正しいURLを指示するための「正規化(canonical設定)」、あるいは「リダイレクト処理」が必要です。
コンテンツが重複していると、患者も混乱するばかりか、検索エンジンの評価が分散してしまい、検索順位の低下を招く可能性があります。
医療分野における具体例としては、「診療案内」ページの重複が挙げられます。
例えば「/clinic-guide」と「/clinic-guide/index.html」が同じ内容を持つ場合、どちらか一方を正規URL(canonical)として指定する、あるいはリダイレクトすることで、検索エンジンの評価を一本化できます。
適切なHTMLタグでマークアップする
HTMLタグを正確に使用することは、検索エンジンのクローラーだけでなく、実際にサイトを訪れる患者にとっても、ページ内容を理解しやすくするために重要です。
特に見出しタグ(「h1」~「h6」)を階層的に適切に配置することで、コンテンツの構造が明確になり、読みやすさとSEO効果の両方を高めることができます。
医療分野における具体例としては、診療科別のページ構成が挙げられます。
例えば整形外科のページでは、「h1」タグには「整形外科の診療案内」といった大見出しを設定し、「h2」タグには「当院の整形外科の特徴」「治療方針」などの中見出し、さらに「h3」タグには「リハビリテーションの流れ」「手術後のケア方法」といった小見出しを設定します。
このように階層的に内容を整理することで、医療機関が伝えたい情報が読者に明確に伝わります。
構造化データをマークアップする
構造化データ(schema.orgなど)を用いてページ内容をマークアップすることで、検索エンジンはコンテンツの本質をより正確に理解できるようになります。
また、検索結果にリッチスニペットが表示される可能性が高まり、ユーザーの目に留まりやすくもなります。
具体例としては、まず医療機関や医師の情報のマークアップが挙げられます。
病院名、所在地、診療科目などを「LocalBusiness」や「Hospital」のスキーマで記述することで、検索エンジンは当該医療機関の基本情報を正確に把握できます。
また、医師の経歴や専門分野を「Person」や「MedicalOrganization」のスキーマを使って記述することも有効でしょう。
リンク階層を浅くする
サイト内のリンク階層(トップページから各コンテンツページへアクセスするまでの段階数)が過度に深くなると、ユーザーが目的の情報に到達するのが困難になるだけでなく、検索エンジンのクローラーもすべてのページを効率的に巡回できなくなる恐れがあります。
医療分野あれば、例えば、「トップページ」→「診療科一覧」→「整形外科」のように、3クリック程度でたどり着ける、つまり、3階層程度を目安にした設計が重要です。
医療情報を求める方々が、ストレスなく必要な情報にアクセスできる環境を整えることは、オウンドメディアを通じた患者サービスの質を高めることにもつながります。
パンくずリストを設置する
パンくずリストは、ユーザーが現在サイト内のどの階層に位置しているかを視覚的に表示するナビゲーション機能です。
診療科や検査メニューなど、複数の階層構造を持つ場合、パンくずリストの設置は利用者の利便性を大幅に向上させます。
例えば、「トップページ → 診療科一覧 → 整形外科 → リハビリテーション」といった階層構造を視覚的に表示することで、患者は自分がどの診療科のどの治療項目を閲覧しているのかを即座に把握できます。
パンくずリストを適切に設置することは、ユーザビリティ向上だけでなく、検索エンジンのクローラーがサイト構造を理解するためにも役立ちます。
XMLサイトマップを設置する
XMLサイトマップは、サイト内のURL一覧をXML形式でまとめ、検索エンジンにウェブサイト全体の構成を伝えるためのファイルです。
特にページ数が多いウェブサイトでは有効であり、クローラーが見落としがちなページも漏れなくクローリングされるようになります。
また、最新の医療情報や治療法を定期的に発信しているサイトにも有効です。
新たに更新された記事や追加されたコンテンツが速やかに検索エンジンに認識されるよう、XMLサイトマップを自動生成する仕組み(WordPressプラグインなど)を活用し、Google Search Consoleに登録しておくとよいでしょう。
robots.txtの不要なクロールを制限する
robots.txtは、検索エンジンのクローラー(ロボット)がサイトを巡回する際のルールを記載したテキストファイルです。
膨大なページ数を持つ医療機関のオウンドメディアでは、検索結果に表示する必要のないページをクロール対象から除外することで、サーバーへの負荷軽減と重要ページへの集中的なクロールを促進できます。
例えば、病院のウェブ予約フォームや患者向け問い合わせフォームなどは、検索結果に表示される必要がないケースが多いため、robots.txtファイルを用いてクローラーのアクセスを制限することが適切でしょう。
また、病院内部のスタッフ向けに作成された管理画面や試験的な検査情報ページなども、一般に公開する必要のない情報であればインデックス対象から除外すべきです。
ただし、robots.txtの設定には十分な注意が必要です。
誤って重要なページをクロール制限してしまうと、そのページが検索結果に表示されなくなる可能性があります。
本当にユーザーに見せる必要がないページだけを制限対象とするよう慎重な設定が求められます。
SSL化する
ウェブサイトをHTTPS(SSL/TLS)化することは、現代のウェブサイト運営において基本的な安全対策です。
SSL化により通信が暗号化され、ユーザーとサイト間のデータ漏洩リスクが大幅に軽減されます。
特に医療関連のオウンドメディアでは、患者情報や相談内容など機密性の高いデータを扱うことがあるため、SSL化は信頼性向上に直結する重要な対策といえます。
例えば、予約フォームや問い合わせフォームなど、患者が氏名や連絡先、症状などの個人情報を入力するページは必ずHTTPS化し、入力内容が第三者に盗み見られないよう保護する必要があります。
また、検索エンジン評価の向上という側面もあります。
GoogleはSSL化をSEOの評価要因として明確に位置づけており、HTTPS化することで検索順位にプラスの影響を与える可能性があります。
画像やコーディングなどのデータを削減する
表示速度の向上は、ユーザーのストレス軽減だけでなく、GoogleのCore Web Vitalsといった評価指標においても重要な要素となっています。
ウェブサイトに画像やイラストを掲載する際、最適化せずに重いデータを掲載すると読み込み時間が長くなり、ユーザーの離脱率上昇を招く恐れがあります。
JPEGやWebP形式を活用し、適切な圧縮処理を施すことで、視覚的な品質を保持しながらファイルサイズを削減することができます。
さらに、不要なスクリプトやCSSの排除も効果的です。
院内検索機能や予約システムなど独自機能を実装する場合も、必要最小限のコードに留めることで、サイト全体のパフォーマンスが向上します。
モバイルフレンドリーにする
スマートフォンから検索を行うユーザーは年々増加しており、オウンドメディアにおけるモバイル対応は必須となっています。
Googleはモバイルファーストインデックス(MFI)を採用しており、モバイル端末での表示が最適化されていないサイトは検索順位に悪影響が出る可能性があります。
具体的にはまず、レスポンシブデザインの導入が挙げられます。
トップページはもちろん、診療科紹介、医師プロフィール、診療時間案内など、すべてのページがスマートフォンやタブレットでも見やすいレイアウトになるよう設計することが重要です。
また、タップ操作を考慮したボタン配置も欠かせません。
「予約する」「お問い合わせ」といった重要なアクションボタンを適切なサイズに設定し、十分な余白を確保することで、誤タップを減らし、ユーザーの操作ストレスを軽減できます。
特に高齢者や緊急時のユーザーにとって、この配慮は重要です。
オウンドメディアの外部SEO対策ですべきこと

SEO対策は3種類に大別することができ、それぞれ、内部SEO対策、外部SEO対策、コンテンツSEOと呼ばれるとは、先述の通りです。
本項目では、オウンドメディアの外部SEO対策ですべきことについてご説明します。
良質な被リンクを獲得する
他のウェブサイトから自社オウンドメディアへのリンク(被リンク)は、検索エンジンが「どのサイトを高く評価すべきか」を判断する重要な指標の一つです。
質の高い被リンクを獲得することで、検索結果での上位表示が期待できます。
医療分野における具体例としては、まず学会や医療専門サイトからのリンク獲得が挙げられます。
学会での発表内容や研究論文、医療関連のニュースメディアで紹介されるなど、権威性の高いサイトからリンクを得ることで、サイト全体の評価向上につながります。
また、健康啓発イベントやセミナー情報の外部発信も有効です。
地域密着型の健康講座や医療セミナーの実施レポートを地域の広報誌や業界メディアで取り上げてもらうことで、自然な形で被リンクを集めることができます。
良質な被リンクを獲得するためには、まずオリジナリティのある医療情報や専門家による監修記事など、高品質なコンテンツを作成することが大前提となります。
価値ある情報があってこそ、他サイトからリンクされる価値が生まれます。
サイテーションを獲得する
「サイテーション」とは、医療機関名やブランド名がリンクなしで他のサイトやSNS上で言及されることを指します。
実際のリンクがなくても、「●●病院がこのような取り組みを実施している」といった形で名前が広がると、検索エンジンからの評価が高まる傾向があります。
医療分野での具体例としては、まず地域ニュースやSNSでの言及が挙げられます。
地域住民向けの健康診断イベントやワクチン接種情報などをSNSで発信し、利用者が「●●クリニックで受けることができた」と投稿すれば、それがサイテーションとして機能します。
また、口コミ投稿サイトやQ&Aサイトでの言及も有効です。
「●●医院で検診を受けました」などの体験談が増えることで、信頼性の向上だけでなく、SEO面でも好影響をもたらします。
オウンドメディアのコンテンツSEOですべきこと

SEO対策は3種類に大別することができ、それぞれ、内部SEO対策、外部SEO対策、コンテンツSEOと呼ばれるとは、先にお伝えしました。
本項目では、オウンドメディアのコンテンツSEOですべきことについてご説明します。
適切にキーワードを選定を行う
キーワード選定は、コンテンツSEOの土台となる作業の一つです。
キーワードは、自社(自院)の強みや競合他院・他サイトの弱み、そして患者のニーズを総合的に考慮し、慎重に決定する必要があります。
さらに、潜在顧客(病気や症状はあるが病院を探していない人)むけと、顕在顧客(すでに受診先や検査の予約を考えている人)むけに分けて考えることが大切です。
潜在顧客向けには、「糖尿病 足のしびれ」「血圧 めまい 対処法」など、「なぜ症状が起きるのか」「どう対処すればいいか」を知りたいユーザーに向けた記事を作成します。
これはKnowクエリと呼ばれるもので、情報提供が中心となります。
一方、顕在向けには、「新宿 小児科 駅チカ」「●●駅 内視鏡検査 予約」など、受診先を具体的に探しているユーザーに向けた病院案内・予約ページなどを用意し、コンバージョン(予約・問い合わせ)につなげることが大切です。
これはGo/Do/Buyクエリに分類できるでしょう。
キーワード選定を行う際は、検索ボリュームや競合状況だけでなく、目指す患者層や自院の得意分野を意識し、「潜在顧客」への情報提供と「顕在顧客」の受け皿の両面からバランスよく設計していきましょう。
ユーザーの検索意図を分析・理解する
キーワードを決めても、それが実際にどんな検索意図(何を知りたい・どんな行動を取りたい)を持つユーザーによるものかを分析することが肝要です。
検索意図は、一つ「知りたい(Know)」「行きたい(Go)」「買いたい(Buy)」「したい(Do)」に分類でき、オウンドメディア上でどのようなコンテンツを提供すべきかが変わってきます。
「Know」クエリに対応する場合は、「●●とは何か?」「●●の原因・症状は?」など、情報収集を目的とするユーザーに向けて、分かりやすい解説や事例を提供します。
一方、「Go」「Do」「Buy」クエリに対応する場合は、「クリニックの場所・営業時間が知りたい」「オンライン予約をしたい」「専門医の診断を受けたい」など、具体的な行動を求めるユーザーには予約ページや院内案内を分かりやすく用意することが重要です。
医療系サイトだから特別、というわけではなく、どの分野でもユーザーファーストなコンテンツ制作が必要です。
ユーザーが抱えている疑問や目的を把握し、それに沿った情報を適切な形で提供することで、SEOの評価だけでなく満足度や信頼度も高まります。
競合分析を行う
効果的なコンテンツ作成のためには、同業の医療機関サイトなど競合の傾向を詳細に分析し、自院や自社の強みを明確に打ち出す戦略が必要です。
競合分析といって、具体的には、対象のキーワードで検索した際に表示される他病院・クリニックのオウンドメディアとの比較を行います。
競合サイトをチェックし、症例紹介や検査メニューの見せ方、ページ構成を比較します。
そこから、自院だけの独自の検査方法や治療実績をアピールするポイントを見出すことができます。
競合サイトで上位表示を獲得しているキーワードやコンテンツ構成を詳細に分析した上で、自院の強みや特徴(専門性の高さ、地域医療連携の実績、医師・スタッフの専門資格など)を効果的に打ち出した記事を作成することにより、検索エンジンからより高い評価を得られるようになります。
ユーザーに価値あるコンテンツを作成する
オウンドメディアのコンテンツSEOでは、「ユーザーの検索意図を満たす」「EEAT(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)を高める」ことが重要です。
特に医療情報はYMYL(Your Money or Your Life)に分類され、利用者の健康や生活に直結するため、正確性と信頼性がさらに重視されます。
医療分野での具体例としては、まず検索意図に寄り添った記事構成が挙げられます。
例えば「腰痛 リハビリ 簡単」で検索する人は、すぐに始められるリハビリ方法を求めていることが多いです。
そこで、痛みの程度や症状別にアプローチを整理しながら、医師監修の具体的なリハビリメニューを提案するなど、ユーザーが「これなら試してみたい」と感じる情報を提供しましょう。
また、EEATの観点を満たすための専門家監修も重要です。
整形外科医や理学療法士などの専門家が記事内容を監修・執筆し、プロフィールや資格情報を明示することで専門性・権威性・信頼性が高まり、読者や検索エンジンからの評価向上につながります。
ユーザーファーストを意識して検索意図を満たすコンテンツを提供し、EEATを高める工夫を継続することで、医療系オウンドメディアの検索順位向上やアクセス増加が期待できます。
検索順位やトラフィックなど効果測定を行う
オウンドメディアに記事を公開して終わりではなく、検索順位やアクセス数(PV、UU)、コンバージョン数などの指標を継続的に測定・分析し、どのような改善が必要かを見極めることがコンテンツSEO成功の鍵となります。
医療分野における具体例としては、まずGoogle Search Consoleを活用した検索順位の確認が挙げられます。
主要キーワード別の平均順位やクリック率を分析し、「糖尿病 予防法」「整形外科 リハビリ 効果」など、当初想定したキーワードで実際に上位表示されているかを定期的に把握することが重要です。
また、アクセス解析ツール(Google Analyticsなど)の活用も欠かせません。
例えば、ページにどれだけの訪問者があり、平均滞在時間はどの程度か、直帰率は高くないかなどを詳細に確認します。
これにより、コンテンツが読みやすい構成になっているか、適切な導線設計ができているかを判断できます。
さらに、医療機関の場合は問い合わせや予約件数の計測も重要です。
オンライン診療予約システムや問い合わせフォームの利用数を把握することで、SEOによって集客したユーザーが実際にどの程度受診予約や問い合わせに至っているかを確認し、PDCAサイクルを回すことができます。
これらのデータを定期的かつ体系的に分析することで、より効率的なコンテンツ制作方針を立案し、限られたリソースを最適に配分することが可能になります。
リライトを行う
公開済みの記事を継続的に更新・改善(リライト)することは、検索順位の向上やアクセス数の増加につながる重要な施策です。
医療分野においては、新たな研究成果や治療ガイドラインが日々更新されるため、最新の知見に基づいてコンテンツを更新し、情報の鮮度を保つことも不可欠です。
医療分野における具体例としては、まず診療ガイドラインの変更への対応が挙げられます。
例えば新しい治療指針が学会から発表された場合、関連する既存記事を速やかにアップデートし、最新の医学的見解を盛り込むことで、コンテンツの信頼性と有用性を維持します。
また、検索順位が伸び悩む記事の再構成も重要です。
例えばアクセス数が期待より少ない記事を、より読みやすい構成に変更し、説明用の画像や図表を追加することで閲覧体験を向上させます。
必要に応じて関連キーワードの選定を見直すことも検討します。
リライトを実施する際は、ページの閲覧数や離脱率、平均滞在時間などの指標を基に具体的な改善点を抽出し、ユーザーにとってより価値が高く、使いやすい記事に仕上げることを意識することが大切です。
2025年からのSEO対策:トレンドから対策方法を解説

本項目では、2025年からのSEO対策:トレンドから対策方法を解説についてお話します。
2025年からのトレンド
2025年以降のSEOでは、生成AIの一般化とユーザーの検索意図への最適化がさらに重要視されると予想されています。
特に医療系サイトはYMYL(Your Money or Your Life)分野に該当するため、より正確で最新かつ経験に基づいた独自性の高い情報提供が求められます。
また、医療分野では特に、経験に基づく独自情報の提供が重要となるでしょう。
糖尿病患者の実際の食事記録や実践的レシピ、専門医が実際に体験した手術手順や術後経過レポートなど、医療スタッフや患者自身の体験談を加えることで、生成AIが作りにくい唯一無二のコンテンツを提供できるようになります。
また、記事の下書きやデータ整理には生成AIを活用しつつも、仕上げには必ず医師・看護師・管理栄養士などの専門家によるファクトチェックを行うことが必要です。
医療情報は誤報や古い知見が重大なリスクにつながるため、最終段階での専門家による監修は不可欠です。
音声検索
スマートスピーカーやスマートフォンの音声アシスタント普及により、音声検索が増加しています。
医療情報も音声による質問(「この頭痛、病院に行くべき?」「近所でインフルエンザ予防接種が受けられる場所」など)をユーザーが行うケースが増えるでしょう。
音声検索に対応するためには、Q&A形式のコンテンツが効果的です。
音声検索でよく使われるフレーズ(「●●はどんな病気?」「いつ病院に行くべき?」)を意識し、簡潔な答えを先に提示して詳しい解説を続ける構成にすることが有効です。
また、音声検索では「●●専門の病院を探してる」「救急外来 24時間 空いている近所」など、口語的で長めのフレーズが使われることが多いため、これらを記事内に自然に取り入れると音声検索との親和性が高まります。
動画SEO
2024年以降、動画コンテンツの重要性はさらに高まるとされています。
YouTubeやショート動画などを通じて、ユーザーが効率的に情報を得られる環境が整いつつあります。
医療現場では、手術の流れや検査方法など、文章では伝わりにくい情報を動画で紹介することが有効です。
例えば内視鏡検査や人間ドックの流れを短い動画にまとめることで、患者が受診前に具体的なイメージを持つことができます。
これにより緊張や不安を和らげる効果があるだけでなく、検索エンジン上での評価も高まりやすくなります。
これらの動画をYouTubeなどにアップロードする際には、病院名や検査名などの適切なキーワードをタイトルやタグに入れて検索性を高めることが大切です。
さらに説明欄には関連キーワードや病院のウェブサイトURL、診療科情報などユーザーが求める追加情報を記載することで利便性が向上します。
まとめ
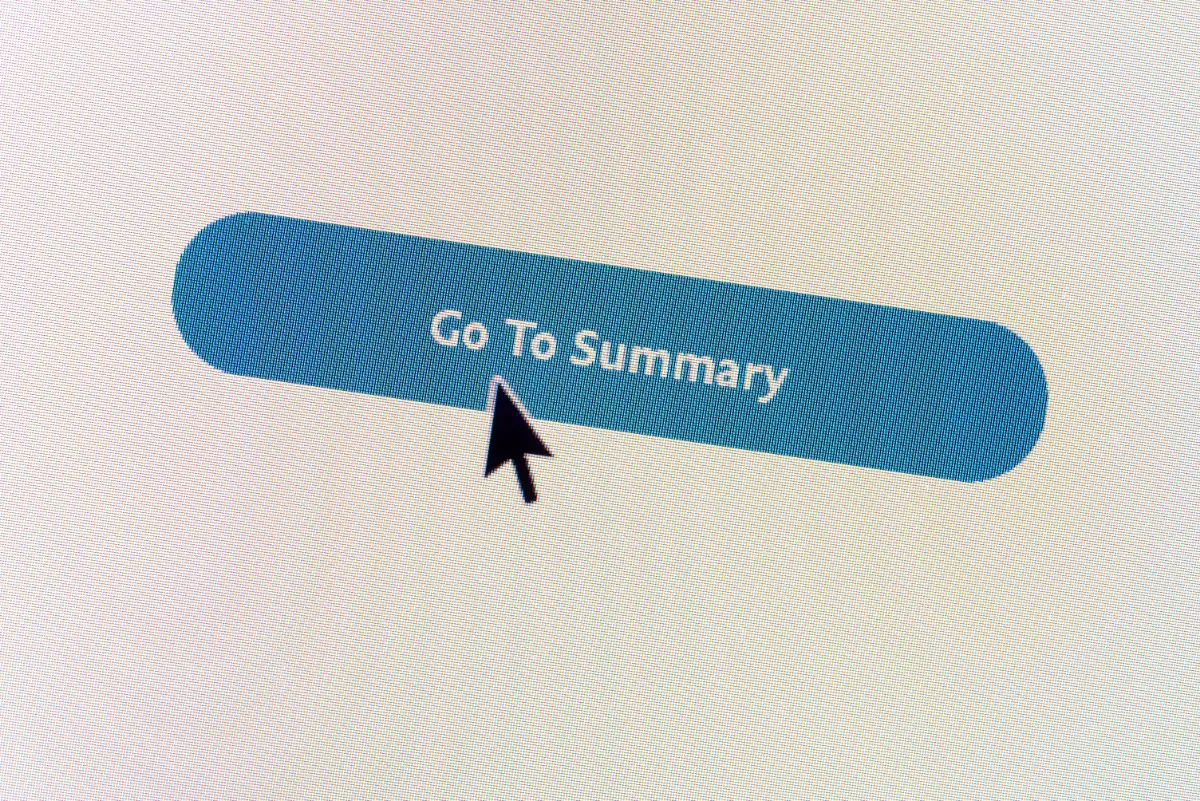
オウンドメディアは医療機関が自社で所有・管理できるウェブサイトやブログなどで、SNSや広告とは異なる特性を持ちます。
メリットとして、専門的な医療情報発信による信頼性向上、症状や治療法を検索する潜在患者との接点創出、診療メニュー紹介による患者獲得、医療機関の理念発信による人材採用効果、長期的な情報資産の蓄積によるプロモーションコスト削減などがあります。
効果的な運営には事前準備が不可欠です。
運営目的の明確化、数値目標設定、予算計画、ターゲット設定を行い、テーマとコンテンツの方向性を決めます。
内製か外注かの判断や運営体制の整備も重要です。
SEO対策としては、URL名の簡潔化、適切なキーワード選定、タイトル・ディスクリプション・見出しの最適化、内部リンク設置、画像のalt属性適正化、URL正規化、HTMLマークアップ、構造化データ活用などの内部対策が有効です。
外部対策では被リンク獲得やサイテーション獲得も重要です。
コンテンツSEOでは、適切なキーワード選定、検索意図の理解、競合分析、価値あるコンテンツ作成、効果測定、リライトが必要です。
今後のトレンドとして、生成AI活用と専門家監修の併用、音声検索対応、動画コンテンツの充実が挙げられます。医療分野では特に情報の正確性と信頼性が求められるため、専門家監修による質の高いコンテンツ提供が成功の鍵となります。
弊社では、医療機関のオウンドメディア(ウェブサイト)制作、運営や集患を総合的にサポートするサービスを提供しています。
事前準備からSEO対策、コンテンツ制作など、専門スタッフが一貫してお手伝いいたします。
オウンドメディア(ウェブサイト)やSEO対策でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせを心よりお待ちしています。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。






















