Google検索アルゴリズムの仕組みや効果的なSEOなど解説!

「Google検索のアルゴリズムってどうなっているの?」
「アルゴリズムに効果的なSEO対策をしりたい」
Google検索が仕組みを知って、効果的にSEO対策など行えるといいですよね。
本記事では、Google検索アルゴリズムとはなにか、Googleの検索アルゴリズムに効果的なSEO対策、Google検索アルゴリズムの変遷などを解説します。
ぜひご一読いただき、日々のSEO対策にお役立てください。
Contents
Google検索アルゴリズムとは?
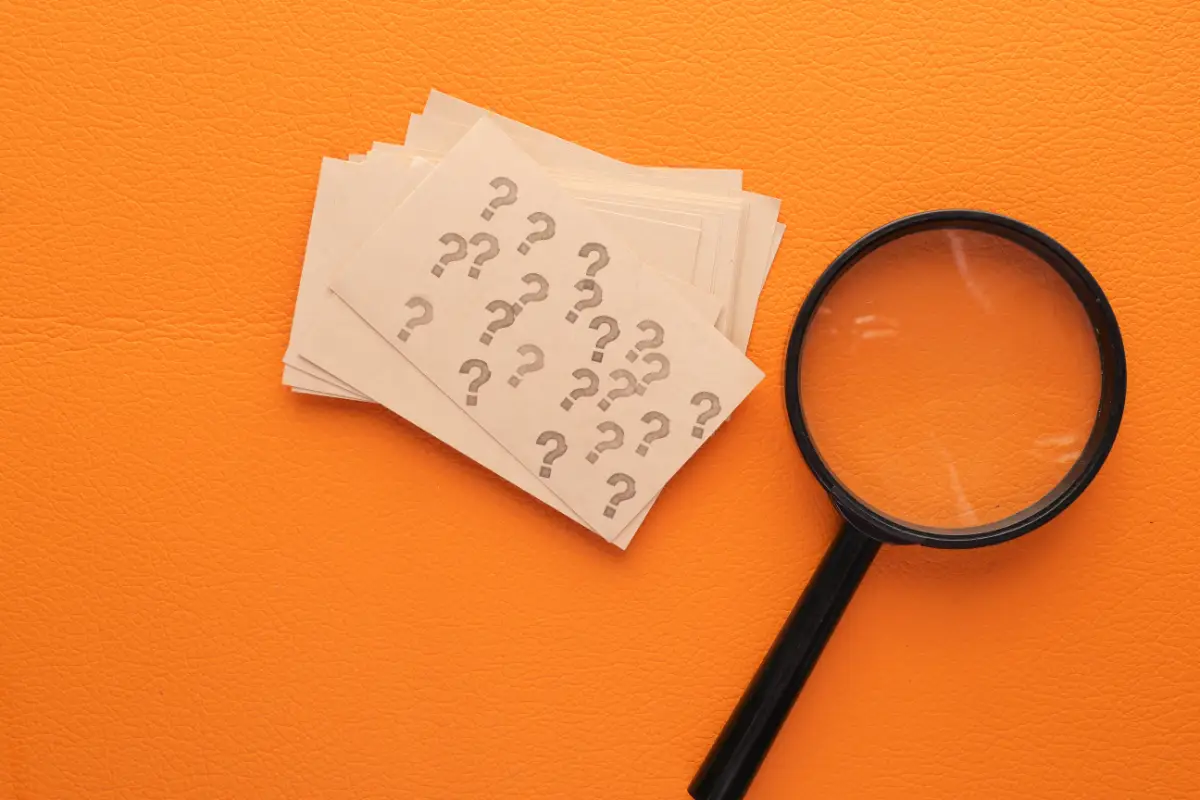
Google検索アルゴリズムとは、Googleが膨大なウェブページの中から、ユーザーの検索意図に最も合致し、役立つ情報を見つけ出して適切な順位で表示するための、ルールと計算方式の総称です。
医療の現場で患者から「腹痛 内科」や「糖尿病 食事指導」などのキーワードで検索があった際、このアルゴリズムが該当キーワードに適したウェブページを評価し、求められる情報を上位に表示します。
Googleのアルゴリズムは200以上もの評価項目を総合的に用いて順位を決定するといわれていますが、その詳細はすべて公開されているわけではありません。
また、アルゴリズムは頻繁にアップデートされ、検索結果も日々変動しています。
そのため、すべての基準を把握して対策を講じることは現実的ではありませんが、主要な指針やアルゴリズムの一部は公開されているため、それらに沿ったSEO対策を行うことで検索順位の向上が期待できます。
Googleの検索エンジンの仕組み
Googleの検索エンジンは、「検出」「クロール」「インデックス」「ランキング」という4つのプロセスを経て検索結果を表示します。
まず、クローラーと呼ばれるプログラムがウェブ上のリンクをたどりながら新たなURLを発見する「検出」の段階があります。
次に、見つけたURLのページに実際にアクセスし、コンテンツの内容を読み取る「クロール」が行われます。
収集した情報はデータベースに保存(インデックス)され、ここに登録されて初めて検索結果として表示される可能性が生まれます。
最後に、インデックスされた膨大な情報の中から、検索キーワードとの関連性やサイトの品質など、Googleが定めるアルゴリズムによる点数付けによって順位が決定される「ランキング」の工程があります。
検索アルゴリズムが最も深く影響を与えるのはランキングの段階ですが、そもそもクロールやインデックスの工程が円滑に行われないと検索結果に表示される可能性はゼロになってしまいます。
そのため、インデックスされやすいサイト構造にするなどの基本対策が欠かせません。
医療機関のホームページであれば、診療メニューや医師紹介・病院概要など、わかりやすい内部リンクの設計を心がけることが重要です。
Google検索アルゴリズムにおいて重要な5つの要素

本項目では、Google検索アルゴリズムにおいて重要な5つの要素についてお伝えします。
検索意図の理解・把握
検索意図(ユーザーインテント)とは、ユーザーが検索エンジンで入力したキーワードの背景や目的を示すものです。
例えば、患者が「胃痛 原因」で検索した場合、「なぜ胃痛が起こるのか」「どのような受診科が適切か」といった情報を求めている可能性があります。
一方、「胃痛 薬」と検索した場合は、即効性のある薬や市販薬の情報を求めているかもしれません。
Googleはこうした検索意図を把握することで、最も関連性の高い情報を上位に表示します。
医療系のウェブサイトでは、患者がどんな悩みを抱えて検索しているのかを考え、コンテンツの方向性を明確にしたり、患者の行動を想定したりすることが重要です。
例えば、「胃痛の原因」を知りたい人向けには、内科や胃腸科受診の目安、原因となり得る疾患の解説をまとめるなどの工夫が考えられます。
検索意図を読み取るためには、実際にどのようなキーワードで、どのようなコンテンツにアクセスされているかを検索結果やアクセス解析から分析し、ユーザーの求める情報に合わせたコンテンツを提供することが不可欠です。
検索クエリとページの関連性
Googleアルゴリズムでは、検索クエリ(キーワード)とページの内容がどの程度関連しているかを厳しく審査します。
医療系のウェブサイトにおいては、以下のようなケースが想定されます。
「禁煙 肺がんリスク」で検索された場合、禁煙指導のメリットや肺がんの発生リスク低減などを適切に取り上げていれば、関連性が高いページと判断されます。
「糖尿病 レシピ」で検索された場合は、糖尿病患者向けの食事管理法やカロリー計算の仕方、専門家(管理栄養士など)の監修が入った具体的なレシピが掲載されていれば、ユーザーにとって有用な情報を提供しているページとして評価されやすくなります。
ただし、ページ内に過度にキーワードを散りばめるキーワードスタッフィングは逆効果であり、Googleからスパム認定を受ける可能性があります。
検索クエリとページの内容を自然に合致させることがポイントです。
具体的には、記事タイトルや見出し(h2, h3等)、本文にあくまで自然な形でキーワードを配置できるとよいでしょう。
コンテンツの品質
Googleは、「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれる医療や健康などに関わる分野を、特に厳格に審査すると言われています。
ユーザーの健康や安全に直結する情報、つまり、YMYLに該当する情報を扱う場合は特に、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識することが重要になります。
経験については、実際の臨床現場で得た知見や経験談をコンテンツに反映させます。
専門性は、専門分野の医師や看護師、管理栄養士などが監修・執筆していることを明示することで示すことができます。
権威性は、権威ある機関や学会、論文などのエビデンスを示すことで担保可能です。
信頼性は、記事の更新日時を明記し、最新情報であることを保証したり、個人情報保護やセキュリティ対策など、安心して閲覧できるサイト設計を示すことなどで高められます。
また、医療情報は専門性が高い反面、患者にとっては難解に感じる場合も多いものです。
そこで、専門用語を補足しながら詳しく解説し、かつ最新の研究結果を踏まえた情報を提供することが重要です。
患者が疑問を抱きそうなポイントを事前に察知し、Q&A形式や図表を用いて説明すると、より深く正確な情報を伝えるでしょう。
このような「わかりやすさ」と「深み」を両立したコンテンツは検索エンジンにも評価されやすく、アクセス数や滞在時間の増加にもつながります。
ユーザビリティ・ページエクスペリエンス
ユーザビリティとは、ウェブサイトの使いやすさを表す指標です。
ページエクスペリエンスは、ユーザーがウェブページを閲覧する際の体験の質を示します。
Googleは、ユーザビリティとページエクスペリエンスを重要な評価基準としています。
ユーザビリティ・ページエクスペリエンス向上のため、以下のような点に留意することが大切です。
・モバイルフレンドリー:スマートフォンやタブレットでも読みやすいレスポンシブデザインを採用する
・ページの読み込み速度:重い画像や広告を避け、ページの表示を高速化する
・適切なフォントサイズ:高齢者でも読みやすいフォントサイズを確保する
・ナビゲーションの最適化:情報を探しやすいメニュー構成やサイト内検索機能を提供する
・コンテンツの見やすさ:見出しや段落、画像などを適切に配置し、見やすさに配慮する
ユーザビリティとページエクスペリエンスに優れたウェブサイトは、滞在時間の増加やページビューの向上につながり、結果としてGoogleからも好意的に評価されます。
文脈の理解・反映
Googleは、検索クエリだけでなく、ユーザーの行動履歴や興味関心などの文脈を理解し、パーソナライズされた検索結果を提供しています。
医療系のウェブサイトにおいては、ユーザーの文脈を考慮したコンテンツ設計が重要です。
例えば、「糖尿病」と検索したユーザーに対しては、病態の説明だけでなく、食事療法や運動療法、合併症の予防など、糖尿病患者が関心を持つトピックを幅広くカバーすることが効果的です。
また、「妊娠 つわり」と検索したユーザーには、妊娠初期の症状や対処法、気をつけるべき食品など、妊婦特有の情報ニーズに応えることが求められます。
ユーザーの文脈を理解し、それを反映したコンテンツを提供することで、ユーザーの満足度が高まり、ウェブサイトへの信頼感も醸成されます。
こうしたポジティブなユーザー体験は、Googleの評価アルゴリズムにも好影響を与えます。
Googleの検索アルゴリズムに効果的なSEO対策

本項目では、Googleの検索アルゴリズムに効果的なSEO対策をご紹介します。
コンテンツ対策①:E-E-A-T・検索ニーズを満たすコンテンツ作成
E-E-A-T(Experience/経験、Expertise/専門性、Authoritativeness/権威性、Trustworthiness/信頼性)は、Google がコンテンツ品質を評価する指標として公開している概念であり、医療系サイトでは特に重要視される要素です。
正確で根拠のある医療情報を発信するために、医療スタッフが実際に経験した症例や治療実績をコンテンツに反映したり、専門医や看護師、管理栄養士など医療分野の資格保有者が執筆・監修したりすることが求められます。
また、厚生労働省や学術論文、ガイドラインなど信頼できる情報源を参照し、学会発表や論文引用など公的機関からの裏付けデータを掲載することで、権威性を高めることができます。
信頼性を保つためには、最新情報にアップデートし続けること、セキュリティ対策やプライバシーポリシーを整備し患者が安心して閲覧できる状態を保つことが大切です。
コンテンツ対策②:検索ニーズを満たすコンテンツ作成
医療系サイトには、患者やその家族、医療従事者同士など利用者の多様なニーズが集まります。
たとえば「●● 症状」で検索する人には原因や初期対応、受診目安をわかりやすく解説したページが求められ、「クリニック名+口コミ」と検索する人には実際の受診体験談や予約方法・アクセス情報などが重要となります。
検索キーワードとページ内容を連動させ、症例写真や解剖図、手順動画を挿入し専門用語をかみ砕いて説明するなど、読む人の背景を考慮しわかりやすい情報提供を心がけることが肝要です。
こうしたユーザーファーストの姿勢を継続することで、Google からも高い評価を得られ、検索上位表示につながりやすくなります。
ウェブサイト対策①:ユーザビリティの最適化
検索順位を上げるためには、ページが見やすく・使いやすい設計であることが欠かせません。
医療系サイトは症状や治療法を探す人にとって切実な場面が多いため、スムーズな閲覧体験はより重要となります。
スマートフォンからのアクセスが7割以上を占めるケースも珍しくないことから、モバイルフレンドリー対応を施し、小さな画面でも文字やボタンが見やすく、クリックしやすい配置にすることが求められます。
また、大きな画像や不要なスクリプトを削減しページ読み込み速度を改善することで、緊急時に検索した患者の離脱率を下げることができます。
ウェブサイト対策②:クローラビリティの最適化
Googleのクローラーがサイト全体をしっかり巡回し、ページをインデックス(登録)してくれることが上位表示への第一歩となります。
総合病院のように診療科が多岐にわたる場合は、サイトマップやパンくずリストを活用して階層を明確化し、ユーザーもクローラーもたどりやすい構造にすることが重要です。
また、カテゴリ構造が明確な URL を設定し、見出しを適切にマークアップしてクローラーがコンテンツ内容を理解しやすくすることも効果的です。
関連ページ間の内部リンクを最適化し、クローラーがリンクをたどることで新規ページも素早くインデックスされやすくなります。
このように「ユーザーにとって使いやすいサイト構造=クローラーにとっても巡回しやすいサイト構造」を意識することが、SEO 効果を高める基本となります。
外部対策①:被リンク獲得
被リンク(外部リンク)は、他のサイトから自サイトへ向けられたリンクのことであり、被リンクが多いサイトは「多くの人が参照する価値のあるコンテンツ」とみなされ、検索アルゴリズム上でも高評価につながります。
医療系サイトにおいては、学会が公表する情報への執筆協力や病院連携先のサイトからの紹介リンク、在宅医療サービスや地域の福祉関連機関の公式サイトからの紹介など、権威のある医療系サイトや関連法人からのリンクを獲得することが有効です。
外部対策②:サイテーション獲得
サイテーションは、SNSなどで「●●病院で受診して症状がよくなった」「このサイトにわかりやすい説明があった」などの言及が増えることを指します。
ドクターや看護師が専門分野について発信し患者や家族からシェア・リツイートされたり、地域の新聞・雑誌・ネットメディアが取り上げてくれたりすることで、サイテーションが自然に増えていきます。
また、患者が書き込む口コミは、サイト運営者がコントロールできないものの、内容を真摯に受けとめ医療サービスの質を向上させることで、良質な口コミが積み重なり外部からの評価が上がり、検索アルゴリズムの評価にも寄与しやすくなります。
ただし、被リンク獲得を急ぐあまりリンク買い取りなどの不自然な行為に手を出すと、Google からペナルティを受ける場合があります。
医療系サイトがペナルティを受けると信頼性が大きく損なわれるため、あくまで自然な形で被リンクやサイテーションを得ることを心がけることが肝要です。
Google検索アルゴリズムの変遷

本項目では、特に重要なものにしぼり、Google検索アルゴリズムの変遷について、わかりやすく解説します。
パンダアップデート(2011年2月)
パンダアップデートは、2011年2月に導入されました。
このアップデートは、コンテンツの品質を重視し、重複やコピーが多いページや、単に文字数を増やすだけで中身が薄い「低品質コンテンツ」を排除することを目的としています。
医療系サイトにおいては、他の医療サイトや論文をそのままコピペしたり、リライトツールで文章を置き換えただけのコンテンツは評価が下がりやすくなりました。
一方で、医師や管理栄養士が実際の症例を踏まえて執筆し、患者が知りたいポイントを詳しく解説しているコンテンツは高く評価されるようになりました。
対策としては、独自性のある情報を提供することが重要です。
例えば、「糖尿病診療の流れ」を自院の実践例とともに写真や図表を交えて解説するなどの工夫が考えられます。
また、論文や学会ガイドラインの引用、執筆者と監修者のプロフィールをしっかり掲載するなど、専門家による監修・引用元の明示も求められます。
ベニスアップデート(2014年12月)
ベニスアップデートは、2014年12月に実施され、日本でも同時期に波及しました。
このアップデートは、ユーザーの位置情報(ローカル要素)を検索結果に反映するアルゴリズムです。
例えば、「歯医者」「内科」など地域名を指定しなくても、検索した場所に近い施設が上位表示されやすくなりました。
医療系サイトにおいては、「内科」とだけ検索しても、検索者の最寄り地域にある内科やクリニックが上位に表示されるようになりました。
また、駅前の耳鼻科や産婦人科など、位置情報を明示するサイトやGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を適切に設定していると、患者が「近場の病院」を探すときに選ばれやすくなりました。
対策としては、Googleビジネスプロフィールの最適化が重要です。
診療時間や電話番号、ホームページのURLを正確に登録しておくことが求められます。
また、ウェブサイト内に「●●駅から徒歩5分」「●●市●●区」といった文言を盛り込み、アクセスマップや駐車場情報などをわかりやすく掲載することも有効です。
ペンギンアップデート(2012年4月)
ペンギンアップデートは、2012年4月に初回実施され、その後、コアアルゴリズムに統合されました。
このアップデートは、不自然なリンクやスパム手法を取り締まるためのアルゴリズムで、自作自演の被リンクや、無関係なサイト同士での相互リンクにより検索順位を操作する行為を厳しく評価します。
対策としては、自然なリンク獲得を目指すことが重要です。
例えば、学会発表や地域医療の取り組みを通じて、外部メディアや公的機関に取り上げてもらうなどの工夫が考えられます。
また、無料ブログの量産や「リンクプログラム」の利用を避けるなど、不自然なリンクを排除することも求められます。
もし過去に不正リンクを利用していた場合は、リンク否認ツール(Googleサーチコンソール)での対処を検討する必要があります。
パイレーツアップデート(2012年8月)
パイレーツアップデートは、2012年8月、2014年10月と実施されました。
このアップデートは、著作権(コピーライト)の侵害コンテンツを大きく取り締まるアルゴリズム更新です。
海賊行為=不正アップロードや盗用などを厳しく評価し、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づいて削除申請されたサイトをランキングで下げる仕組みが導入されました。
医療系サイトにおいては、他病院のホームページの内容を無断でコピペする、医療論文や学会資料を出典も示さず転載する行為がペナルティ対象になり得ます。
また、手術風景やレントゲン写真を他サイトから無断転載して説明ページを作るなど、著作権を明記しない・許諾を得ないまま使用する行為は検索順位を下げられるリスクがあります。
対策としては、必ず許諾を得た画像やテキスト、研究データを使用することが重要です。
また、引用ルールの遵守(引用タグ・引用元リンク・参考文献の明示など)や、患者や自院スタッフによる独自写真・イラストなどのオリジナルコンテンツの制作も有効です。
ハミングバードアップデート(2013年9月)
ハミングバードアップデートは、2013年9月に実施されました。
このアップデートは、会話型や曖昧なキーワードの検索意図をより正確にくみ取るためのアルゴリズム刷新です。
口語表現や文脈からキーワードの背景を理解し、より適切なページを表示することが可能になりました。
音声検索やスマートスピーカーでも使われる重要な技術基盤となっています。
医療系サイトにおいては、ユーザーが「こどもの夜泣き どうしたらいいの?」と検索したとき、「夜泣き対策」「小児科受診の目安」など関連する情報を含むページが評価されやすくなりました。
また、患者が「お腹がチクチク痛むんだけど病院どこ?」といった検索をした場合、「消化器内科」「婦人科」など症状に応じた関連情報を総合的に提供するページが上位表示されやすくなりました。
対策としては、ユーザーの自然な質問を想定し、「症状+どうすればいい」「どんな治療法がある?」など、具体的な問いに対応した情報をQ&A形式でまとめることが有効です。
また、「胃痛」「腹痛」「消化器科」「検査」「治療」など近しい語を文脈として自然に盛り込むと、検索エンジンが内容を理解しやすくなります。
モバイルフレンドリーアップデート(2015年4月)
モバイルフレンドリーアップデートは、2015年4月に実施され、2016年5月に強化が行われました。
このアップデートは、スマホ対応していないサイトの評価を下げるアルゴリズムです。
スマホユーザーの増加に伴い、ページがモバイル端末で見やすい構成かどうかが検索順位に大きく影響するようになりました。
対策としては、Googleの公式ツールであるモバイルフレンドリーテストを実施し、文字サイズや要素間の距離をチェックすることが重要です。
また、患者がスマホ操作でも誤タップしないよう、タップ領域やレイアウトを工夫することが求められます。
さらに、不要なスクリプトを削減したり、画像を軽量化したりするなどでページ読み込みを高速化し、離脱率を下げることも有効です。
健康アップデート(2017年12月)
健康アップデートは、2017年12月に日本国内のみで実施された異例のアルゴリズム改変です。
このアップデートは、医療や健康関連の検索結果を精査するために導入され、YMYL(Your Money or Your Life)に該当するような、人々の健康や生活に直結する情報の質を重視し、医学的根拠のない情報を上位に表示させないようにする目的で行われました。
医療系サイトにおいては、サプリや食事療法を「万病に効く」とうたっているが科学的根拠が薄いコンテンツなど、医学的根拠のない治療法の記事が順位下落する一方で、医師・看護師・薬剤師などの資格保有者が執筆または監修し、論文やガイドラインを参考にした治療法の解説ページは評価が高まりました。
対策としては、執筆者がどの科の医師か、所属学会や論文実績を記載するなど、専門家のプロフィールとエビデンスを明示することが重要です。
また、ガイドライン改定や新薬の登場などを速やかに反映し古い情報はアップデートするなど、最新情報・更新頻度を高めることも求められます。
さらに、医療専門用語だけでなく一般的な表現にも言い換え、誤解を生まないよう工夫するなど、患者目線のわかりやすい解説を心がけることも有効です。
スピードアップデート(2018年7月)
スピードアップデートは、2018年7月以降に実施されたアップデートで、ページ読み込み速度(特にモバイル版)を検索順位評価の要素として組み込みました。
ページ表示に時間がかかりすぎるサイトは、ユーザー体験を損ねると判断され、順位が下がる可能性が高まります。
対策としては、高画質が必要な場合でもWebP形式や適切な圧縮を活用するなど、画像や動画の軽量化が重要です。
また、ユーザー所在地に近いサーバーからコンテンツを配信できるキャッシュやCDNの導入も、読み込み速度の向上につながります。
さらに、医療系サイトでも不必要な装飾やアニメーションは極力減らしてページを軽くするなど、無駄なスクリプトやプラグインを削除することも有効です。
ページエクスペリエンスアップデート(2021年6月)
ページエクスペリエンスアップデートは、2021年6月にモバイル版で実施され、2022年2月~3月にPC版にも適用されました。
このアップデートでは、ユーザー体験(UX)を評価する指標「Core Web Vitals(LCP・FID・CLS)」が検索順位に反映されるようになりました。
さらに、HTTPSの導入やインタースティシャル広告(画面が切り替わる際に表示される広告)の排除など、ユーザーが快適にサイトを閲覧できる環境かどうかが総合的にチェックされるようになりました。
医療系サイトにおいては、ページ読み込み中にレイアウトがズレて予約ボタンや「受診科目を探す」リンクが押しづらくなるなど、レイアウトの安定性(CLS)が悪いページでは、ユーザーがストレスを感じ離脱する恐れがあります。
また、患者が個人情報を入力する問い合わせフォームが安全でない場合、信頼度が下がり検索評価も低下する可能性があります。
さらに、ページを開いた瞬間に画面全体を覆うポップアップで診療案内やキャンペーンを表示するなど、インタースティシャル広告の過剰表示はユーザー体験を損ねるとしてマイナス評価の対象となります。
対策としては、PageSpeed InsightsやSearch Consoleのレポートを活用し、LCP(表示速度)、FID(操作応答性)、CLS(レイアウト安定性)を定期的に確認するなど、Core Web Vitalsのモニタリングが有効です。
また、個人情報を扱う医療系サイトには必須のHTTPS化や最新のSSL/TLS証明書の導入などセキュリティ対策も必須です。
さらに、デザインやコンテンツ配置を患者の利用場面に合わせて最適化し、煩わしい広告や大きなポップアップは可能な限り削減するなど、UX向上を最優先することも肝要です。
ヘルプフルコンテンツアップデート(2022年8月)
ヘルプフルコンテンツアップデートは、2022年8月以降、英語圏から始まり段階的に拡大しているアップデートです。
このアップデートは、”ユーザーのために作られた独自性の高いコンテンツ”を正しく評価し、検索結果で上位表示しようとする取り組みの一環であり、今後は日本語を含む多言語にも適用が進む見込みです。
ユーザーの検索意図を満たし、かつ有益で信頼できる情報を提供できるサイトが評価されやすくなります。
医療系サイトにおいては、同じ病気の説明を使い回ししつつ広告リンクばかり並べているコンテンツなど、ユーザー目線が欠如したコンテンツが順位下落する一方で、実際に医師や看護師が監修した「糖尿病患者が知っておくべきインスリン注射のポイント」「通院時の注意点」などは、独自の専門知識と患者視点が融合した”ヘルプフル”な記事として評価されやすくなりました。
対策としては、医療従事者の実名や所属、経歴を明記し記事の裏付けを明確にするなど、専門家による解説・監修が重要です。
また、他院サイトとの差別化(症例数や独自の治療方法など)と、患者が抱きそうな疑問への回答をセットで提供するなど、独自性と網羅性のバランスを取ることも求められます。
さらに、AIやテンプレートの一括生成ではなく人の目でチェック、監修を行い、正確性と読みやすさを担保するなど、自動生成コンテンツには注意が必要です。
2023年以降のGoogleアルゴリズムアップデート
2023年以降、Googleのコアアルゴリズムアップデートが複数回実施されています。
主な共通の傾向としては「コンテンツ評価の比重増加」「ドメイン全体の信頼度や専門性の重視」が挙げられます。
特に医療系サイトではYMYL(Your Money or Your Life)という概念が強く作用するため、正確性・専門性の確保がより一層重要となっています。
代表的なアップデート例としては、2023年3月コアアルゴリズムアップデートではコンテンツの専門性やドメインテーマの整合性をより重視する傾向が見られ、2023年8月コアアルゴリズムアップデートでは「コンテンツ評価 vs ドメイン・運営元評価」「特化型 vs 網羅型」などを見極める方向性が示唆されました。
医療系サイトにおいては、内科全般を扱うよりも「糖尿病」に特化して深く情報提供しているサイトのほうが専門性が高いと認識される場合があるなど、専門領域を絞ったサイトの評価が高まりやすい傾向にあります。
また、総合病院のサイトであれば各診療科の情報がバランスよく掲載されているか、一方で大学病院レベルの高度専門領域を深掘りしているかなど、コンテンツの網羅性と特化性のバランスも重要視されます。
さらに、当時のまま放置している古い治療法の記載、誤った用語やデータが含まれるページ、あるいは不自然に外部リンクを貼っているページが存在すると、ドメイン全体の評価が下がる可能性があるなど、マイナス面の炙り出しによる評価低下リスクにも注意が必要です。
対策としては、多診療科を扱うサイトでもそれぞれのページに専門家の監修を入れるなど、コンテンツの質を一定以上に維持し、ドメイン全体のテーマ整合性を向上させることが重要です。
また、学会ガイドラインやエビデンスに合わせて記事を定期的にリライトし最新情報を維持するなど、古い情報の継続的アップデートも求められます。
さらに、スパム的なリンクや重複コンテンツ、著作権に抵触する素材の利用などを徹底的に見直し、全体の信用度を上げるなど、ネガティブ要因の排除も肝要です。
Google検索アルゴリズムにおける順位変動の理由と対策

本項目では、Google検索アルゴリズムにおける順位変動の理由と対策についてお伝えします。
一時的な変動
地域や時間帯、検索条件のわずかな違いによっても、検索結果が微妙に変わることがあります。
また、ニュースなど時事性が高いトピックが急上昇すると、それに関連するキーワードで一時的に上位に入れ替わるサイトが増え、相対的に順位が押し下げられる場合があります。
対策としては、まず数日~1週間程度様子を見ることが挙げられます。
すぐにリライトや修正を行わず、再び順位が戻るケースも多いので、まずは観察するのがよいでしょう。
また、SEOツールで順位を定期的にチェックし、変動のパターンや傾向を把握することで、一時的な変化なのか長期的な下落なのかを見極めることができます。
さらに、一時的に台頭してきた記事は何が評価されているのかを把握し、必要に応じて自サイトのコンテンツを改善するのも有効です。
例えば、新薬関連の最新情報を追加したり、患者が知りたい情報をよりわかりやすくまとめたりすることが考えられます。
記事を公開して間もない
新規記事は、Googleが内容をインデックスし評価するまでに時間がかかり、不安定な順位変動を起こしやすい傾向にあります。
特に新ドメインの場合は、サイト全体の評価が定まっていないため、より順位が付与されにくくなります。
対策としては、最低1か月程度は様子を見ることが重要です。
すぐにリライトや修正を繰り返すと、記事の評価軸を見失い、本来得られる評価ポイントを消してしまう恐れがあるためです。
また、Search Consoleでインデックス状況を確認し、「インデックス登録リクエスト」を送信してクローラーが記事を素早く発見できるようにすることも有効です。
情報が古くなった
時間が経過して内容が陳腐化していると、検索エンジンの評価が下がりやすくなります。
競合サイトが最新の研究成果やガイドラインを反映した記事をリライトしていくと、相対的に古い情報のページが順位を落としがちです。
対策としては、新しい診療ガイドラインや研究成果、学会発表の内容などを取り入れ、情報を更新するリライトや更新が有効です。
大幅改訂が必要な場合は、新規記事として再構築し旧記事から301リダイレクトを行うことも検討するとよいでしょう。
また、サイト内の記事を半年や1年などのタイミングで棚卸しし、医学的情報の鮮度をチェックする定期的なコンテンツ監査も重要です。
重複コンテンツだと認識された
同じ内容や類似度が高いテキストが、異なるURLで複数存在している場合、「重複コンテンツ」と判断されることがあります。
また、サイト内(サブドメイン含む)で同テーマの記事が複数あり、評価が分散してしまう「カニバリゼーション」も起こりやすくなります。
もちろん、他サイトとほぼ同じ情報を転載・引用している場合も、検索エンジンからは「オリジナリティがない」と見なされるリスクがあります。
対策としては、まず「site:自社ドメイン キーワード」の検索で、同じキーワードに対して別URLのページが上位化していないかチェックすることが重要です。
重複ページが見つかった場合は、内容がほぼ同じなら最も評価を受けているページへ301リダイレクトを行います。
また、必要に応じてcanonicalタグを用いて、検索エンジンに「どのページが正規なのか」を明示することも有効です。
さらに、医療機関では症例報告や医師コメントなど専門家独自の視点・情報を加筆することで、独自性を打ち出しやすくなります。
ウェブページのhead要素の記述ミス
「title」や「meta description」、「canonical」、「robots」など、検索エンジンへの指示を行うタグに誤った記述があると、ページが正しくインデックスされない・検索結果から除外されるなどのトラブルが起きることがあります。
ページ更新時に「noindex」を誤って設定したり、正規URLの指定を間違えたり、リダイレクト先を誤設定していたりすることが原因として考えられます。
対策としては、ページ修正後に特に「title」、「robots meta」、「canonical」、「meta description」に変更がないかを確認することが重要です。
また、Search Consoleでインデックス状況を確認し、Googleがインデックスを拒否しているページがないか、エラーや警告メッセージをこまめにチェックすることも有効です。
さらに、テストサーバーで作業した際の「noindex」やリダイレクト設定を本番リリース時に確実に解除するルールを整備したり、同じようなコンテンツを複数URLで展開する場合は検索エンジンにどちらが正規かを明示して重複認識を回避するcanonical設定を正確に行ったりすることが求められます。
スパム判定などペナルティを受けた
Googleの品質ガイドラインに違反する行為(不自然リンクの購入・クローキング・隠しテキストなど)で手動ペナルティを受けたり、過度な相互リンクやリンクファームなどでサイト全体の信頼性が低下していたりすると、順位変動の要因となります。
また、コンテンツがコピー・自動生成など低品質と判断されると、アルゴリズム上のペナルティによって順位が大幅下落、あるいはインデックス削除されることがあります。
対策としては、まずSearch Consoleの「手動による対策」を確認し、警告メッセージが出ている場合はどの行為がガイドラインに違反しているかを特定して修正することが重要です。
また、外部サイトへの削除依頼、あるいはリンク否認ツールを活用して不自然リンクを削除・否認し、ペナルティを解除できるよう手続きを進めることも有効です。
さらに、クローキングや隠しテキストなどブラックハット手法があれば速やかに削除し、再審査リクエストを提出することも求められます。
加えて、医師や薬剤師が監修した正しい情報を提供し、ユーザーにとって有益な医療コンテンツを充実させることで、専門家監修の質の高いコンテンツを用意することも重要です。
ガイドライン遵守を徹底し、再評価を待ちましょう。
アップデートによりアルゴリズムが変更された
Googleは日々細かなアルゴリズムを調整しており、さらに年に数回、大規模なコアアルゴリズムアップデートが行われます。
特にコアアップデートでは、医療や健康などYMYL(Your Money or Your Life)領域の情報精度が厳しくチェックされる傾向があります。
アップデートの内容は公式に詳細が公表されるわけではなく、「信頼性の高い情報を上位にする」などの概略のみの発表が中心です。
そのため、急に評価基準が変わり、検索順位が下がってしまうことがあります。
対策としては、Google検索セントラルや信頼できるSEO情報サイトを常にウォッチして、アップデートの時期や概要を把握することが重要です。
また、医師や薬剤師など専門家が監修したエビデンスの明示、最新のガイドラインへの対応などを積極的に行い、医療コンテンツの信頼性を高めることも有効です。
さらに、コアアップデートがある度に慌てて修正するのではなく、日ごろから情報の鮮度を保ち、医療現場の最新知識に合わせてページを更新することも求められます。
記事リライトやサイト自体の評価向上により相対的に競合が強くなった
自社サイト側は特段の落ち度がなくても、競合が積極的にリライトやサイト全体の品質改善を行ったことで検索評価が高まり、相対的に自サイトの順位が下がるケースがあります。
高品質な外部リンクを得たり、SNSでの拡散によりサイト認知度が上がった競合が、Googleからの信頼度を高めて上位に浮上した場合もあります。
対策としては、競合のコンテンツを分析し、医療系ならではの専門情報(症例写真、論文の引用、学会の参加報告など)をどのように強化しているか確認することが重要です。
また、長期的な視点で記事を定期的に見直し、検索ニーズや最新医療情報を踏まえた更新を継続的に実施することも有効です。
さらに、専門家による見解や患者の体験談・インタビューなどを積極的に取り入れ、より説得力のあるコンテンツにすることも求められます。
加えて、医療分野では特に重要視される指標であるE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)を意識し、資格や経歴の明示、実績の提示、運営者情報の明確化などを強化することで、サイトの評価向上を図ることも肝要です。
まとめ

Google検索アルゴリズムは、膨大なウェブページの中から、ユーザーの検索意図に最も合致し、役立つ情報を見つけ出して適切な順位で表示するための、ルールと計算方式の総称です。
医療従事者にとって、このアルゴリズムを理解し、SEO対策を講じることは、患者への有益な情報提供と検索順位の向上に欠かせません。
アルゴリズムは頻繁にアップデートされ、コンテンツの品質や専門性、ユーザー体験の向上などを重視する方向で変遷してきました。
特に医療系サイトでは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の要素が重要視され、医師や専門スタッフによる監修、信頼できるエビデンスの提示、最新情報へのアップデートなどが求められます。
また、患者目線でのわかりやすい解説、症例写真や図表の活用、Q&A形式での疑問解決など、ユーザーの検索意図に合致したコンテンツ設計も肝要です。
ェブサイト全体としても、モバイルフレンドリー対応、ページ速度の改善、ナビゲーションの最適化など、ユーザビリティとページエクスペリエンスの向上が重要となります。
さらに、自然な被リンクやサイテーションの獲得、不自然なリンクの排除、ドメイン全体のテーマ整合性の維持など、サイト内外の要因にも注意を払う必要があります。
Google検索アルゴリズムにおける順位変動の理由として、一時的な変動、記事を公開して間もない、情報が古くなった、重複コンテンツだと認識されたなどが挙げられます。
弊社では、これらのGoogleアルゴリズムの動向を踏まえ、医療機関に最適なSEO対策をご提案しております。
専門性の高いコンテンツ制作、患者目線でのユーザビリティ改善、サイト内部構造の最適化など、貴院のニーズに合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。
ウェブサイト制作やSEOをはじめとした集患対策でお悩みの際は、ぜひ弊社サービスをご活用ください。
お問い合わせは、専用フォームまたはお電話より承ります。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。











