サイトリニューアル時のSEO|9つの注意点、手順など解説!
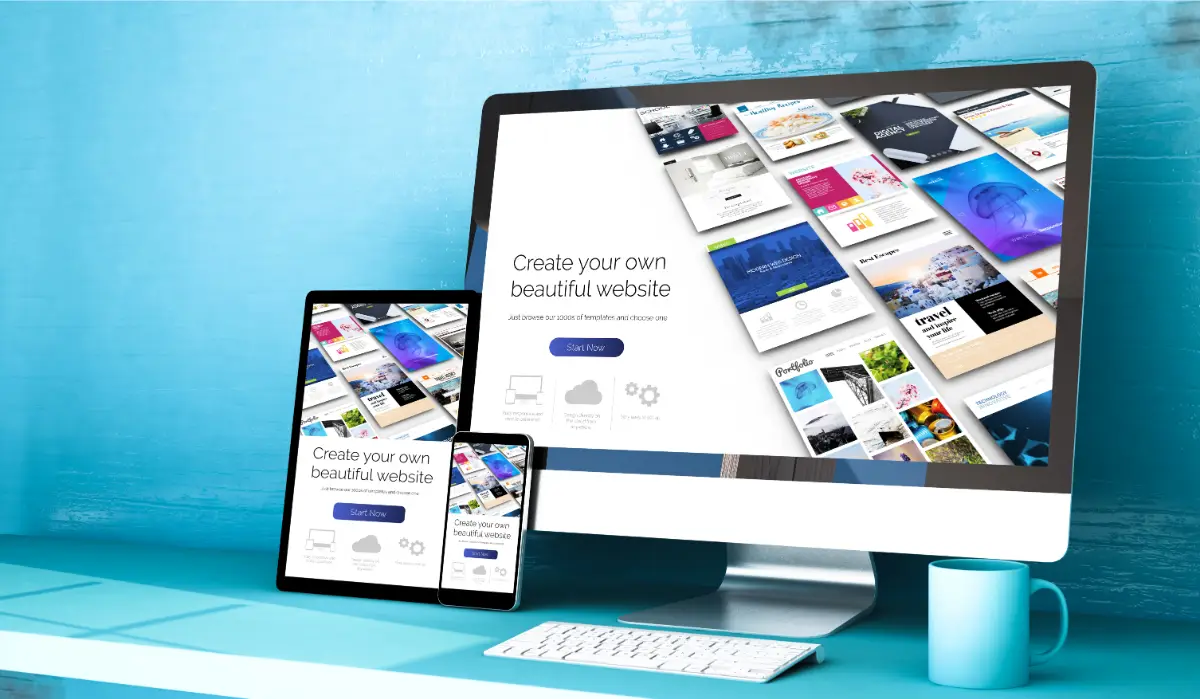
「リニューアル時、SEOで気を付けることはなに?」
「ウェブサイトリニューアルで気を付ける点は?」
ウェブサイト運用もさることながら、ウェブサイトのリニューアルもまた大仕事ですよね。。
本記事では、サイトリニューアルにおけるSEOの注意点、サイトリニューアルのタイミングなど解説します。
ぜひご一読いただき、貴院のサイトリニューアルやSEO対策にお役立てください。
Contents
サイトリニューアルを行うべきタイミング

ウェブサイトのリニューアルは、SEO対策の観点から見ても非常に重要です。
ここでは、医療機関のサイトにおいて、リニューアルを検討すべきタイミングについて、ご説明します。
サイトのデザインが古く感じたとき
医療機関のウェブサイトは、信頼感を与えるデザインが非常に重要ですが、公開から5年も経過すると、時代遅れの印象を与えかねません。
競合他院と比較して見劣りすれば、患者が不信感を持つかもしれません。
そのため、近隣医療機関のサイトを分析するなどして、最新のトレンドを積極的に取り入れることが求められます。
具体的には、フラットデザインなど現代的な手法を採用する、ロゴやメイン・サブカラーを一新するなどが挙げられるでしょう。
加えて、高品質な写真や動画を活用して、医療機関の最新の雰囲気や特長を効果的に伝えることも忘れてはなりません。
最新バージョンのブラウザに対応していない
ブラウザは常にアップデートされており、古いバージョンのみに対応したサイトでは、レイアウト崩れや機能障害が発生する可能性が高くなります。
その結果、患者はサイトを快適に利用できなくなってしまいます。
このような事態を防ぐために、定期的に最新ブラウザでの動作確認を行い、不具合を迅速に修正することが重要です。
合わせて、FlashやSilverlightなどの古いプラグイン技術からHTML5やCSS3などの現代的なウェブ標準技術に移行することも強く推奨されます。
これにより、ブラウザの種類や版数に依存せず、安定した動作を保証できるようになります。
モバイルに対応していない
現在、インターネット利用者の約7割がスマートフォンを使用しており、特に若年層や忙しい患者にとって、スマホ対応は必須要素となっています。
レスポンシブデザインを導入し、どのようなデバイスからアクセスされても見やすく使いやすいレイアウトを実現することが求められます。
具体的には、画面サイズに応じて要素の配置や大きさを自動的に最適化し、タップやスワイプといったタッチ操作に適したインターフェースを提供することが重要です。
さらに、よく利用されるページ、例えば診療時間やアクセス情報、予約フォームなどを優先的に表示するモバイルファーストの設計手法を採用することで、患者の利便性を大幅に向上させることができるでしょう。
ページの表示速度が遅い
表示速度の遅さは、閲覧者の離脱率上昇や潜在的な患者の逃失につながる深刻な問題です。
サイトの表示速度を改善するためには、GoogleのPageSpeed Insightsなどの速度測定ツールを活用し、具体的な課題を特定、原因に応じた対策を講じる必要があります。
例えば、画像や動画のファイルサイズが大きい場合は、適切な形式への変換や圧縮により軽量化を図ります。
CSSやJavaScriptのファイルを最適化することも効果的です。
また、サーバー側の設定や通信環境の見直しも重要な検討項目です。
キャッシュの活用やCDNの導入により、レスポンスタイムを短縮できるでしょう。
サイト構造が複雑、コンテンツが煩雑になっている
サイト構造が複雑な場合やコンテンツが煩雑になっている場合、抜本的な見直しが求められます。
まず、サイトの目的と主要なターゲットを再確認し、優先すべき情報を明確にします。
そして、それらを基にサイトマップを再構築し、直感的にわかる階層構造を設計します。
また、ナビゲーションメニューの整理や、検索機能の最適化も欠かせません。
利用者がスムーズに目的のページにたどり着けるよう、動線を整備しましょう。
合わせて、コンテンツの内容面でも、ページごとの情報量や記述の簡潔さ、視覚的な見やすさなどを再点検するとよいでしょう。
ユーザビリティを改善したい
ウェブサイトのユーザビリティは、訪問者が目的を達成するための使いやすさや快適さを表す指標であり、医療機関のサイトにおいても重要な要素です。
特に、高齢者やスマートフォンユーザーが増加する中、あらゆる利用者に配慮したデザインが求められています。
ユーザビリティの改善には、アクセス解析ツールを活用し、閲覧者の属性や動線、離脱ポイントなどを詳細に分析することが必要です。
それをもとに、スマートフォンでの閲覧に適したレスポンシブデザインの採用や、タップやスワイプ操作に適した要素の配置などを再考するとよいでしょう。
また、高齢者に配慮した文字サイズやカラーコントラストの設定、わかりやすいアイコンの使用なども重要です。
新機能を導入したい
オンライン予約システムや問診票のウェブ記入、遠隔診療システムなど、患者の利便性を高める新機能の導入は常に求められます。
これらを取り入れることで、患者の待ち時間短縮や診療の質向上、通院困難な方へのサポートなど、多くのメリットが期待できます。
一方、新機能の導入にあたっては、慎重な検討が必要です。
まず、コストや既存システムとの連携、患者への周知方法などを十分に吟味しなければなりません。
さらに、スタッフの教育や業務フローの見直しといった組織的な対応も欠かせません。
新機能の導入は、医療機関の競争力強化につながる一方で、その実現には多角的な視点と綿密な準備が求められます。
サイト運用の効率化を図りたい場合
医療機関のウェブサイトには、診療科情報や医師のスケジュール、お知らせなど、頻繁に更新が必要なコンテンツが数多く存在します。
これらを適切に管理し、常に最新の情報を提供できなければ、患者からの信頼を失いかねません。
サイト運用の効率化を図るためには、CMSの導入が有効です。
CMSを活用することで、専門的な知識がなくてもスタッフが簡単にコンテンツを更新できるようになります。
合わせて、運用マニュアルを作成し、ナレッジを蓄積することで、担当者が変わっても一定の品質を維持できるでしょう
ブランドイメージの変更を考えている場合
医療機関は、時代の変化や経営戦略に合わせて、ブランドイメージを変更する必要に迫られることがあります。
新たな診療科の開設やターゲット患者層の変更、地域医療への注力などがその代表的な例でしょう。
ブランドイメージの刷新にあたっては、ウェブサイトが重要な役割を果たします。
まず、ロゴやカラー、フォントなどのデザイン要素を見直し、新しいブランドコンセプトを視覚的に表現するとよいでしょう。
また、トップページのメッセージや診療科ごとのキャッチコピーなども、ブランドの方向性に合わせて変更する必要があります。
一方、ブランドイメージの変更は、既存の患者に混乱を与えるリスクもはらんでいます。
ウェブサイトの刷新と並行して、院内掲示やパンフレットなども更新し、ブランドの一貫性を保つことが求められるでしょう。
サイトリニューアルの一般的な流れや手順
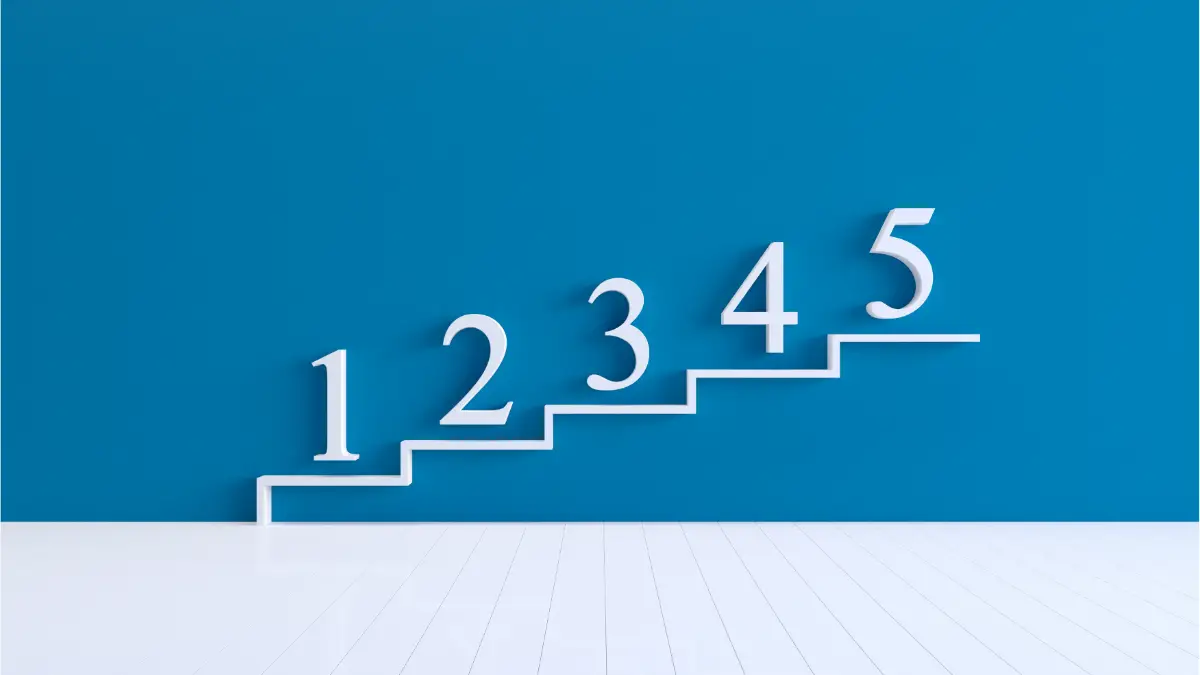
本項目では、サイトリニューアルの一般的な流れや手順について、ご説明します。
サイトリニューアルの目的と目標数値を設定
リニューアルを成功に導くためには、明確な目的を定めることが不可欠です。
曖昧な目的では、プロジェクトの方向性が定まらず、効果的なリニューアルが難しくなります。
目的の例としては、新患や利用者の増加を目指す「集客増加」、医師や看護師の採用数を増やす「採用強化」、サイト運用の効率化を図る「業務改善」などが挙げられます。
それぞれの目的に応じて、具体的な数値目標を設定しましょう。
例えば、集客増加では「月間予約件数20%増、サイト訪問者数30%増加」、採用強化では「サイト経由の応募数を月10件増やす」といった目標が考えられます。
現状の課題を洗い出し、数値目標を具体化することで、成果の測定が可能になります。
自サイト・競合サイトを分析する
自社サイトと競合サイトを比較分析することで、自社サイトの課題や改善ポイントが明確になります。
自サイト分析では、Googleアナリティクスを活用してアクセス数や滞在時間、離脱率などを確認し、「診療科の情報が少ない」「スマホ表示が見にくい」といった課題を洗い出します。
一方、競合サイト分析では、デザインの洗練度、オンライン予約や患者口コミ表示などの機能、SEOパフォーマンスなどを観点に、優れた事例を参考にします。
例えば、競合が導入している「簡単な症状チェック機能」を自社でも採用するといった具合です。
分析にはAhrefsなどのSEOツールを活用し、キーワードランキングやトラフィックを調査するほか、ユーザーアンケートを通じて患者の使い勝手や改善希望を反映するのも有効でしょう。
要件定義をまとめる
リニューアル後のサイトに必要な要件を整理し、明確にすることが目的です。
この段階で目標と課題解決策を具体化し、設計や開発に役立つ情報を文書化します。
基本情報としては、WordPressなどのCMSを使用したサイト構築方法や、オンライン予約、症状別の診療案内、問い合わせフォームの簡略化といった必要機能を定義します。
課題解決策としては、画像最適化とキャッシュ利用によるページ速度の向上や、レスポンシブデザインの導入によるモバイル対応などが考えられます。
これらの要件を提案依頼書(RFP)としてまとめ、現行システムの状況、期待する機能、開発スケジュールなどの情報を盛り込みます。
サイト構造を設計する
この工程における目的は、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるように、サイト全体の構造を整理することです。
具体的には、サイトマップを作成し、サイト全体のページ構成を一覧化します。
トップページから各診療科の詳細ページ、お問い合わせページまでの階層やリンクの関係性を明確にすることが重要です。
次に、各ページの要素(ロゴ、メニュー、CTAボタンなど)を配置したワイヤーフレームを作成します。
これにより、ユーザー導線を視覚化し、関係者間で共通理解を得ることができます。
また、目的の情報に3クリック以内で到達できる構造を目指すことで、ユーザービリティを高めることができるでしょう。
デザインを決定する
デザインはサイト全体の印象を左右する重要な要素であり、機能性と見た目のバランスを取りながら、ターゲット層に適したデザインを採用することが求められます。
例えば、高齢者がターゲットの場合は、大きな文字サイズやシンプルな配色を採用し、若年層がターゲットの場合は、モダンで視覚的に訴求力のあるデザインを選択するといった具合です。
また、ブランディングに基づいたカラーやフォントを決定することも重要です。
医療系サイトの場合、青や緑など清潔感のある色を使用することが推奨されます。
デザイン案が確定したら、TOPページから下層ページへと展開していきます。
コンテンツ作成とSEO対策
コンテンツは、ユーザーに価値を提供する核となる部分であり、SEO対策を施すことで検索エンジンからの流入増加も期待できます。
まずは、ユーザーのニーズを調査し、ターゲットに応じた適切なコンテンツを準備します。
例えば、「初めての来院の流れ」や「症状別診療ガイド」といったコンテンツを追加することで、ユーザーの満足度を高めることができるでしょう。
コンテンツ作成の際は、SEOツールを活用してキーワードを明確にし、キーワードを自然に散りばめたテキストを作成するとよいでしょう。
もちろん、過剰なキーワードの詰め込みは避け、自然な流れで情報を伝えることが重要です。
また、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識してコンテンツ作成することで、検索エンジンからの評価も高まります。
サイト構築とテストを行う
デザインとコンテンツが確定した後、実際のサイト構築に進みます。
この工程では、社内チームあるいは制作会社が中心となり、技術的な実装を行います。
具体的には、デザインカンプをもとにHTML/CSSやJavaScriptを用いてコーディングを行い、WordPressなどのCMSを使用する場合は、プラグインやテーマのカスタマイズを含めた動的な構築を実施します。
また、サーバー環境の整備では、適切な設定(PHPバージョン、SSL証明書など)の適用やメールフォーム・データベースの接続確認が必要です。
構築が完了したら、ステージング環境でテストサイトを公開し、各ブラウザ・デバイスでのデザイン表示、ボタンやフォームの動作、読み込み速度などを入念に検証します。
サイトを公開する
テストが完了し、修正が反映された段階で、サイトを正式に公開します。
この工程では、公開中のトラブルを防ぐための準備が肝心です。
まずは、テストサイトで行った確認項目を再度チェックし、ドメイン設定やDNSの確認します。
公開作業は、アクセスの少ない時間帯に行うのが望ましく、必要に応じてメンテナンス画面を表示します。
公開直後には、ページ読み込み速度、SEO設定、サーバーログのエラーの有無などを確認し、社内チームや顧客、取引先などに新サイトの公開を周知します。
重要なデータのバックアップを事前に取得し、サイトが一時的にダウンする場合に備えて代替案を準備しておくことも忘れてはなりません。
(サイト公開後)運用・保守を行う
公開後のサイトは、運用・保守を通じて最適化や安定性を確保します。
このフェーズでは、トラブルの早期発見と改善が求められます。
定期的な更新と改善では、新しいコンテンツの追加やアクセス解析ツールを用いたパフォーマンス測定と改善点の特定が重要です。
セキュリティ対策としては、CMSやプラグインの定期的なアップデートが欠かせません。
また、サーバーデータやデータベースの定期バックアップを自動化し、外部ストレージに保存することでリスク分散を図ります。
アクセス数や問い合わせ数の変動を継続的に観察し、異常があれば速やかな対応が求められます。
サイトリニューアルでアクセス数が減ったときの確認ポイント

本項目では、サイトリニューアルでアクセス数が減ったときの確認ポイントについてご説明します。
検索エンジンからのクロールを拒否していないか確認
リニューアル時にテスト環境で設定したクロール拒否が、本番環境にそのまま適用されるミスはしばしば発生します。
これにより、検索エンジンがサイトを巡回できず、検索結果に反映されなくなる場合があります。
確認方法としては、Google Search Consoleの「ページ」で「ページがインデックスに登録されなかった理由」を参照するか、または、robots.txtに「Disallow: /」の記述がないかを確認します。
さらに、サーバー側でクローラーのアクセスを拒否していないか、特にIP制限やファイアウォール設定を確認することが必要です。
対策としては、テスト環境専用のクロール拒否設定を本番環境に適用しないようにし、修正後、Google Search Consoleの「URL検査ツール」を使用して、修正されたページがクロール可能であることを確認するとよいでしょう。
インデックスが適切に行われているか確認
リニューアル後にインデックスされていないページがあると、検索結果に表示されず、流入が減少してしまいます。
特に「noindex」タグが誤って設定されている場合は要注意です。
確認方法としては、Google Search Consoleで「ページ」レポートに「noindexタグによって除外されました」と表示されるページがないか、サイトマップが正確に送信されているかを確認します。
また、「URL検査ツール」で個別のページがインデックスされているかを確認するのもよいでしょう。
対策としては、ページに「noindex」タグが誤って設定されている場合は削除し、インデックスを促進するため、Google Search Consoleの「インデックス登録をリクエスト」機能を使用します。
さらに、XMLサイトマップを最新状態に更新し、Search Consoleで再送信することが推奨されます。
ペナルティを受けていないか確認
Googleのガイドライン違反がある場合、検索順位が大幅に下がる可能性があります。
不正なSEO施策やリニューアル時の設定ミスが原因になることもあります。
確認方法としては、Google Search Consoleの「セキュリティと手動による対策」項目で、手動ペナルティ(例: スパムリンク、不自然なコンテンツ)が課されているか確認します。
また、Google Analyticsで特定の時期に急激な流入減少がないかを確認し、Ahrefsなどを利用して不自然な外部リンクが増加していないかチェックするのも有効です。
対策としては、手動ペナルティの場合、Search Consoleで原因を特定し、ガイドラインに基づいて修正を行い、再審査リクエストを送信します。
不正リンクの場合は、スパムリンクを確認し、Googleの「Disavow Links Tool」を使って否認することができます。
リダイレクトミスや漏れがないか確認
サイトリニューアル時にURLが変更された場合、旧ページから新ページへの適切なリダイレクトが設定されていないと、検索エンジンの評価が引き継がれず、アクセス減少の原因となります。
特にリダイレクト漏れや転送先URLの記述ミスに注意が必要です。
確認方法としては、Google Search Consoleの「カバレッジレポート」で404エラーが出ていないかを確認し、全ての旧URLに対応する新URLが存在するか、旧ページと関連性のないページへのリダイレクトが設定されていないかを確認します。
そして、旧ページのSEO評価を新ページに引き継ぐために、301リダイレクトを使用し、旧URLと新URLの対応表を作成して正確にリダイレクトを設定します。
設定後は、リダイレクトが正しく動作しているかをブラウザで確認するか、リダイレクトチェッカーを使用するとよいでしょう。
削除・変更したコンテンツにトラフィックが大きかったものがないか確認
リニューアル時に削除または大幅に変更したコンテンツが、実は多くのトラフィックを獲得していた場合、その影響でアクセスが減少することがあります。
確認方法としては、Google Analyticsでリニューアル前のトラフィックデータと比較し、流入が減少したページを特定。
削除したページがあれば、それがリニューアル前にどれほどのトラフィックを集めていたかを確認します。
合わせて、Google Search Consoleで削除または変更したコンテンツが、どの検索クエリからトラフィックを得ていたかを分析します。
対策としては、削除してしまったページを復活させるほかありません。
次善策として、トラフィックが多かったコンテンツの要素(キーワード、テーマ)を再確認し、関連する新しいページやセクションを追加するのもよいでしょう。
サイトリニューアルにおける9つのSEO注意点

サイトのリニューアルを行う際は、SEO面での失敗を避けることが肝要です。
本項目では、サイトリニューアルにおける9つのSEO注意点について、詳しく解説します。
コンテンツの不注意な削除や変更
サイトのリニューアル時は、コンテンツの不用意な削除や変更に気をつけましょう。
検索エンジンで高く評価されていたコンテンツを削除してしまうと、SEO対策に悪影響が出ます。
削除する前に、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleで、そのページがどれくらいのアクセスを集めていたかの確認は必須です。
どうしてもページを削除しなければならない場合は、関連性の高い別のページに301リダイレクトを設定しましょう。
内部リンク不注意な削除や変更
内部リンクは、サイト内のページ同士の関係性を示すだけでなく、検索エンジンのクローラーがスムーズにサイトを巡回するために大切な要素です。
内部リンクを不用意に削除したり、リンク切れを放置したりすると、SEO対策に悪影響が出ます。
対策としては、サイトの内部リンク構造を見直し、主要なページや関連ページへのリンクが維持されているかを確認することがあります。
リニューアル後は、リンクチェックツールなどを使い、すべてのリンクが正しく機能しているかチェックしましょう。
ドメイン(URL)変更時に301リダイレクトを設定していない
301リダイレクトを設定し忘れてしまうと、検索エンジンが新しいURLを認識できず、古いURLのSEO評価を引き継ぐことができなくなります。
その結果、サイトへのアクセスが大幅に減ってしまうかもしれません。
これを防ぐには、古いURLと新しいURLの対応表を作り、正確にリダイレクトを設定することがポイントです。
設定が完了したら、ブラウザやツールを使い、リダイレクトが適切に動作しているか確認を忘れないようにしましょう。
存在しないページ、削除したページに404を設定していない
サイトリニューアル時、存在しないページや削除したページに404エラーの設定を忘れないようにしましょう。
これを怠ると、ユーザーが不要なリダイレクトやトップページへの転送を経験することになり、SEOに悪影響を及ぼします。
もし削除したページに代わる新しいページがある場合、関連性の高いページに301リダイレクトを設定しましょう。
また、404ページは、ユーザーが困らないよう、分かりやすいエラーメッセージやトップページへのリンク、関連コンテンツへの案内などを用意することがおすすめです。
URLの正規化を行っていない
URLの正規化を行わないと、(例えば、「example.com」と「www.example.com」など)同じコンテンツが複数の異なるURLでアクセスできる状態が発生し、重複コンテンツとして検索エンジンに認識される可能性があります。
また、アクセスが分散してしまうなど、SEOにプラスはありません。
対策としては、HTMLの「link rel=”canonical”」タグを使って、正規のURLを指定することが挙げられます。
また、wwwありとなしのURLや、index.htmlの有無などを統一し、301リダイレクトで正規のURLに誘導することも必要です。
内部リンクやサイトマップでも一貫して正規URLを使用し、クロールの効率を高めることが大切です。
XMLサイトマップを設定・送信していない
XMLサイトマップは、ウェブサイトの構造を検索エンジンに伝える大事なファイルです。
これを設定・送信しないと、クローラーが効率的にサイトを巡回できず、インデックスされないページが発生する可能性があります。
XMLサイトマップの作成には、「sitemap.xml Editor」やWordpressであれば「XML Sitemaps」などのプラグインを使用すると便利です。
作成したXMLサイトマップは、Google Search Consoleに登録して、クローラーに最新のサイト構造を知らせます。
新しいページを追加したり構造を変更した際には、サイトマップを更新し、再送信することを忘れないようにしましょう。
robots.txt・noindexの外し忘れ
サイトのリニューアル作業中、一時的にクローラーの訪問を制御するためにrobots.txtやnoindexタグを設定することがあります。
これらの設定を外し忘れてしまうと、検索エンジンにウェブサイトやページがインデックスされず、検索結果に表示されなくなってしまいます。
これを防ぐには、公開時に必ずrobots.txtのDisallowを解除し、noindexタグがないことを確認しましょう。
WordPressを使っている場合は、管理画面の「検索エンジンの表示を許可する」設定が正しいかチェックする必要があります。
Google Search Consoleの「URL検査」ツールで、インデックス可能な状態になっているか確認すると盤石でしょう。
MFI対応をしていない
Googleは、スマートフォンでの閲覧体験を重視し、MFI(モバイルファーストインデックス)を導入しています。
よって、モバイル対応を怠ると、検索順位の下降など、SEOに悪影響を与える可能性があります。
対策としては、デバイスに応じてレイアウトが変わるレスポンシブデザインの採用があります。
また、すべてのページをモバイル端末でテストし、レイアウトの崩れやタッチ操作のしにくさがないか確認しましょう。
GoogleのPageSpeed Insightsでモバイルページのパフォーマンスを分析し、改善点を実行することも大切です。
中古ドメインを利用する場合、ペナルティの有無を確認する
中古ドメインを利用する場合は、ペナルティの有無を必ず確認するようにしましょう。
中古ドメインを使用すると、過去のSEO評価を引き継げるメリットがありますが、ペナルティを受けた経歴があるドメインでは、サイト全体に悪影響を与える可能性があります。
対策としては、過去の使用履歴が確認できる信頼性の高い業者から中古ドメインを購入することがあります。
また、ドメインをGoogle Search Consoleに登録し、手動によるペナルティが課されていないか確認するとよいでしょう。
サイトリニューアルを外注する際に確認すべき点
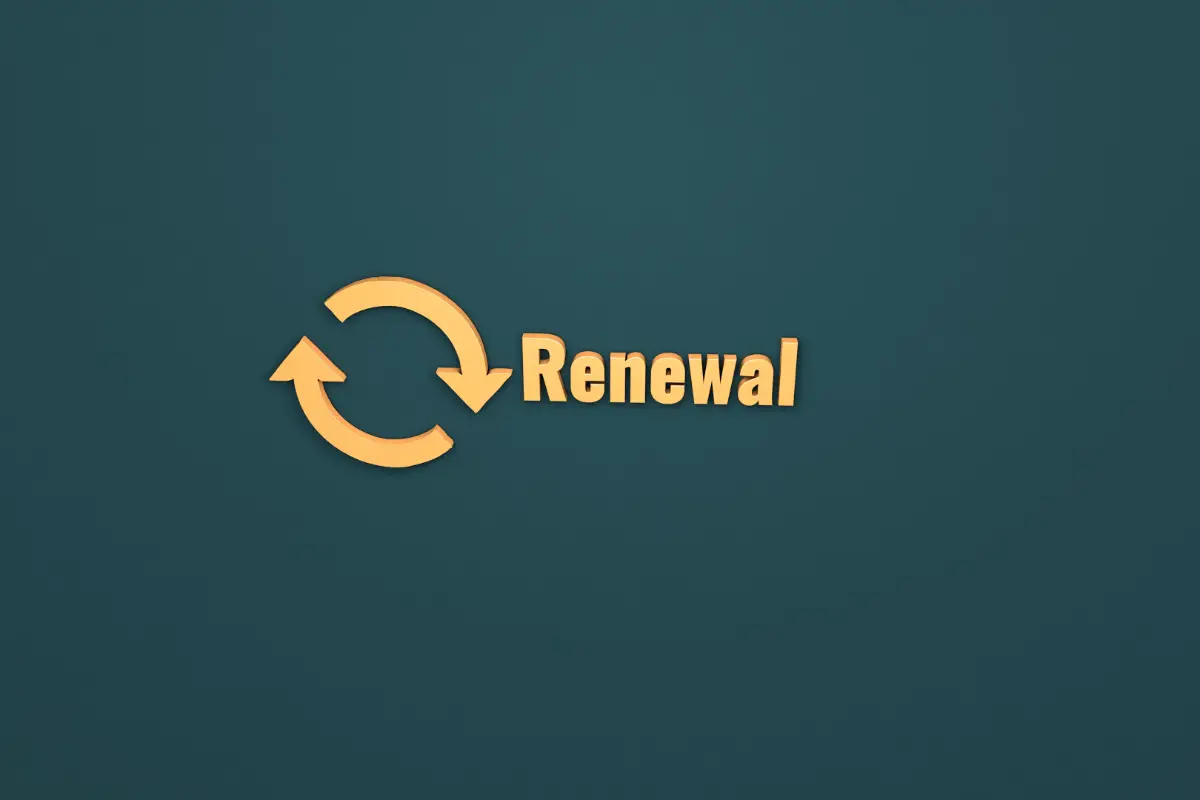
本項目では、サイトリニューアルを外注する際に確認すべき点について、ご説明します。
サイト構築やリニューアルの実績が豊富か
サイトリニューアルを外注する際は、依頼先のサイト構築やリニューアルの実績が豊富かどうかをしっかりと確認しましょう。
サイトリニューアルは複雑で幅広い作業が求められるので、経験不足の企業では進行が滞ったり、期待通りの成果が得られない恐れがあります。
依頼先がどんなリニューアルプロジェクトを手掛けてきたのか、特に自社と同じ業界や規模のプロジェクト経験があるかを確認することが大切です。
また、ポートフォリオを見て具体的なデザイン事例や実績をチェックし、プロジェクトの質や対応力を評価するのも良いでしょう。
成功事例や具体的な成果を公開している企業は信頼できる傾向にあります。
SEO対策の実績が豊富かどうか
SEO対策の実績が豊富かどうかも、サイトリニューアルを外注する際の重要なポイントです。
SEOに詳しくない企業に依頼すると、検索順位やアクセス数などが下がってしまうリスクがあります。
リニューアル後のサイト運用では、SEOは欠かせない要素です。
過去にSEO対策を含むサイト構築で成功した事例があるかどうかを確認しましょう。
また、自社の業界や業種の特性をよく理解しているか、専門用語やターゲット層に合った施策を提案できるかもチェックポイントです。
レスポンスは速いか
制作会社のレスポンスの速さも見逃せないポイントです。
レスポンスが遅いと、プロジェクト全体の進行が遅れ、納期に間に合わなくなる可能性があります。
コミュニケーションの遅れは、不要なトラブルを招くこともあるでしょう。
見積もり依頼時の返信の速さを確認し、迅速に対応してくれる企業を選ぶのがよいでしょう。
リニューアル後のサポートや保守契約も、スピーディーな対応が期待できるかどうかを確認しておくことをおすすめします。
親身になってくれるか
サイトリニューアルを依頼する際は、制作会社が親身になってくれるかどうかも重要なポイントです。
クライアントの要望や目標をしっかりと理解し、それに沿った提案ができる企業なら、リニューアル後の満足度も高まるはずです。
クライアントに寄り添う姿勢を持つ企業を選ぶことが、成功への近道と言えるでしょう。
初回の打ち合わせから親身に相談に乗ってくれるか、具体的な質問や意見を出してくれるかを確かめましょう。
自社のニーズに合ったカスタマイズや業界特有の課題解決策を提案できるかどうかも大切です。
リニューアル後の運用やメンテナンスまで考慮した提案をしてくれる企業なら、安心して任せられます。
費用や期間は明確か
サイトリニューアルの費用や期間が明確かどうかも、外注先を選ぶ上で重要な確認事項です。
リニューアルプロジェクトでは、費用や期間が大幅に変わることがあるため、透明性の高い企業を選ぶことが肝心です。
あいまいな契約内容だと、後になってトラブルに発展する恐れがあります。
費用の内訳や作業内容が詳しく書かれた見積書を出してくれる企業が望ましいでしょう。
プロジェクトの完了までにかかる期間についても、詳しい説明があるかどうかを確認します。
追加作業や変更が生じた場合の費用についても、事前に説明してくれるかどうかを見ておくとよいでしょう。
まとめ

医療機関のウェブサイトを一新することは、競争力強化と患者満足度向上に直結する重要な取り組みです。
しかし、リニューアルには複雑な作業が伴うため、適切なタイミングと手順に沿って進めることが成功の鍵を握ります。
まず、サイトのデザインが古くなったと感じたら、それはリニューアルのタイミングだと言えるでしょう。
競合他院との比較で見劣りしないよう、最新のトレンドを取り入れ、デザインや機能の強化が求められます。
また、幅広いブラウザやモバイル端末への対応も欠かせません。
サイト運用の効率化を図りたい場合や、新機能の導入を検討している際も、リニューアルに着手するべきタイミングです。
CMSの活用やコンテンツ更新フローの整備により、情報の鮮度を保ちつつ作業負担を軽減できます。
一方、リニューアル後のアクセス減少には十分な注意が必要です。
クロール拒否の設定ミスやインデックスの問題、コンテンツの不用意な削除などが原因となる可能性があるため、入念なチェックが欠かせません。
リニューアルを外注する際は、実績豊富で親身になってくれる制作会社を選ぶことが重要です。
費用や期間の透明性も見逃せないポイントと言えるでしょう。
医療機関のウェブサイトは、患者との重要な接点であり、最適化する恩恵は計り知れません。
弊社では、豊富な実績と専門知識を活かし、医療機関に特化したウェブサイト制作・リニューアルを総合的にサポートしています。
貴院のニーズに寄り添い、最適なソリューションをご提案いたします。
ウェブサイトやSEOでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。
















