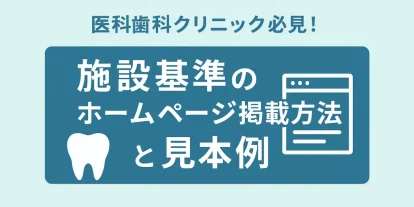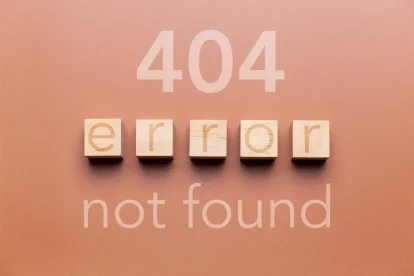医療(病院・クリニック)SEOが難しい理由、成功のポイントなど解説!

「医療(病院・クリニック)SEOって難しいの?」
「医療(病院・クリニック)の成功のポイントが知りたい」
他分野に比べ、医療(病院・クリニック)分野におけるSEOは難しいと言えます。
本記事では、医療(病院・クリニック)SEOとはなにか、医療(病院・クリニック)SEOが難しい理由、成功に導くためのポイントなどを解説します。
ぜひご一読いただき、貴院の医療SEOにお役立てください。
Contents
医療(病院・クリニック)SEOとは?

医療SEOとは、検索エンジンのアルゴリズムに適合するよう、ウェブサイトを最適化することで、検索結果の上位に表示されることを目指す取り組みです。
たとえば、「東京 内科」や「大阪 歯科」といった検索キーワードで上位に表示されれば、潜在的な患者にアピールできる確率が格段に上がります。
ここで気になるのが、医療SEOで特に重視される項目、また、具体的な医療SEO施策です。
以下に、詳しく解説していきます。
医療(病院・クリニック)SEOが難しい理由
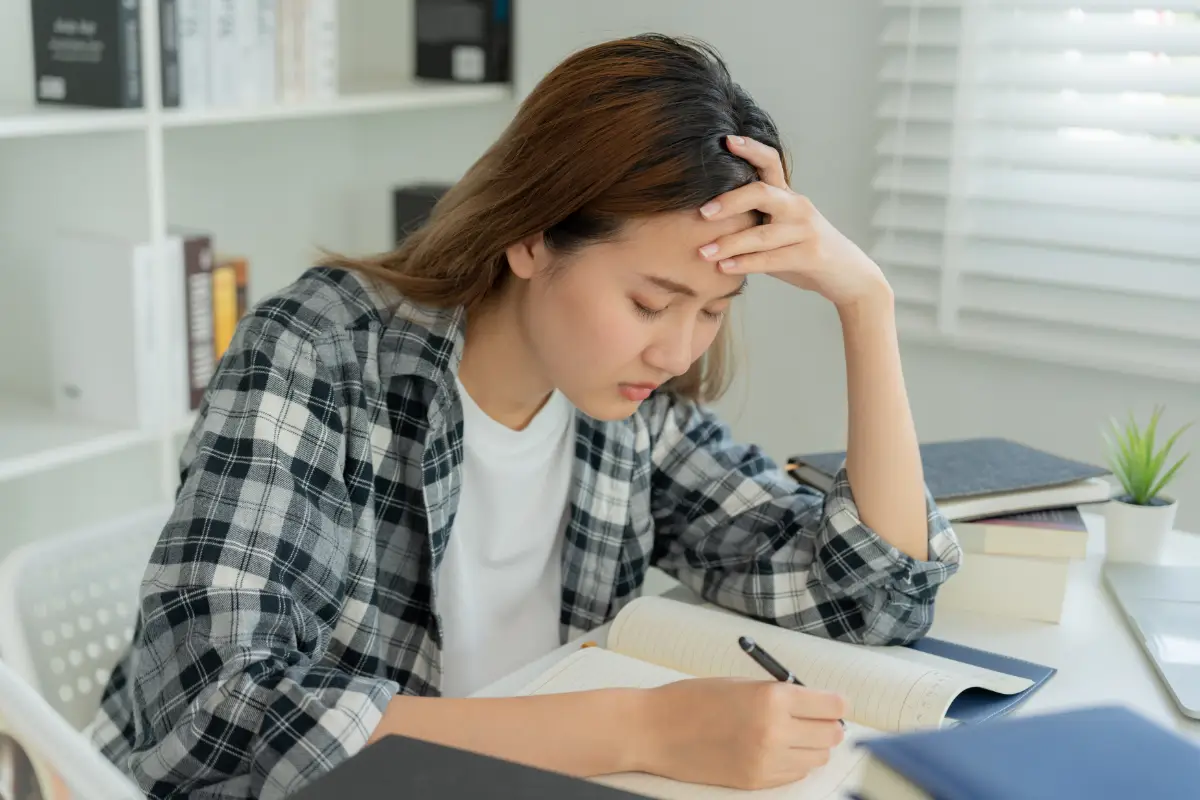
医療分野の検索エンジン最適化(SEO)は、他の分野に比べて難易度が高いと言えます。
本項目では、医療(病院・クリニック)SEOが難しい理由についてお伝えします。
Googleからの評価が厳しい、YMYL領域に該当する
まず、医療系サイトはGoogleからの評価が厳しいYMYL(Your Money or Your Life)領域に分類されることが挙げられます。
医療に関する情報は人々の健康や命に直結するため、誤った情報が広まるリスクを最小限に抑える必要があります。
例えば、美容皮膚科クリニックが適切でない治療法を推奨したり、精神科クリニックが根拠のないサプリメントの効果を謳ったりすると、患者の健康を損なう恐れがあるのです。
2016年に発覚した「Welq問題」を機に、Googleは医療や健康に関する検索結果の精度をさらに高める取り組みを強化しました。
その結果、専門家による正確な情報発信が重視されるようになったのです。
E-E-A-Tを満たす必要がある
また、医療系サイトではE-E-A-Tという指標を満たす必要があります。
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、具体的には、医療現場での実体験や専門的な知識を有する人物が情報を発信し、所属学会や経歴などを明示することで権威性と信頼性を担保することが求められます。
一方、患者のプライバシーにも十分配慮しなければなりません。
医療広告ガイドラインの理解・遵守が必要になる
さらに、医療広告ガイドラインの理解と遵守も欠かせません。
ガイドラインに違反すると、罰則が科される可能性があるためです。
2024年3月の改定で、注意すべき表現がさらに細分化されたことから、最新情報を確認しながらウェブサイトを制作することが重要となります。
具体的には、他院との比較優位性を根拠なく主張する比較優良広告や、極端な表現で効果を保証するような誇大広告は避けるべきでしょう。
公序良俗に反する内容や、患者の体験談、ビフォーアフター写真の不適切な取り扱いにも注意が必要です。
正確で事実に基づいた情報提供を心がけることが、ガイドライン遵守の大前提となります。
医療(病院・クリニック)SEOを成功に導くためのポイント

医療機関のウェブサイトを通じた集患は欠かせない取り組みです。
一方、医療分野の検索エンジン最適化(SEO)には独特の難しさがあります。
本項目では、医療(病院・クリニック)SEOを成功に導くためのポイントについて解説します。
クリニック・病院名で対策する
クリニックや病院の正式名称のみ、あるいは、クリニック・病院名と「評判」「口コミ」などのキーワードを組み合わせた指名検索で、自社サイトを上位表示させることが重要です。
既存患者の多くは施設名で検索してアクセスしようとするため、ここで公式サイトが上位に表示されないと、他の口コミサイトや競合クリニックのサイトに流出してしまう恐れがあるのです。
対策のポイントは、サイト内に正式名称や住所、診療時間等を明記し、Googleとユーザーにとって公式サイトだと分かりやすい構造にすること。
また、Googleビジネスプロフィールへの登録も欠かせません。
正確な情報を記載し、検索結果上のローカル枠に表示されるようにしましょう。
さらに、患者がスマートフォンやタブレットで検索するケースが多いため、SSL化とモバイルフレンドリー対応も必須です。
地域名×診療科目で対策する
「地名(駅名・市区名など)+診療科目」の組み合わせで上位表示を狙います。
これは診療を求めているユーザーが最も使用するだろうキーワードであり、近隣の患者の集患につながる可能性が高いキーワードです。
例えば、「渋谷 皮膚科」で検索する人は、自宅から通える、あるいは、仕事帰りに通えるクリニックを探している可能性が高く、「銀座 在宅医療」「銀座 訪問診療」で検索する人は近隣で在宅医療を提供してくれる施設を求めているでしょう。
対策としては、サイトタイトルや見出しにキーワードを盛り込み、診療科目の詳細ページを充実させること。
各科目の症状例、治療法、担当医師の専門分野を明記し、ユーザーが”誰が診察するのか”を把握できるようにします。
また、皮膚科専門医や在宅医療専門医などの経歴・資格を示すことで、専門性と信頼性(E-E-A-T)を高めることも大切です。
地域名×症状で対策する
例えば、「新宿 頭痛」で検索するユーザーは頭痛外来がある内科や脳神経外科を、「六本木 腹痛」で検索するユーザーは夜間や急な腹痛に対応可能な内科・消化器内科を探しているかもしれません。
そこで、症状に関するQ&Aコンテンツやコラムを用意し、専門医が監修した信頼できる解説を提供します。
また、診察の流れ・検査方法・対応科目を具体的に記載し、患者が自分の症状が合致するかイメージしやすくすることも効果的です。
さらに、症状ページを読んだユーザーがすぐに質問や予約をできる問い合わせフォームや予約フォームの整備も忘れてはいけません。
運営者を明示したうえで、安心して問い合わせられる体制を整えましょう。
誰による情報か明示する
医療SEO対策において、記事の執筆者や監修者を明確にすることは非常に重要です。
医療系サイトでは専門性の高い情報を扱うため、発信者のプロフィールが不透明だと、ユーザーやGoogleからの信頼を得にくくなります。
例えば、美容皮膚科に関する記事において、執筆者が医療の資格や経験を持つ医療従事者だと明記されていない場合、読者は情報の正確性を疑ってしまいます。
そこで、執筆者・監修者の氏名・経歴・所属学会を明示し、可能な範囲で資格・免許番号も記載します。
「●●大学医学部卒業、皮膚科専門医として10年の経験」「日本皮膚科学会認定専門医」といった情報を示すことで、専門性を担保しやすくなるでしょう。
また、執筆と監修の役割分担を明記するのも効果的です。
例えば、「執筆:医療ライターA(薬剤師資格保有)、監修:●●クリニック院長(●●専門医)」と表示すれば、記事制作に誰がどのように関わったのかが明確になります。
誰が運営しているサイトか明示する
医療情報を発信するうえで、サイトの運営主体が医療機関なのか、それとも第三者機関なのかによって、ユーザーの信頼度は大きく変わります。
クリニックや病院の公式サイトであれば、「●●クリニック公式サイト」といった形でトップページやフッターなどに運営者情報を分かりやすく提示します。
また、医療機関として実在する住所・連絡先・診療時間を掲載し、ユーザーが安心して来院できる環境を整えましょう。
一方、一般企業や第三者が運営するサイトの場合は、運営者の法人名・代表者名・企業所在地を明記する必要があります。
医療系メディアを運営するIT企業であれば、会社概要や所在地などをまとめたページへの導線を用意するといいでしょう。
また、運営が医療機関でなくても、医師や医療機関と連携して情報発信している場合は、その関係性を明らかにすることが大切です。
提携クリニック名や監修医師氏名などを記載し、サイト全体がどのように医療機関と連携しているのかを示します。
正しい情報かよく確認する
医療系サイトが扱う情報は、患者の健康や命に直結する場合も多いため、誤情報の拡散は重大なリスクを伴います。
例えば、古い治療ガイドラインを引用してしまったり、病名や症状説明を誤ったり、薬の用量・副作用情報を間違えたりすると、患者に深刻な被害を及ぼしかねません。
そこで、医師・薬剤師・看護師などの医療従事者が監修する仕組みを整え、執筆者が医療従事者でない場合でも必ず専門家による内容確認を行います。
また、内部の医師監修だけでなく、別のスタッフや医療知識のある編集者など、複数人によるダブルチェック体制を敷くことが望ましいでしょう。
さらに、記事の最終更新日を明記し、定期的に情報を見直すことも欠かせません。
年に数回は厚生労働省の公式情報や学会資料を確認してアップデートし、常に最新の知見を反映させる努力が必要です。
加えて、患者からの問い合わせ窓口を設け、誤情報の指摘にいち早く気づき修正できる体制を整備しましょう。
医療(病院・クリニック)SEOを外注するメリット

医療分野におけるSEO対策は、厳格なガイドライン遵守や高い専門性や正確性が求められるため、他ジャンルと比べて難易度が高くなりがちです。
まず、マーケティングやSEOのノウハウを独学で身につけるには相当な時間と労力が必要です。
また、医療広告ガイドラインやプライバシー保護の問題など、法律・規制をクリアすることは至難だと言えます。
内製が難しい場合、あるいは、よりスムーズかつ安全にウェブ集患を進めたい場合など、専門的な知識と経験を持つ外部のSEO業者への依頼も検討するとよいでしょう。
本項目では、医療(病院・クリニック)SEOを外注するメリットについてお伝えします。
SEOの専門知識や経験がなくても対策できる
医療SEOには、医療広告ガイドラインやYMYL(Your Money or Your Life)領域への対応など、通常のSEOに比べて守るべきルールが多く、専門知識が必要です。
しかし、クリニックの医師やスタッフがSEOを独学で習得するのは大きな負担となるため、プロに依頼することは一考に値するでしょう。
例えば、歯科クリニックが「インプラント治療ページを作りたい」と思っても、医療広告ガイドラインへの配慮や専門用語の解説など、注意点が多岐にわたります。
SEO専門会社に依頼すれば、誇大広告を避けながらも患者に伝わりやすい構成を提案してくれるため、院内での負担を最小限に抑えられます。
最新のアルゴリズムやトレンドをおさえた効果的な対策ができる
Googleをはじめとする検索エンジンは日々アルゴリズムをアップデートしており、特に医療系サイトはYMYL領域として厳しく評価されるため、最新の情報や技術に即した対策が欠かせません。
SEO専門会社は検索アルゴリズムの変化や新技術に敏感なため、タイムリーな施策を実行できます。
例えば、Googleが医療系キーワードの検索結果を大幅に見直すアップデートを行った場合、自院サイトを自力で最適化しようとしても、アップデート内容の把握や検証に手間がかかり、機会損失が発生しがちです。
一方、SEO専門会社であれば他の医療機関での事例やデータを持っているため、最適な改修策を早期に提案し、検索順位の下落リスクを抑えられるでしょう。
また、SGE(Search Generative Experience)などのAI技術導入により、新しい検索体験が広がる中、コンテンツの構成や見せ方など細かい対策ポイントが増えています。
外注すれば、専門家が「どこに力を入れると効果的か」を見極め、最新のトレンドを踏まえたコンテンツ制作をサポートしてくれます。
時間などリソース不足でも対応できる
医療SEOでは、記事やコラムの定期更新、キーワードリサーチ、競合調査、アクセス解析など多くのタスクが発生します。
これらを院内スタッフだけで回そうとすると、診療や患者対応に支障が出る恐れがあります。
外注を活用することで、SEOにかける時間やマンパワーを大幅に節約しながら、着実にサイトを育てることが可能です。
例えば、個人経営のクリニックにおいて、土日も診療、平日は少数のスタッフで運営しているケースでは、サイト更新やSNS発信まで手が回らず、情報が古いまま放置されがちです。
外注すれば、更新タイミングやコンテンツ企画をプロがリードしてくれ、院長は監修や最終チェックに集中できるでしょう。
法規制の知識がなくても対応できる
医療機関のウェブサイトは、医療広告ガイドラインのほか、Googleが定める品質基準(YMYL: Your Money or Your Life)にもしっかり対応する必要があります。
外注先のSEO専門会社は、医療広告ガイドラインや公序良俗に関する表現の制限など、医療系ならではの法規制への理解を持っている場合が多いのが特徴です。
これにより、誇大広告や虚偽表示といった違反リスクを最小限に抑えたコンテンツ運用が可能となります。
例えば、美容皮膚科のサイトで誤解を招くビフォーアフター写真を掲載しないよう、適切なキャプションや注釈を加えて違反リスクを回避したり、歯科クリニックのウェブページで「痛みが絶対にない」「100%成功」などの誇大表現を避け、事実ベースでの治療実績を示したりすることができます。
SEO業者は日々医療広告ガイドラインやGoogleアップデートの最新動向を把握しているため、コンプライアンス遵守と検索順位向上を両立した施策が期待できるのです。
診療など本業に集中できる
医療機関が自力でSEO対策に取り組む場合、コンテンツ制作・キーワード選定・サイト更新などに多大な時間と労力がかかります。
外注すれば、院内のスタッフや医師は診療や患者対応に専念しつつ、ウェブ集患を進めることが可能です。
例えば、総合病院の広報担当が外注先と定期的にミーティングを行うだけで、記事作成やSEO施策をスピーディーに進められます。
結果、広報担当は院内イベントや取材対応など、他業務にも力を注ぐことができます。
また、個人経営のクリニックにおいて、受付スタッフがウェブ担当を兼任している場合、患者対応や電話応対に追われ、定期更新が滞ってしまうかもしれません。
この場合、SEOを外注することで、SEO対策は進めつつ、スタッフは予約管理や患者フォローに集中できます。
まとめ

医療機関にとって、ウェブサイトを通じた集患は欠かせない取り組みです。
しかし、医療分野の検索エンジン最適化(SEO)には独特の難しさがあります。
医療系サイトはGoogleからの評価が厳しいYMYL領域に分類され、誤情報の拡散リスクを最小限に抑える必要があります。
また、E-E-A-Tという指標を満たすため、医療現場での実体験や専門知識を有する人物が情報を発信し、権威性と信頼性を担保することが求められます。
さらに、医療広告ガイドラインの理解と遵守も欠かせません。
医療SEOを成功に導くためには、クリニック・病院名、地域名×診療科目、地域名×症状などのキーワードで上位表示を狙うこと、情報の発信者や運営者を明示すること、正しい情報かどうかを入念にチェックすることが重要です。
加えて、予約や問い合わせフォームの設置、MEO対策、モバイルフレンドリー化など、ユーザビリティの向上にも注力する必要があります。
医療SEOには複雑な要素が絡み合っているため、院内の限られたリソースだけで対応するのは容易ではありません。
専門的な知識と豊富な経験を持つ外部のSEO業者に依頼することで、医療広告ガイドラインなどの法規制リスクを回避しつつ、最新のアルゴリズムやトレンドをおさえた効果的な対策を行えます。
また、コンテンツ制作やサイト更新などの作業を任せることで、医療機関は診療など本業に集中することが可能となるでしょう。
弊社では、医療機関に特化したウェブサイト制作、SEOをはじめとした集患サポート行っております。
豊富な実績と専門知識を活かし、貴院を全力でサポートいたします。
ウェブサイトや集患でお悩みの際は、ぜひ一度お問い合わせください。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。