SGEとは?SEOとの違いや影響、対策方法、使い方など解説!

「SGEとは?」
「SGEとSEOの違いを知りたい」
今後を考えると、SGEはおさえておきたい要素です。
本記事では、SGEとSEOとの違いや影響、SGE対策方法、SGEの導入方法(使い方)など解説します。
ぜひご一読いただき、貴院のSGE・SEO対策にお役立てください。
Contents
SGEとは

SGE(Search Generative Experience)は、Google検索結果の画面上部にAIが生成した回答を直接表示する機能です。
これまでの検索では、キーワードに合致するウェブページや広告のリストが表示されるだけでしたが、SGEでは検索結果の最上部にAIが自然言語で作成した回答が提示されます。
この機能は2023年5月の「GoogleI/O」で発表され、同年8月から日本での試験提供が開始されました。
2024年5月からは「AI Overview」という名称に変更され、さらなる機能拡充が進められています。
SGEの特徴として、長文や複雑な質問に対しても文脈を理解した回答を生成できること、検索結果画面内で追加質問ができる対話的な検索体験を提供することなどが挙げられます。
なぜSGEを導入したのか
Googleが検索にSGEを導入した背景には、AI技術の急速な発展と利用者の利便性向上という目的があります。
従来の検索エンジンは単にクエリに関連するウェブページを列挙するだけでした。
しかし、複雑な質問や日常的な疑問、適切な検索キーワードを思いつかないユーザーにとっては、求める情報にたどり着くことが困難な場合があったと言えます。
SGE導入の利点としては、まず検索に不慣れなユーザーでも質問を重ねながら回答を精緻化できること、そして長文や複雑な質問に対してもAIが要点をまとめた回答を提供するため、情報把握が迅速になることなどが挙げられます。
医療分野では、例えば新たな治療ガイドラインが公開された際、適切なキーワード組み合わせを考えなくても「特定の疾患における最新治療法」といった質問形式で入力すれば、SGEが複数の学術文献や医療サイトを参照した上で重要ポイントを要約して提示してくれるでしょう。
これにより、多忙な医療現場における効率的な情報収集が可能となります。
Bardとの違い
Bardは、Googleが提供するチャットボット型の生成AIで、独立したウェブサービスとして運用されています。
一方SGEは検索エンジンに統合された機能であり、ユーザーが検索を実行した際にAI回答が表示される点が大きく異なります。
両者の具体的な相違点として、提供形態があります。
Bardはチャットインターフェースを通じてユーザーが質問し回答を得る独立型サービスであるのに対し、SGEはGoogle検索に組み込まれ、検索結果上部にAI回答が表示される仕組みです。
SGEとSEOの違い
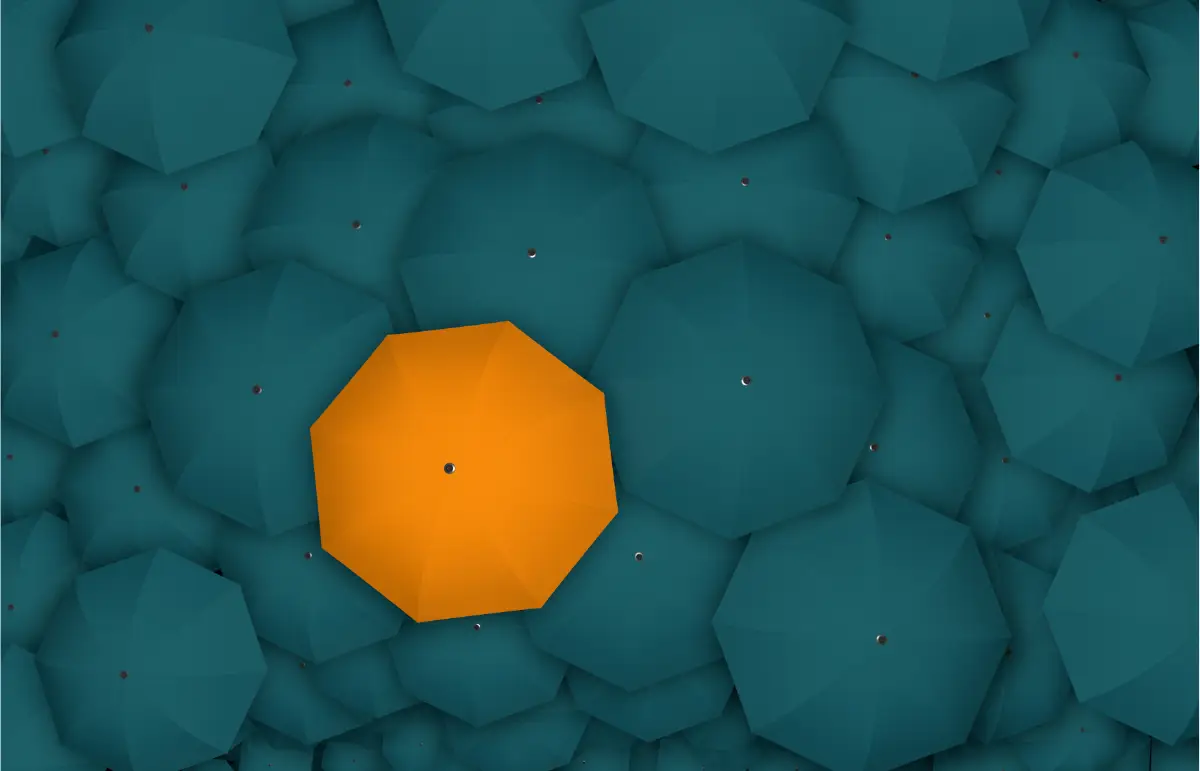
SGEとSEOには根本的な違いがあります。
SEO(Search Engine Optimization)はウェブサイトを検索エンジンに高く評価してもらい、検索結果の上位表示を目指す施策です。
ユーザーがクリックしてサイトへ訪問し、サービスや情報を利用してもらうことが目的となります。
一方、SGE(Search Generative Experience)は検索結果の最上部にAIが生成した回答を表示する機能です。
表示位置とアルゴリズムにも違いがあります。
SGEは検索結果の最上位にAIが生成した回答を表示するため、従来の自然検索結果より目立つ位置を占めます。
また、SEOによる上位表示のアルゴリズムと、SGEの回答として取り上げられるアルゴリズムは異なる基準で動作していると推測されます。
SGEの機能
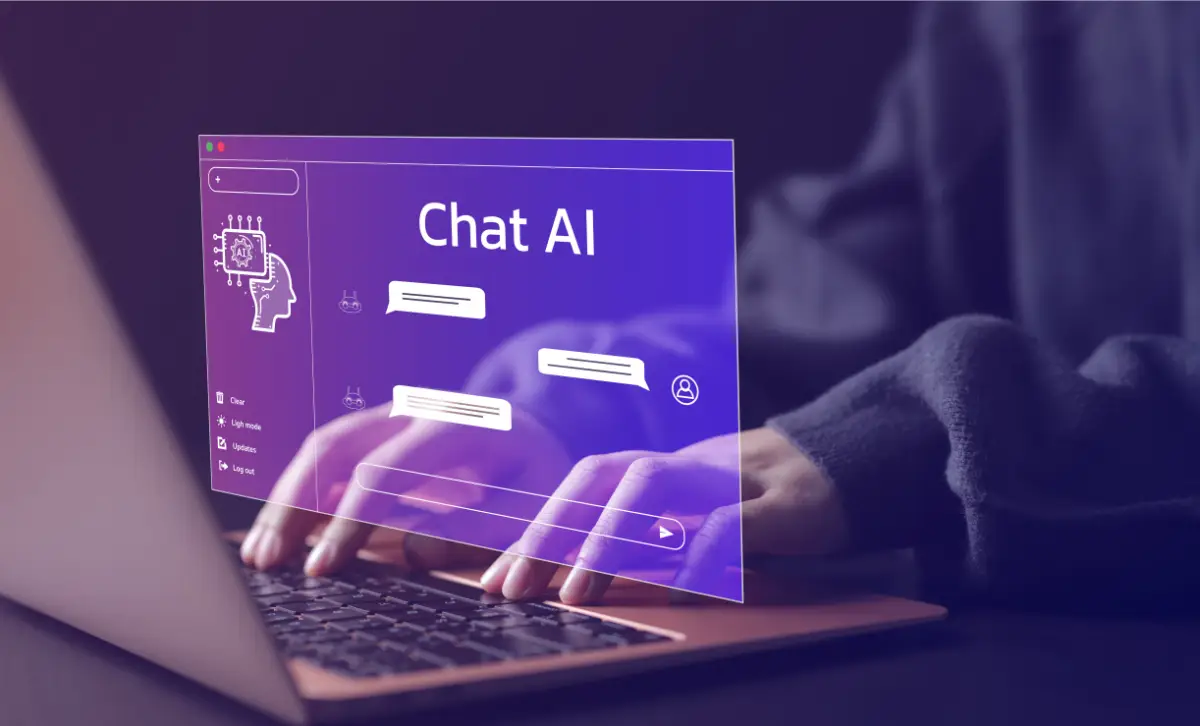
本項目では、SGEの機能を解説します。
生成AIによる回答が検索結果のトップに表示される
SGE(Search Generative Experience)の最も特徴的な機能は、検索キーワードに対するAI生成の回答が検索結果ページの最上部に表示されることです。
これは従来の「強調スニペット」や「関連質問」の機能を大きく発展させたもので、ユーザーが検索結果画面だけで主要な情報を得られるようになります。
医療分野での具体例としては、「特定疾患の初期症状」と検索した場合、要約(スナップショット)には主要な初期症状が列挙されるとともに、その症状を裏付ける医学的根拠や信頼性の高いソースへのリンクが提示されます。
一方、検索結果画面だけで必要な情報がほぼ得られてしまうため、SEOの観点では、従来のようにウェブサイトへアクセスせずに離脱する「ゼロクリックサーチ」が増加するリスクも存在します。
会話型AIによって詳細な情報を得られる
ユーザーの質問に対してAIが回答を生成するだけでなく、その回答を踏まえて追加の質問を重ねられる会話形式の検索をサポートしている点も、SGEの重要な機能として挙げられます。
文脈を引き継いだやり取りが可能なため、効率的な情報の収集に役立ちます。
回答の精度向上という面では、AIが提示した回答に対してユーザーが「特定の内容についてさらに詳しく知りたい」と追加質問することで、回答の精度や具体性が高まります。
また、回答(スナップショット)には回答の根拠となったウェブサイトへのリンクが併記される場合があり、より深い情報確認が必要な際はリンク先を参照できます。
一度の検索セッションで必要な情報を体系的に収集できる点が大きなメリットだといえるでしょう。
パーソナライズされた広告・販売促進
SGEは情報提供にとどまらず、ユーザーの興味関心や検索意図に応じて広告や販売促進につながる情報を併せて表示する機能の拡充も進めています。
また、個人の検索履歴に基づいてパーソナライズされた広告が表示されることで、例えば、特定の専門領域における研修機会や共同研究に必要な情報をより効率的に収集できる可能性があります。
その一方で、過剰な広告表示や誤った製品情報が医療従事者の判断を誤らせることのないよう、適切な対策を講じることも重要な課題となります。
SGEがSEOに与える影響

本項目では、SGEがSEOに与える影響についてご説明します。
ゼロクリックサーチが増える
SGE(Search Generative Experience)の導入により、検索結果画面だけで情報取得が完結してしまう「ゼロクリックサーチ」が増加する可能性が高まります。
これまでも「天気予報」や「営業時間の確認」のように検索画面上で疑問が解消される場面はありましたが、SGEの登場によってさらに幅広い質問に対応できるようになり、ユーザーがウェブサイトを訪問する必要性が減少するでしょう。
医療分野での具体例としては、看護師が「特定疾患の主な症状」を検索した際、SGEが提供する要約(スナップショット)ですでに症状や注意点が表示されると、医療情報サイトや病院のホームページに訪問する必要がなくなり、直接アクセスが減少する可能性があります。
結果、医療機関のウェブサイトが目指していた情報提供や広告効果が限定的になるおそれがあります。
Knowクエリからのアクセスが減少する
「Knowクエリ」とは、ユーザーが知識や情報を得たい場合の検索キーワードを指します。
SGEはこうした情報検索に対して迅速に要約を提示するため、ウェブサイトを訪問せずとも必要な情報が得られる状況がさらに増加すると考えられます。
医療分野での具体例として、シンプルな質問である「高血圧の定義は?」「特定ウイルスの潜伏期間は?」といった検索では、SGEが簡潔な回答を上部に表示するため、医療従事者が確認後すぐに検索行動を終了してしまうことがあります。
従来であれば医療機関のトップページや関連コラムへ誘導できていたものが、検索結果だけで完結してしまうケースが増えるため、アクセス数減少につながる可能性が高い点に注意が必要です。
生成AI最適化が求められるようになる
ゼロクリックサーチやKnowクエリからの流入減少を防ぎながら、今後も検索ユーザーの目に触れるためには、SGEに適した対策が不可欠となります。
従来のSEO施策(タイトル最適化、キーワード選定など)だけでなく、AIが認識しやすい情報構造や信頼性の高いコンテンツ作りが求められるようになるでしょう。
AI最適化の具体策については「SGE対策方法」の項目で後述していますが、ひとつユーザーが求める追加情報の網羅が効果的でしょう。
SGEは対話形式で追加質問を続けられるため、「症状が重くなった場合の対応」「副作用が出た際の対処法」といった深掘りされがちなトピックもあらかじめ回答に含め、AIにとって参照価値の高い記事を作成することが有効です。
結果としてSGEに引用されれば、検索からのクリックや参照元リンクとして表示されるチャンスが高まります。
SGEの導入方法(使い方)

本項目では、SGEの導入方法(使い方)をご説明します。
パソコンで使う場合の設定方法(Chromeブラウザ)
導入手順は以下の通りです。
1.Google Chromeを準備・起動
導入するにはまずGoogle Chromeを準備し起動します。
もしChromeがインストールされていない場合は、Google Chrome公式サイトからダウンロードしてください。
2.Googleアカウントでログイン
起動時はシークレットモードをオフにしておきましょう。
次に18歳以上の個人向けGoogleアカウントでログインします。
現状ではビジネス向けのGoogle Workspaceアカウントは利用できないため、必ず個人アカウントを使用してください。
3.「Search Labs」にアクセスし、SGEを有効化
ChromeブラウザでSearch Labsページを開き、Googleアカウントにログインした状態で「SGE:生成AIによる新しい検索体験」の項目にある「オンにする」ボタンをクリックするか、「OFF」を「ON」に切り替えます。
表示される「Google利用規約」と「生成AI追加利用規約」に同意すると設定完了です
4.検索画面にてSGEの動作を確認
最後に通常通りGoogleで検索を行い、SGEの動作を確認します。
検索内容によっては、結果画面の最上部にAIが生成した回答(スナップショット)が表示されます。
すべてのキーワードでSGEが表示されるわけではない点に留意しておきましょう。
導入後、新しい治療ガイドラインや医療機器の情報など検索すると、検索画面トップに要点をまとめたスナップショットが表示されます。
まずそこで概要を把握し、さらに詳細を知りたい場合にウェブサイトへアクセスするという流れで、情報収集の時間短縮が可能です。
スマホで使う場合の設定方法(Googleアプリ)
設定手順は以下の通りです。
1.Googleアプリのインストール・アップデート
まずはGoogleアプリをインストールするか最新版に更新します。
iPhoneならApp Store、AndroidならGoogle Play Storeで「Googleアプリ」を検索し、インストールまたはアップデートしてください。
2.Googleアカウントでログイン
次にアプリを開き、個人のGoogleアカウント(18歳以上)でログインします。
3.フラスコのアイコン「Search Labs」をタップ
続いてアプリ画面上または下部メニューにあるフラスコ形状の「Labs」アイコンをタップします。
このアイコンが表示されない場合は、まだ利用権限が付与されていない可能性があるので、条件(18歳以上、個人アカウントなど)を再確認しましょう。
4.SGEをオンにする
「SGE」を選択し「オンにする」をタップして、表示される利用規約に同意すると設定完了です。
5.検索の実行
設定後はGoogleアプリからキーワード検索を行うと、検索内容に応じてスナップショットが画面上部に表示されることがあります。
Google Workspaceで利用する方法
2025年3月現在、Google Workspace(ビジネスアカウント)ではSGEが利用できない状況です。
Search Labsの試験運用において、企業アカウントは対象外となっています。
将来的な展開については、Bardも当初はWorkspaceアカウントでの利用が制限されていましたが、後日解禁されました。
SGEについても今後段階的に企業アカウントでの利用が可能になる可能性が考えられます。
SGEの上手な活用例
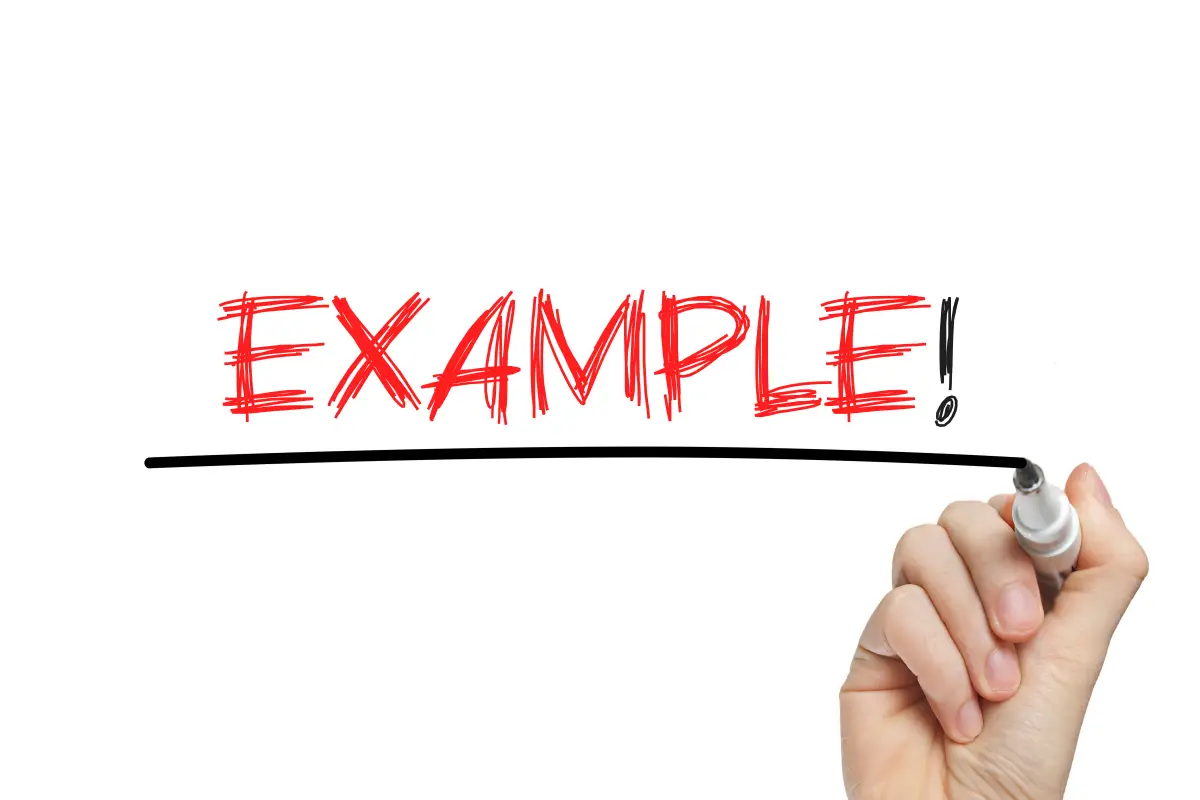
本項目では、SGEの上手な活用例をお伝えします。
効率的なネットショッピング
SGEは商品に関する情報を一括で取得できるため、価格・性能・口コミなどを比較検討する際に有用です。
複数のサイトを訪問する手間を省き、生成AIが必要な情報を要約して提示してくれるため、購入の意思決定までの時間を大幅に短縮できます。
医療分野での具体例として、手袋やマスクなどの消耗品を大量調達する場合、製品レビューや価格相場を一覧表示してくれるため、「早期納品可能な業者はどこか」「1箱あたりの単価の相場はいくらか」といった情報を簡単に把握できるようになります。
これにより調達業務の効率化が期待できます。
幅広い情報のインプット
SGEは、まだ情報があいまいな段階で「とりあえず様々な情報を知りたい」と考えている場面に適しています。
検索キーワードが少し漠然としていても、生成AIが関連するデータを広範囲にまとめてくれるため、効率よく基礎知識を把握することができます。
医療現場での活用例として、「呼吸器感染症 治療法 基本」といった検索を行うと、考えられる病原体や症状、一般的な治療の流れなどをスナップショットで要約して表示します。
その後に追加質問を続けることで、抗菌薬の選択肢や治療期間の目安など、より詳細な情報に段階的に深掘りしていくことが可能です。
SGE対策方法

本項目では、SGE対策方法をお伝えします。
SEOにもなる対策①:E-E-A-Tの強化
SEO同様、SGEにおいても、専門性や信頼性の高いサイトからの引用が優先されると考えられます。
よって、Google検索品質ガイドラインでも推奨されている、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化が、これまで以上に重要になると言えます。
具体的な取り組みとしては、まず経験(Experience)の明示が挙げられます。
実際に体験した事例やノウハウを共有することで信頼度が高まります。
医療現場での実践例や特定の医療機器の使用経験などを詳細に記載することが効果的です。
次に専門性(Expertise)の担保も重要です。
記事の担当者や執筆者がどのような資格や経歴を持っているかを明示することで、読者だけでなくAIからの評価も向上します。
医師や看護師などの専門資格や経験年数、専門領域を明記しましょう。
権威性(Authoritativeness)を高めるには、他サイトや外部メディアからの被リンクや引用を獲得し、信頼できる情報源として認知される体制を構築することが大切です。
医療系の学会や公的機関からの参照があると特に評価が高まります。
そして信頼性(Trust)を確保するために、運営者情報の開示やプライバシーポリシーの整備など、基本的な信頼性対策を徹底しましょう。
医療情報を扱うサイトでは特に、情報の出典や更新日の明記が重要になります。
SEOにもなる対策②:FAQコンテンツの作成
SGEでは複数のサイト情報をまとめた要約が提示され、さらにユーザーが追加質問をしながら詳細を深掘りできるのが特徴です。
このような仕組みに対応するために、「よくある質問(FAQ)」形式のコンテンツを充実させることで、生成AIに情報を引用してもらう可能性が高まるでしょう。
具体的な取り組みとして、まずはユーザーが抱えそうな疑問を徹底的に洗い出します。
ウェブサイト経由の問い合わせやSNSのコメント欄などを確認し、実際に患者がよく質問する内容をリストアップしましょう。
次いで、キーワード配置も重要です。
FAQの質問文や回答文に、ユーザーが検索で用いそうな医療用語や一般的な表現を自然に組み込みましょう。
ただし、不自然なキーワードの詰め込みは厳禁です。
SEOにもなる対策③:要約コンテンツの作成
SGEはユーザーに対して「最適なまとめ」を提示するシステムです。
コンテンツ作成の際は、要約や結論を分かりやすく提示しておくことで、AIが情報を抽出しやすくなり、引用される確率が向上すると考えられます。
具体的な取り組みとしては、まず記事冒頭に結論やポイントを簡潔にまとめることが効果的でしょう。
長い説明の後に結論を書くのではなく、まずは結論を明確にすることで、AIにもユーザーにも親切な構成となります。
次に見出しと段落をしっかり分けることも重要です。
例えば「概要」「具体的な治療手順」「注意すべき副作用」といったセクションに分け、読者・AIともに内容が把握しやすくなるでしょう。
このような「AIが要約しやすい構造」のコンテンツ作りは、従来のSEO対策にも有益であると同時に、SGE対策としても効果的です。
SEO以外の対策①:ウェブ広告
SGEの普及によって検索からの流入が減少するリスクに備えるためには、ウェブ広告を活用してサイトへの直接的な誘導を強化することが、ひとつ有効です。
代表的なウェブ広告としてディスプレイ広告、リスティング広告、SNS広告などがあります。
これらはユーザーの年齢や居住地などの属性、検索履歴や閲覧履歴に基づくターゲティングが可能なため、医療サービスや製品に関心のある層へ効率的にアプローチできる利点があります。
ウェブ広告で成果を上げるには、目的に応じて広告を選択する必要があります。
認知度向上ならディスプレイ広告、具体的な情報を求めているユーザーの獲得なら検索連動型広告が適しているといえます。
広告出稿前には「クリック率」「コンバージョン率」などの具体的な目標値を設定し、結果に基づいてクリエイティブやターゲティングなど継続的な改善が成功への鍵となります。
医療情報の広告には規制も多いため、コンプライアンスを守りながら効果的な訴求を行いましょう。
SEO以外の対策②:メルマガやLINEによる情報発信
メールマーケティングやLINE公式アカウントなどを活用して、自院や医療機関から直接ユーザーへ情報を届ける施策も検討するとよいでしょう。
メールマガジンやLINEでの情報発信により、医療機関から患者に対して、休診日のお知らせ、健康管理のアドバイス、医療セミナーの案内などを定期的に届けることができます。
検索ユーザーを待つのではなく、こちらから積極的にアプローチできる点が利点です。
配信間隔と内容には工夫が必要です。
頻繁すぎる配信はユーザーの負担になり、開封率低下や登録解除につながる恐れがあります。
情報を提供する際は、月1〜2回程度の適切な頻度で、季節の健康情報や最新の医療知識など、毎回価値ある内容を届けることが大切です。
またオンライン予約の優先枠など、登録者限定の特典を用意することも効果的です。
SEO以外の対策③:SNS
X(旧Twitter)やInstagram、LINEなどのソーシャルメディアで公式アカウントを運用することも有効です。
検索エンジンに依存しないトラフィック源を確保しつつ、患者との距離を縮めて双方向のコミュニケーションが実現できます。
フォロワーとのコミュニケーションがSNS活用の大きな利点です。
医療機関のアカウントと患者が直接やり取りできるため、サービスへの感想や施設環境への要望などが有用なフィードバックがリアルタイムで得られるでしょう。
こうした声は医療サービスの改善に活かせるだけでなく、やり取りからラポールを構築することでリピートの促進にもつながります。
SEO以外の対策④:YouTube
YouTubeでの情報発信を強化することも効果的な対策となります
動画の説明欄に医療機関のウェブサイトや専門外来ページへのリンクを設置することで、内容に関心を持った視聴者を直接誘導できます。
医療情報には、文字だけでは伝わりにくい内容もままあるため、動画による説明は大きな価値を持ちます。
コンテンツの充実も重要です。
医療機器の使用方法や治療の流れ、患者向け健康管理のアドバイスなど、医療従事者や患者が「知りたい」と感じる動画を定期的に公開し、チャンネル登録者を増やしていくことが大切です。
医療現場の実際の様子や医師による解説があると、視聴者の安心感や信頼感も高まります。
SEO以外の対策⑤:ホワイトペーパー
ホワイトペーパー(健康ガイド、セルフケアマニュアルなど)の作成・展開も有効な施策といえます。
日常生活で役立つ健康知識や疾患予防法などをまとめた資料を無料提供することで、多くの人に興味を持ってもらいやすくなるでしょう。
ホワイトペーパーの作成においては、テーマ設定が重要です。
他の医療機関があまり取り上げていない視点を盛り込むと、資料の魅力が高まります。
例えば、食事制限中でも楽しめる具体的なレシピや、高齢者や運動が苦手な人向けの簡単ストレッチ法など、自院ならではの専門知見をまとめると差別化につながります。
ダウンロードフォームを活用したリード獲得も効果的です。
氏名・メールアドレスなどの情報を入力したユーザーのデータを蓄積し、必要に応じてLINEやメールで継続的に健康情報を提供することで、医療機関とユーザーとの関係構築が進みます。
まとめ

SGE(Search Generative Experience)は、Google検索結果の最上部にAI生成回答を表示する機能です。
2023年5月に発表され、「AI Overview」として機能拡充中です。
複雑な質問にも文脈を理解した回答を生成し、追加質問ができる対話型検索が特徴です。
導入背景には検索体験向上があり、医療分野では新治療法など専門情報の効率的収集に貢献します。
SGEはGoogle検索に統合されており、独立型サービスのBardとは異なります。
懸念点として「ゼロクリックサーチ」の増加があり、特に単純な医療情報検索では医療機関サイトへのアクセスが減少する可能性があります。
対策としてE-E-A-T強化、FAQ作成、AIが引用しやすい要約コンテンツ制作が効果的です。
利用はChromeまたはGoogleアプリから「Search Labs」にアクセスし設定するだけですが、現状は個人アカウントのみ対応しています。
SEO以外の対策としてはウェブ広告、メルマガ、SNS、YouTubeなどの活用も重要です。
弊社では、医療機関に特化したウェブサイト制作、SGE時代に最適化された集患サポートも行っています。
AIに引用されやすいコンテンツ作成、SEO対策やリスティング広告など、総合的に集患・人材獲得をサポート。
ウェブサイトやSGE・SEOでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。















