検索クエリとは?キーワードとの違い、SEOに活かす方法など解説!
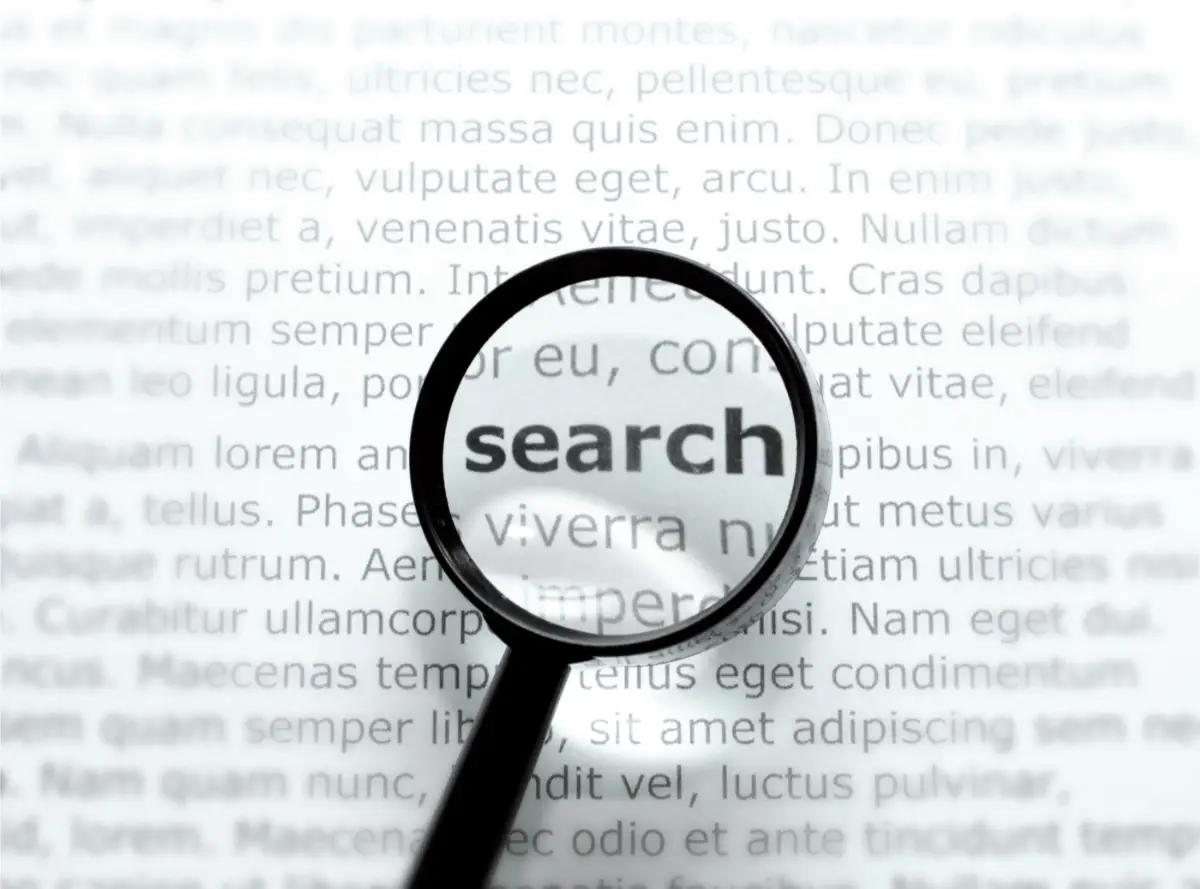
「検索クエリってなに?」
「検索クエリを効果的にSEOに活かす方法は?」
SEOは専門用語はたくさんあって大変ですよね。
本記事では、検索クエリとはなにか、検索クエリとキーワードの違い、検索クエリをSEOに効果的に活かす方法など解説します。
ぜひご一読いただき、貴院のSEOにお役立てください。
Contents
検索クエリとは
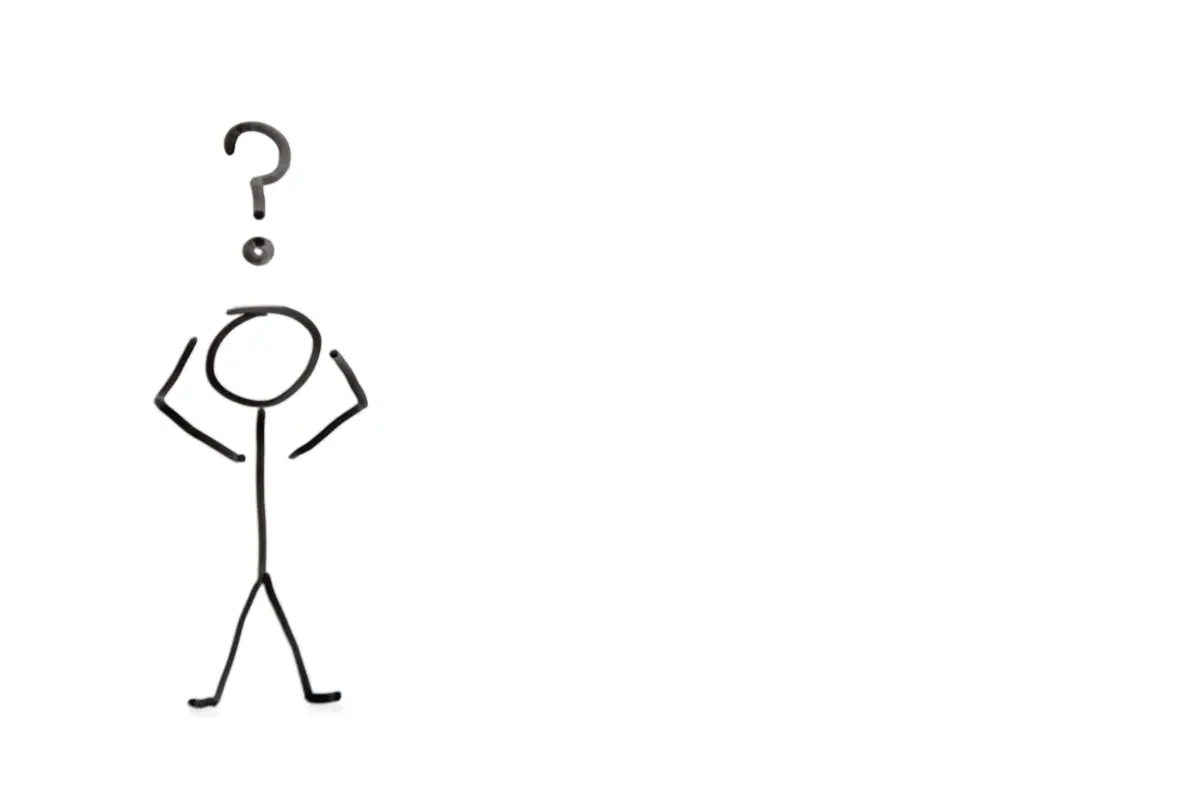
検索クエリとは、Googleなどの検索エンジンにユーザーが入力する言葉やフレーズを指します。
例えば「糖尿病によい献立」や「土日診療してる病院 東京 吐き気」などがその具体例にあたります。
これらの検索クエリは、まさにユーザーの知りたいこと、探したいこと、そして実際にとりたい行動を端的に表しているのです。
検索クエリの大きな特徴としては、第一にユーザーの抱えるニーズや課題がダイレクトに反映されている点が挙げられます。
例えば「糖尿病によい献立」という検索であれば、糖尿病患者本人やその家族が、制限のある中でもおいしく食べられる料理のレシピを知りたがっているのだと想像できます。
このように検索クエリには、ユーザーの生の声が凝縮されているのです。
そこに耳を澄まし、適切に応えていくことが、ウェブサイトには求められているのです。
検索クエリとキーワードの違い
検索クエリとキーワードはよく混同されますが、以下の点において違いがあります。
第一に、起点となる視点が異なります。
検索クエリはあくまでユーザーが検索窓に打ち込む生の言葉です。
対してキーワードは、ウェブサイトの制作・運営サイドが、どの単語・フレーズでコンテンツを最適化するかを意識して選定するものです。
第二に、抽象度にも違いがみられます。
実際の検索クエリは、言い回しやスペルのゆれ、あるいは誤字脱字や複数の単語の組み合わせなど、まさに十人十色だと言えます。
一方でキーワードは、そうした多様なクエリを一定程度集約し、コンテンツ制作の方向性を定めるための、いわば代表的な単語やフレーズとして扱われるのです。
例えば、「新宿でおすすめの歯医者さん」「しんじゅく歯医者人気」「新宿 敗者 おすすめ」などはクエリにあたり、「新宿 歯医者 おすすめ」はキーワードにあたります。
検索クエリの種類と検索意図(ユーザーインテント)

本項目では、検索クエリの種類と検索意図(ユーザーインテント)について解説します。
インフォメーショナルクエリ(情報型クエリ:Knowクエリ)
インフォメーショナルクエリとは、ユーザーが何かについて知りたい、学びたいという目的で入力する検索クエリのことを指します。
例えば、「〜とは?」「〜の原因」「〜の治し方」といった、疑問形や説明・解説を求めるクエリがこれに該当します。
こうしたクエリには、正しい服薬指導や具体的な養生法などを丁寧に説明することで、患者の不安解消につなげることができるでしょう。
また、専門医の監修記事や、看護師による実践的なアドバイスを提供できれば、検索者の満足度は高まるはずです。
ナビゲーショナルクエリ(案内型:Doクエリ)
ナビゲーショナルクエリとは、特定のウェブサイトやサービスを利用したり、何らかのアクションを起こしたりするために入力される検索キーワードです。
例えば、「●●病院 予約システムログインしたい」といったクエリからは、その病院の予約画面に直接アクセスしたいという明確な意図が読み取れます。
こうしたユーザーを目的を満たすためには、分かりやすくやり方を示すことが求められます。
ビジットインパーソンクエリ(エリア型:Goクエリ)
ビジットインパーソンクエリとは、実際の店舗や施設に足を運びたいと考えている人が使う検索キーワードです。
「近くの●●」「●●市 評判のいい耳鼻科」など、地域名や「近辺」といった表現を伴うことが多いのが特徴です。
こうした検索意図に応えるには、ウェブサイトはもちろん、Googleビジネスプロフィールや地域情報サイトなどに営業日時や診療科目をきちんと登録しておくことが肝要です。
トランザクショナルクエリ(取引型:Buyクエリ)
トランザクショナルクエリとは、ユーザーが何かしらの取引、つまり購買意図を持って検索する際に用いられるキーワードです。
例えば「~を購入」「申し込み」「資料請求」といった、具体的なアクションにつながるフレーズが含まれることが多いのが特徴です。
こうしたユーザーは、すでに受診先を絞り込んでいたり、比較検討している段階にあったりします。
予約フォームや料金プランを見やすく示すことで、スムーズな申込みにつなげられるでしょう。
トランザクショナルクエリは購買意欲が高い反面、競合他社との競争も激しい領域だと言えます。
いかに競合との差別化をはかれるか、また、「アクション」を促せるかが勝負どころになるでしょう。
検索クエリの調べ方

本項目では、検索クエリの調べ方をご説明します。
Googleサーチコンソールで検索クエリを調べる方法
GSCを導入するには、まずサイトの所有権確認が必要になります。
HTMLファイルのアップロードやDNS設定などの方法で、自分がそのサイトの管理者であることを証明します。
続いて、サイトやサブドメインごとに「プロパティ」を設定します。ここでも所有権の確認が求められるので、手順に沿って進めていきましょう。
検索クエリの確認方法ですが、GSCのメニューから「検索パフォーマンス」を選ぶと、詳細なレポートが表示されます。
ここでは「クエリ」「ページ」「国」「デバイス」などの切り口からデータを絞り込むことができ、特定の検索キーワードでの表示回数やクリック数、クリック率(CTR)、平均掲載順位などを知ることができます。
例えば、「●●市の内科 すぐ予約できる」というクエリで自院のサイトがどれだけの人の目に留まり、実際に訪問されているのかがわかります。
もし表示回数に対してクリック数が少なければ、ページタイトルやメタディスクリプションを魅力的なものに変更したり、予約ページへの導線を改善したりする余地がありそうです。
Googleアナリティクスで検索クエリを調べる方法
GAを使い始めるには、専用のトラッキングコードをサイト全体に設置する必要があります。
そしてGSCとGAを連携させることが、検索クエリ把握の大前提になります。
これによりGAのレポート上でも、GSCのデータを一部閲覧できるようになります。
具体的には「レポート」→「Search Console」→「クエリ」などの順で選択すると、各クエリのクリック数や表示回数、平均掲載順位といった指標を横並びで見ることができます。
Googleアナリティクスにおける、検索クエリの「(not provided)」とは
GAレポート上で「(not provided)」とは、情報提供ができない、キーワードを表示することができないということ意味し、GoogleをはじめとするSSL対応の検索エンジンが、ユーザーのプライバシー保護のために検索キーワードを暗号化して送信するようになったことが大きな理由として挙げられます。
かつてはGoogleアカウントにログインしていない状態やYahoo!検索からの流入では一部のキーワードが取得できましたが、今ではほとんどすべてのオーガニック検索が(not provided)となってしまうのが実情です。
しかしながら、検索クエリの分析をあきらめる必要はありません。
GoogleサーチコンソールとGAと連携することで、GA上でもある程度のクエリ情報を参照できるようになります。
Googleアナリティクスにおける、検索クエリの「(not set)」とは
Googleアナリティクス(GA)のレポートで「(not set)」と表示されるのは、主に以下のような場合です。
まず、GAがデータを適切に取得できなかったケース。
例えばリダイレクトによって参照元情報が正しく引き継がれなかったり、そもそも検索キーワードが存在しないSNSやブックマークからのアクセスなどが該当します。
また、リファラースパムの影響で、設定されていない言語情報や不正な参照元が紛れ込むと、キーワードの取得が困難になることもあります。
こうした「(not set)」への対処としては、まずはリファラースパムの除外が有効です。
「ユーザー→地域→言語」から(not set)のユーザーを抽出し、「セカンダリディメンション→参照元」で怪しいドメインを特定してフィルタリングします。
また、クッキーやJavaScriptの設定、データストリームの実装などが適切かどうかを再確認しておくことも大切でしょう。
Googleアナリティクスにおける、検索クエリの「(other)」とは
GAのレポートを見ていると、「(other)」という項目が目につくことがあるかもしれません。
これは文字通り「その他にまとめられたデータ」を表すラベルで、大量のクエリを一括処理した結果として表示されます。
実はGAにはひとつのディメンション(ページURLやキーワードなど)で扱える行数に上限があり、それを超えた分は自動的に「(other)」として集計されてしまいます。
無料版の場合、この制限は50,000行とされています。
つまり5万種類を超える検索クエリが流入すると、GA側が高基数(large cardinality)だと判定し、「(other)」にまとめ上げるわけです。
こうした事態を回避する手段としては、いくつか選択肢が考えられます。
ひとつは、GA4とBigQueryを連携させ、上限を超えた詳細データをSQL分析する方法。
もうひとつは、有償版のGoogle Analytics 360を導入し、拡張データを活用することで「(other)」の発生を抑える戦略です。
あるいは地道な対策として、ビューやレポートの設計時点から細分化を心掛けるのも有効でしょう。
無意味なパラメータやデータの重複を排除したり、診療科ごとにビューを分割するなど、一箇所に情報が集中しすぎないよう工夫するわけです。
いずれにせよ、GAの「(other)」表記は、サイト設計の複雑さとアクセス規模に起因するデータ集約の表れだと言えます。
レポートの制約にとらわれず、本当に必要な検索クエリを見極める視点が問われているのかもしれません。
検索クエリだけで検索意図がわからない時の対処法
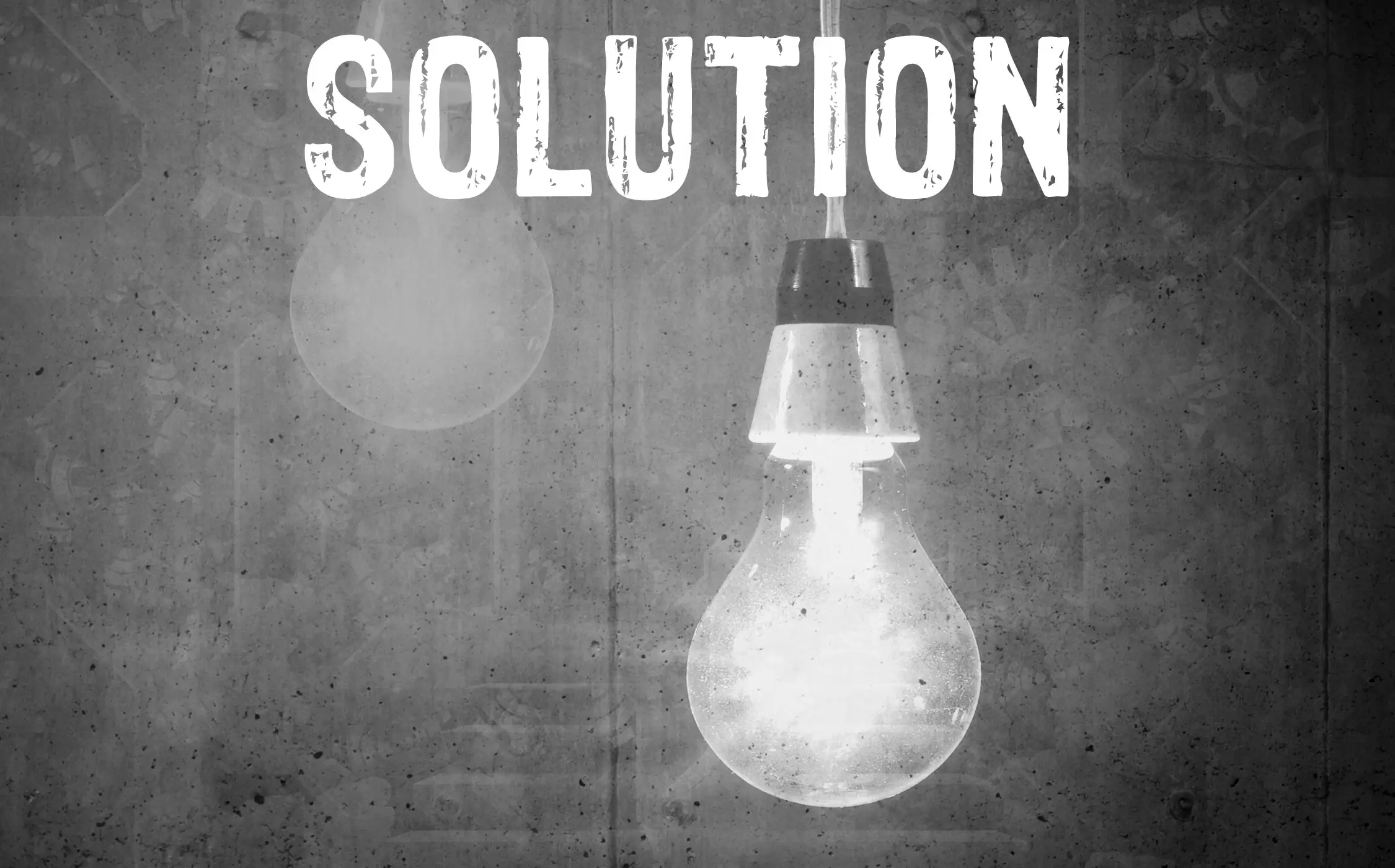
本項目では、検索クエリだけで検索意図がわからない時の対処法についてご説明します。
検索結果を確認する
検索クエリの文言だけでは、ユーザーが本当に求めている情報を推し量ることが難しいケースがあります。
そんな時は、実際にそのクエリで検索をかけてみて、上位に表示されるページを確認するのが有効です。
例えば「糖尿病の初期症状 なにがある」というクエリ。
文字通りには初期症状について知りたいのだろうと考えがちですが、検索結果を見渡すと「予防法」や「血糖値管理」など、関連トピックを扱ったページも多く見受けられるかもしれません。
つまり利用者は、自分が糖尿病かもしれないと不安に感じてチェックしたいというだけでなく、もしそうだった場合にどう対策すればいいのかという点も併せて知りたがっている可能性があるわけです。
また「インフルエンザ 予約 大阪」のように、ワクチン接種の予約なのか、発症後の診療予約なのか一見わかりにくいクエリもあります。
検索結果に目を通すと「インフルエンザワクチンの予約方法」「高熱時の夜間診療」「休日対応クリニック」など様々なタイプのコンテンツが現れるかもしれません。
そこから「発熱した患者が夜間でも受診できる病院を探している」「予防接種を希望する人が多い」といった具体的なニーズが浮かび上がってくるはずです。
こうした検索結果の観察から、タイトルや見出し、本文に至るまで念入りにチェックすることで、ユーザーの検索意図を探ることができます。
Yahoo!知恵袋などQAサイトを確認する
検索クエリ以上に生々しいユーザーの声を集めるなら、Yahoo!知恵袋や教えて!goo、あるいは専門的なQ&Aサイトなどが参考になります。
ここには検索キーワードでは表せないような具体的な状況や相談内容が書き込まれており、利用者の抱える悩みや背景を垣間見ることができるのです。
例えば、Yahoo!知恵袋で「手術後 痛み なかなか治まらない」などの投稿を見つけたとします。
そこには「痛みの程度はどのくらいなのか」「いつまで我慢が必要なのか」「病院に行くべきなのか」など、患者の生の不安が綴られているかもしれません。
こうした書き込みから、手術後のアフターケアやリハビリに関する詳しい情報、痛みの目安や受診の判断基準など、病院のウェブサイトで提供すべきコンテンツのヒントが得られるはずです。
利用者の具体的な状況や心情に注目しながら、コンテンツの補強ポイントを探っていくとよいでしょう。
ペルソナから考察する
しかし検索クエリだけでは、「誰が」「どんな状況で」「なぜ」そのキーワードで検索しているのかまでは掴みきれません。
そこで効果的なのが、ペルソナ(具体的な利用者モデル)を設定して、ユーザー像を明確にすることです。
ペルソナを作成する際は、年齢や家族構成、職業、ライフスタイルなどを具体的にイメージします。
そうすることで、表面的な検索キーワードの背後にある、利用者の真のニーズや検索意図が見えてくるのです。
例えば「子育て中の母親が、子どもの予防接種や病気について調べている」というペルソナを想定してみましょう。
30代前半で、保育園に通う子どもが2人。共働きでフルタイムの仕事をしているため、なかなか時間が取れない。
こんな状況だとすると、「予防接種 スケジュール 見やすい表」「子どもの発熱 病院 いつ行くべきか」といったクエリが多くなりそうです。
このように具体的な人物像を思い描いた上で、検索クエリに隠れているニーズや日常の状況をリストアップしていくのです。
そして病院のウェブサイトや医療情報ページにおいて、そのペルソナの抱える様々な疑問に応えられるよう、コンテンツ設計を工夫することが大切だと言えます。
検索クエリをSEOに効果的に活用する方法

本項目では、検索クエリをSEOに活用する方法について解説します。
共起語を抽出・活用する
共起語とは、あるキーワードと同じ文脈で頻繁に使われる単語やフレーズのことを指します。
検索エンジンは、共起語を含むコンテンツを「より関連性が高い」と判断する傾向にあります。
例えば「認知症」をメインキーワードとする場合、「アルツハイマー」「物忘れ」「介護サービス」「グループホーム」「記憶障害」などが共起語として考えられます。
これらを適切に文章中に織り込むことで、認知症に関する潜在的な疑問(症状の特徴や支援制度など)にも幅広く答えられる記事になるでしょう。
また「看護師 夜勤 健康管理」というキーワードなら、「睡眠不足」「シフト調整」「交代制勤務」「ストレスケア」「仮眠の取り方」といったフレーズが関連してきます。
夜勤で働く看護師の悩みを想定し、これらの共起語を含めて解説することで、より実用的なコンテンツに仕上げられるはずです。
共起語のチェックには、専用の検索ツールやキーワードサジェスト機能が役立ちます。
トレンドや季節を意識したキーワードを抽出・活用する
医療分野では、インフルエンザや花粉症など季節によって検索数が大きく変動する疾患があります。
また新型コロナウイルスのように突発的に流行する感染症や、最新の治療法に対する注目度の高まりなど、世間の関心事は刻々と移り変わっていきます。
例えば、春や秋の花粉症シーズン前には、「花粉症 つらすぎる 対処法」といったクエリが増加傾向を見せます。
年ごとの飛散状況や、新たな治療薬の登場などを盛り込んでコンテンツを更新すれば、ユーザーだけでなく検索エンジンからも高く評価されるはずです。
冬場なら「ノロウイルスの症状と対策」などの検索数にも注目です。
手洗いや消毒方法といった予防策や、家庭内での対処法、適切な受診タイミングなどを網羅した記事は、多くの人から信頼を集めることができるでしょう。
ロングテールSEOに活用する
ロングテールSEOとは、検索ボリュームこそ多くないものの、非常に明確な意図を持つ複合キーワードを狙うアプローチです。
例えば、「糖尿病 食事制限中でもいけるレシピ」というクエリ。
このクエリを活かし、「糖尿病 食事」や「糖尿病 レシピ おすすめ」などをテーマとしたコンテンツを作成すれば、さらに具体的なニーズを持つユーザー層を捉えられるでしょう。
また「看護師 夜勤で仮眠をとるコツ」のように、ある職種に特化した悩みを扱うのも有効です。
大手の看護系サイトではあまり掘り下げられていない話題を丁寧に解説することで、上位表示を目指せる可能性があります。
院内ブログや採用ページなどで、ベテランスタッフの体験談や実践的なアドバイスを発信するのは有効です。
ローカルSEOに活用する
ローカルSEOとは、地名や施設名を含む検索クエリで、自院やクリニックの情報を上位に表示させる手法を指します。
身近な事例を見てみましょう。
「●●で夜中にやってる病院 おなか痛い」「土日診療 ●●駅近くの小児科」といったクエリは、地域に密着した明確なニーズの表れです。
こうした検索をする人は、近くの医療機関を探しており、提供されている情報をもとに受診を決めるケースが多いはずです。
ですから自院の診療時間や休日対応の有無など、詳細な情報をウェブサイトやGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に正確に反映させておくことが肝要となります。
また地域名と診療科やサービス内容を掛け合わせたキーワードを意識した、ターゲットを絞り込んだページ作成も効果が期待できるでしょう。
検索クエリに基づくメタデータの最適化
まずは、検索エンジンにおけるメタデータの重要性についてです。
メタデータとは、ウェブページのタイトルタグ(title)やメタディスクリプション(description)、見出し(H1・H2など)に記載される情報を指します。
ユーザーが検索窓に入力したクエリに合致するメタデータを設定することで、検索結果画面でのクリック率やページの認知度を高められるでしょう。
具体的な事例を見てみましょう。
夜間救急に対応している病院のページを想定し、「夜間救急 ●●市」というクエリに最適化するとします。
タイトルタグは「【夜間救急】●●市で夜間対応可の●●病院 – 内科・小児科・整形外科」、メタディスクリプションは「●●市で夜間救急対応を行う●●病院です。内科・小児科・整形外科の夜間診療を行い、安心の医療体制をサポート。夜間対応の流れや緊急連絡先などを詳しく紹介します。」といった具合です。
実践のポイントとしては、Google Search Consoleで表示・クリック数の多いクエリを把握し、タイトルやディスクリプションに的確に反映させることが肝要です。
文字数制限の中で、ユーザーが「ここなら自分の疑問が解決できそう」と感じる情報をわかりやすくコンパクトに盛り込むことを心がけましょう。
コンテンツの最適化
ユーザーがどんな情報を求めているかを踏まえ、それに応えられる内容を作成・編集することが重要だと言えます。
例えばFAQ形式で患者の疑問に答えるコーナーを設けるとしましょう。
「高血圧 食事で注意するべきこと」「高血圧 運動 週何回」といったクエリに対応するQ&Aを用意し、「高血圧の方のための運動ガイドライン」「食事制限はどこまで必要?」など、読者が”自分も当てはまるかも”と感じる具体的な事例を盛り込むことで、満足度の高いページになります。
肝心なのは、ユーザーが具体的にどんな情報を求めているかをイメージすること。
その疑問を解消できる文章や画像、動画を適切に配置することです。
「疾患名だけ」「治療法だけ」ではなく、予防や検査、リハビリ、費用、保険適用など関連情報を多角的に網羅することで、ページの滞在時間を伸ばすことができるでしょう。
まとめ

検索クエリとは、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンに入力するキーワードやフレーズのことを指します。
それは、ユーザーの知りたいこと、探したいこと、実際に取りたい行動を端的に表しており、ニーズや課題が直接反映されています。
一方、キーワードは、ウェブサイトの運営側が、コンテンツを最適化するために意識的に選定する単語やフレーズを指します。
検索クエリには、インフォメーショナル(情報を得るため)、ナビゲーショナル(特定のサイトに行くため)、トランザクショナル(商品の購入などの取引のため)、ビジットインパーソン(実店舗に行くため)の4種類があります。
これらの検索意図を理解し、適切なコンテンツを提供することが重要です。
検索クエリは、Google Search ConsoleやGoogle アナリティクスを使って調べることができます。
ただし、キーワードの多くが「(not provided)」と表示され、詳細がわからないことがあります。
また、「(not set)」や「(other)」と表示されるケースもあり、データの解釈に注意が必要です。
検索クエリから検索意図を読み取るには、実際の検索結果を確認したり、Q&Aサイトの質問内容を参考にしたりすることが有効です。
また、ペルソナを設定し、ユーザーの属性や状況を具体的にイメージすることもいいでしょう。
検索クエリをSEOに活用する方法として、共起語の抽出、トレンドや季節性の把握、ロングテールキーワードの活用、ローカルSEOの強化などが挙げられます。
また、メタデータやコンテンツを最適化し、ユーザーの求める情報を適切に提供することが重要です。
弊社では、医療機関に特化してのウェブサイト作成、SEOをはじめとした集患対策サポートを行っています。
検索クエリ分析から、コンテンツ制作、サイト設計まで、専門スタッフが伴走し、集患力の向上をサポートします。
ウェブサイトや集患でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。











