SEO内部対策とは?対策必須の21項目チェックリストなど公開!

「SEO内部対策ってどんなもの?」
「効果的なSEO内部対策の方法が知りたい」
SEO内部対策は比較的対応しやすいものが多く、その内容を知るメリットは大きいと言えます。
本記事では、SEO内部対策とはなにか、具体的なSEO内部対策、やってはいけないSEO内部対策など解説します。
ぜひご一読いただき、日々のSEO対策にお役立てください。
Contents
SEO内部対策とは?

SEO内部対策とは、ウェブサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンのクローラーが効率的にサイトを巡回(クロール)し、正確に内容を理解(インデックス)できるようにする一連の施策です。
具体的には、HTMLコードの整備、適切なリンク階層の構築、コンテンツの論理的な配置などが含まれます。
この対策により、検索エンジンがサイトを正確に評価するだけでなく、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上にもつながり、直帰率の低減やコンバージョン率の向上も期待できます。
SEO内部対策の目的
SEO内部対策には複数の目的が挙げられます。
第一に、検索エンジンに正確な評価を受けるためのクローラビリティとインデクサビリティの向上があります。
適切なHTMLマークアップの実装、スキーママークアップの導入、論理的な内部リンク構造の構築により、クローラーがすべてのページを効率的に発見し、内容を理解しやすくなります。
一例にはなりますが、見出しタグを適切に設定して情報の階層性を明確にし、各種メタタグにキーワードを自然に配置することが重要です。
第二に、コアウェブバイタルに代表されるユーザーエクスペリエンス(UX)の向上が挙げられます。
内部構造が整理されたサイトでは、LCP(画面上に最大の要素が表示されるまでの時間)、FID(ユーザーの操作に対するレスポンスの速さ)、CLS(レイアウトのズレの有無)などの指標が改善され、ユーザーが必要とする情報へのアクセスがスムーズになります。
例えば、病院サイトにおいて診療科目や担当医情報への導線が明確に設計されていれば、ページ滞在時間が延び、直帰率が低減し、患者エンゲージメントが向上します。
第三に、SERP(検索結果ページ)におけるランキング向上のための基盤構築も目的といえるでしょう。
適切な内部対策により、クローラビリティとインデクサビリティ、および、ユーザービリティを最適化することにより、検索エンジンより評価を得やすくなります。
結果として、ランキング向上、ともなって、オーガニックトラフィックやコンバージョンの増加につながります。
SEO外部対策との違い
SEO内部対策と外部対策は、アプローチとコントロール範囲に明確な違いがあります。
内部対策はサイト内の要素に焦点を当て、自院でコントロールできる部分を最適化します。
より具体的にいえば、HTML構造の改善、XMLサイトマップの整備、内部リンク階層の最適化、URLの正規化などが施策として挙げられます。
これらにより、ユーザーおよび検索エンジンがサイトのテーマや内容を適切に理解できる環境を整え、SEO評価の向上をはかります。
一方、外部対策は他サイトからの被リンク獲得など通じて、サイト外からサイト評価を高める施策です。
医療分野では、専門性の高い医療機関や学術サイトからの高品質リンクを受けることで、大きな評価向上が期待できます。
しかし、これらの外部要因は自院だけでは完全にコントロールできないため、まずはコントロール可能な内部対策の実施をおすすめします。
SEO内部対策:クローラビリティ関連

本項目では、SEO内部対策:クローラビリティ関連についてご説明します。
わかりやすいURL(パーマリンク)を設定する
クローラビリティを高めるためには、URLを「短くシンプルに・内容が推測しやすい」形に整えることが推奨されます。
医療系サイトでの具体例としては、疾患別情報ページであれば、「https://example-hospital.com/disease/cancer/」のように、短くまとめながらも対象疾患名を含めることで、コンテンツの主題を明確に示すことができます。
ページ内容に合った英単語やカテゴリ名を使用することで、検索クローラーのインデクサビリティが向上し、同時にユーザーもページ内容を直感的に把握できるようになります。
パンくずリストを設置する
パンくずリストは、ウェブサイト内での現在位置を階層的に表示するナビゲーション要素です。
このリストにより、クローラーとユーザーの両方にサイト内の位置関係や階層構造を明確に伝え、クローラビリティ、ユーザービリティを同時に向上させることができます。
医療系サイトの具体例では、総合病院サイトのパンくずリスト構造として「トップページ > 診療科一覧 > 循環器内科 > 心不全の治療」といった形で実装すると効果的です。
これにより訪問者は現在のページが循環器内科カテゴリに属していることを瞬時に把握でき、必要に応じて上位階層へ容易に移動できます。
同時に検索エンジンにとっても、このページが心不全治療という専門性を持ち、循環器内科の情報階層に属していることが明確になります。
ページネーションを設置する
ページネーションは、大量のコンテンツを複数ページに分割し、順序立てて閲覧できるようにする仕組みです。
特に情報量の多いサイトでは、10〜20記事ずつ区切ってページ番号を設置することで、クローラーの巡回効率が向上し、ユーザーエクスペリエンスも改善されます。
医療系サイトの事例として例えば、症例紹介ページにおいて、多数の治療事例をすべて1ページに掲載するよりも、適切に分割することが挙げられます。
これにより、情報の整理性が高まり、クローラーの負担も軽減されます。
ページの表示速度向上にもつながり、モバイルフレンドリーの観点からも有利に働きます。
サイトの階層構造の最適化
クローラビリティを向上させるためには、サイトのディレクトリ構造を論理的に整理し、階層をなるべく浅く保つことが重要です。
階層構造を最適化することで、クリック数を最小限に抑え、患者やクローラーが求める情報に迅速にアクセスできるようになります。
例えば、診療科目ページの階層設計では、「トップページ > 診療科一覧 > 循環器内科 > 高血圧の治療」といったシンプルな階層構造が推奨されます。
また、医療コラムや症例紹介など、コンテンツ量が多いセクションでは、科目別・症状別などで適切にカテゴリ分けし、ドロップダウンメニューなどのナビゲーション要素を活用することで、深すぎる階層構造を避けつつ、情報を整理できるでしょう。
内部リンク設置のポイント(アンカーテキストでリンク先の内容を示す)
「リハビリテーション科」と「運動療法のコラム」のように、テーマ的に関連性の高いページ間にリンクを設けることで、関連コンテンツのまとまりを形成し、検索エンジンのコンテンツ理解を助けます。
リンク設置の際は、「こちら」や「詳しく見る」といった汎用的な表現ではなく、「高血圧治療のガイドラインを確認する」「整形外科手術の最新症例」など、リンク先の内容を端的に表現する適切なキーワードを含むアンカーテキストを使用しましょう。
これにより、クローラーにコンテンツの関連性を明確に伝えることができます。
トップページなど、サイト内で重要度の高いページからの内部リンクは特に価値があります。
これらのページからの戦略的なリンク配置により、新規コンテンツや重要ページへのクロール優先度とインデックス速度を高めることができます。
検索対象外のページ、低品質コンテンツはnoindex設定をする
検索結果に出す必要のないページや、情報量が乏しいページ、古くなった情報などをインデックスさせないようにするためには、noindexタグの設定が有効です。
低品質なページをそのままにしておくと、サイト全体の評価を下げる恐れがあるため、適切に管理することが重要です。
医療機関サイトにおいては、患者が予約確定後に表示される「予約完了ページ」のように、検索エンジンで表示しても意味がないページはnoindexで除外するのが適切です。
noindexの記述は、HTMLのheadタグ内に< meta name="robots" content="noindex"/ >と記述するだけで、検索エンジンに「このページはインデックスしなくてよい」という指示を出すことができます。
この設定により、クローラーは当該ページを発見しても検索インデックスには登録しないため、不要なページが検索結果に表示されることを防ぐことができます。
noindex設定をしたページへの内部リンクはnofollow設定をする
noindex設定をしたページがあっても、内部リンクが貼られているとクローラーがそのページを巡回しようとします。
そこで、クローラビリティを高めたい本来のページへのクロールを優先させるため、noindexページへのリンクにはnofollowを付与することが効果的です。
nofollowの記述例は、< a href="クロール不要のページURL" rel="nofollow" >アンカーテキスト< /a >のように記述します。
robots.txtによる不要なクロールの制限
検索エンジンのクローラーが巡回しなくてもよいページやディレクトリを指定するために、ウェブサーバーのルートディレクトリに配置するのが「robots.txt」です。
このファイルは検索エンジンのクローラーが最初に参照するもので、「sitemap.xml」と併せて設定すると、クローラーに対して「ここはインデックスしてほしい」「ここはクロール不要」と明確に伝えることができます。
医療系サイトでは、医院内部で利用するPDFや詳細な治療ガイドなど、一般公開が不要なディレクトリを「robots.txt」でクロール対象外に設定しておけば、誤って検索エンジンに拾われるのを防ぐことができます。
リンク切れをチェックする
サイト内でURLを変更したり、古いページを削除することで「リンク切れ(404エラー)」が発生することがあります。
リンク切れは利用者の使いやすさを損なうだけでなく、クローラビリティにも悪影響を及ぼし、検索エンジン評価の低下につながる可能性があります。
医療系サイトでは、例えば、学会やセミナー等の情報ページを削除した後、そのページへのリンクが院内の他ページに残っているとリンク切れになるため、定期的なチェックが必要です。
リンク切れのチェック方法として、「Broken Link Checker」などのWordpressプラグインなどを利用するなどが挙げられます。
また、Google Search Consoleの「カバレッジ」レポートでも404エラーの発生状況を一覧で把握できるため、発見したら速やかに修正やリダイレクト設定を行うことが望ましいでしょう。
サイトの更新頻度を上げる
検索エンジンのクローラーは、よく更新されるサイトには頻繁に巡回し、最新情報をインデックスしやすくなります。
医療系サイトの具体例としては、季節性疾患(インフルエンザ・花粉症等)の情報や、新しい治療ガイドラインなどを定期的に追加することで、「更新の多いサイト」と認識されやすくなります。
サイトの更新頻度を保つことは利用者の信頼獲得にも直結します。
最新の医療情報が整備されたサイトとして閲覧者に安心感を与え、結果として検索エンジンからも「価値の高い情報があるサイト」として認識されるようになります。
SEO内部対策:インデックス関連

本項目では、SEO内部対策:インデックス関連についてご説明します。
タイトルタグを最適化する
タイトルタグは検索エンジンがページ内容を理解する重要な要素であり、検索結果画面に表示されるためクリック率にも影響します。
医療系サイトでは「内科クリニック|高血圧・糖尿病など生活習慣病の治療なら●●医院」のように、重要キーワードを前方に配置し、続けて施設の特徴や強みを簡潔に示すことが効果的です。
タイトル作成のポイントとして、全角30文字前後を目安に内容を簡潔にまとめることがあります。
また、狙いたい検索キーワードを含め、「専門医による診療」「最新治療に対応」など患者にとって価値ある情報を盛り込むことで、より効果的にタイトルになるでしょう。
医療コラムであれば「【医師監修】花粉症の原因と対策|最新治療法を解説」のように、情報の信頼性と内容価値を前面に出すことで閲覧意欲を高められます。
メタディスクリプションを最適化する
メタディスクリプションは検索結果でタイトル下に表示される概要文で、ページ内容の概要と得られるメリットなどを端的に伝えます。
クリニック紹介ページであれば、「●●医院の内科では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病診療に力を入れています。経験豊富な専門医が一人ひとりの状態に合わせた治療を提供し、初診受付やオンライン予約も可能です」といった形で、診療内容と利便性を簡潔に示すとよいでしょう。
効果的なメタディスクリプション作成のポイントは、120文字程度の長さで、キーワードを自然に含め、重要情報を前半に配置します。
「専門医による丁寧な診療」「初めての方でも安心」など、利用者の不安や疑問に応える表現を含めることで、クリック率向上は見込めるでしょう。
スマートフォン表示での文字数制限も考慮し、伝えたい内容から示す構成が望ましいでしょう。
見出しタグを最適化する
見出しタグは文書構造を明確にし、ページ内容の階層と関係性を示す重要な要素です。
h1はタイトルや主題、h2は大見出し、h3は中見出しといったように、順序よく配置すると読みやすくなります。
見出しには狙いたいキーワードや関連語句を自然に織り込むことで、検索エンジンの内容理解を助けるとともに、利用者が求める情報に素早くたどり着ける道標としての役割も果たします。
医療系サイトでは、例えば、h1タグに「高血圧:糖尿病などの生活習慣病の改善方法【医師が監修】」のようにページタイトルや主題に割り当てるのが一般的です。
h2タグには「高血圧の原因と症状」「糖尿病の検査と診断基準」など、大見出しとなる項目を設定します。
さらにh3タグで「塩分制限による血圧管理」「血糖値コントロールの重要性」といった中見出し、あるいは小見出しとなる項目に分け、情報を整理するとよいでしょう。
画像にalt属性を記述する
alt属性の設定とはつまり、視覚的コンテンツをテキスト補完することを意味します。
良質なalt属性は画像が何を表しているかを具体的に示し、コンテンツ理解に役立つ情報を提供します。
例えば、医療系サイトでは、手術風景の画像に「心臓バイパス手術を行う医師と看護師のチーム医療の様子」といった具体的な説明を記述することで、検索エンジンは「心臓バイパス手術」に関する画像だと認識しやすくなります。
また、視覚障害のある利用者がスクリーンリーダーで情報を得る際にも重要です。
注意点として、不自然なキーワード詰め込みは避け、実際の画像内容に即した自然な文章にすることが挙げられます。
構造化データをマークアップする
構造化データは、ウェブページの内容や属性を検索エンジンに明確に伝えるための標準化されたコードであり、適切な実装は検索結果の視認性を高め、クリック前に必要情報を提供することで、質の高いアクセスを増やす効果が期待できます。
医療機関サイトでいえば、Schema.orgの「MedicalOrganization」や「Hospital」スキーマを用いて、施設名、住所、電話番号、診療時間などを定義することで、検索結果から直接予約電話番号や診療時間が確認できるようになり、利用者の利便性が向上するでしょう。
実装にはJSON-LD形式が推奨され、ヘッダー内にJSONコードとして記述します。
医療機関情報や診療内容など正確なデータを漏れなく記載し、Googleのリッチリザルトテストで表示確認を行うとよいでしょう。
W3Cのガイドラインに即しコーディングを最適化する
HTMLやCSSの文法エラーや不適切なタグの使い方は、検索エンジンに誤った構造を伝えたり、利用者の閲覧環境を損ねたりする恐れがあります。
W3C(World Wide Web Consortium)のガイドラインに沿った正しいコーディングを行うことで、サイトのアクセシビリティ向上や検索エンジンへの正確な情報伝達につながります。
コーディング最適化のポイントとしては、W3C Validatorの活用が挙げられます。
W3Cの公式バリデータでエラーをチェックし、修正することで、コードの品質を向上させることができます。
また、セマンティックHTMLの利用も重要です。
< header >、< main >、< footer >など意味を持つタグを用いて、ページの構造を明確化することで、検索エンジンの理解を助けます。
医療系サイトでは、例えば、各ページにおいて、見出しタグ(< h1 >、< h2 >)や段落(< p >)を正しく配置し、定義リスト(< dl >、< dt >、< dd >)や表(< table >)を適切に使うことで、情報が構造的に整理され、クローラーと利用者の双方にわかりやすくなります。
URL正規化や重複コンテンツをなくす
「http://example.com」と「https://example.com」など、同じコンテンツが複数のURLで表示されると、検索エンジンは「重複コンテンツ」とみなし、どのページを評価するべきか判断しづらくなります。
これを避けるために「正規化(canonical設定や301リダイレクトなど)」を行い、検索エンジンに「正しいURLはこれです」と伝える必要があります。
正規化・重複コンテンツ対策のポイントとしては、canonicalタグの使用があります。
< link rel="canonical" href="正規URL >をhead内に記述することで、検索エンジンに優先すべきURLを明示できます。
また、301リダイレクトで統合することも効果的です。
古いURLへアクセスした利用者を自動で正規URLへ飛ばし、SEO評価を集約することができます。
XMLサイトマップを設置・送信する
「XMLサイトマップは、サイト内のURL一覧を検索エンジンに伝える「地図」のようなファイルで、クローラーが効率よくページを発見しインデックスするのに役立ちます。
医療分野では、特に複数の診療科を持つ総合病院のような大規模サイトや、医療情報コラムや研究成果を多数掲載しているサイトでの活用が効果的です。
ページ数が多い場合や、新規コラムの公開、学会発表・論文情報の更新が頻繁な場合、サイトマップがあることでクローラーが重要ページを見逃さず、新情報を素早く検索結果に反映できるようになります。
設置・送信は以下の手順で行います。
まず、WordPressなどのCMSプラグインや無料ツールを使ってサイトマップファイル(sitemap.xml)を生成します。
次に、Google Search Consoleの「サイトマップ」画面からこのファイルを登録します。
コンテンツの更新があった場合は、サイトマップも更新して再送信することで、最新情報のインデックスを促進できます。
SEO内部対策:ページエクスペリエンス関連

本項目では、SEO内部対策:ページエクスペリエンス関連についてご説明します。
コアウェブバイタルを改善する
コアウェブバイタル(Core Web Vitals)は、ページの読み込み速度やインタラクション、視覚的安定性などを指標化したもので、Googleが検索結果の評価に用いる重要な指標です。
医療系サイトでは例えば、オンライン予約システムの使いやすさが重要です。
予約フォームの読み込みや操作が遅いと、患者はストレスを感じて離脱しやすくなります。
画像やスクリプトを圧縮したり、キャッシュ機能を活用することでフォームページのLCP(画面上に最大の要素が表示されるまでの時間)やINP(ユーザーの操作に対するレスポンスの速さ)を改善し、スムーズに予約できるようにしましょう。
改善を進めるには、まずPageSpeed Insightsで計測し、各指標の数値を確認して提案される改善点を参考に対策します。
画像やCSS/JSの最適化として、画像圧縮や不要なスクリプト削除などが挙げられます。
モバイルフレンドリーにする
スマホやタブレットからのアクセスが増えるなか、Googleは「モバイルファーストインデックス(MFI)」を導入しており、モバイル最適化の有無がサイト評価に大きく影響します。
改善のポイントとしては、まずレスポンシブウェブデザインを採用することが挙げられます。
これは1つのHTMLをデバイス幅に応じてレイアウトを切り替えられるので、管理が楽なうえGoogleも推奨している方法です。
実装後はGoogle Search Consoleやモバイルフレンドリーテストツールでエラーがないか確認しましょう。
また、文字やボタンの大きさにも配慮しましょう。
医療系サイトでは高齢者が利用するケースも多いため、文字を大きめにし、タップ領域を確保することが大切です。
ウェブサイトをSSL化(HTTPS化)する
インターネット上でのセキュリティ強化として、サイト全体をHTTPS化することが求められています。
医療系サイトでは、予約システムや問い合わせフォームでの患者情報(氏名、電話番号、症状など)の送信が発生します。
HTTPS化していないとこれらの通信が傍受されるリスクが高まるため、患者のプライバシーを守るためにもSSL化が求められます。
また、自費診療や健康食品を販売しているクリニックサイト等でオンライン決済を導入している場合は、クレジットカード情報保護のためにも必ずSSL化が必要となります。
やってはいけないSEO内部対策
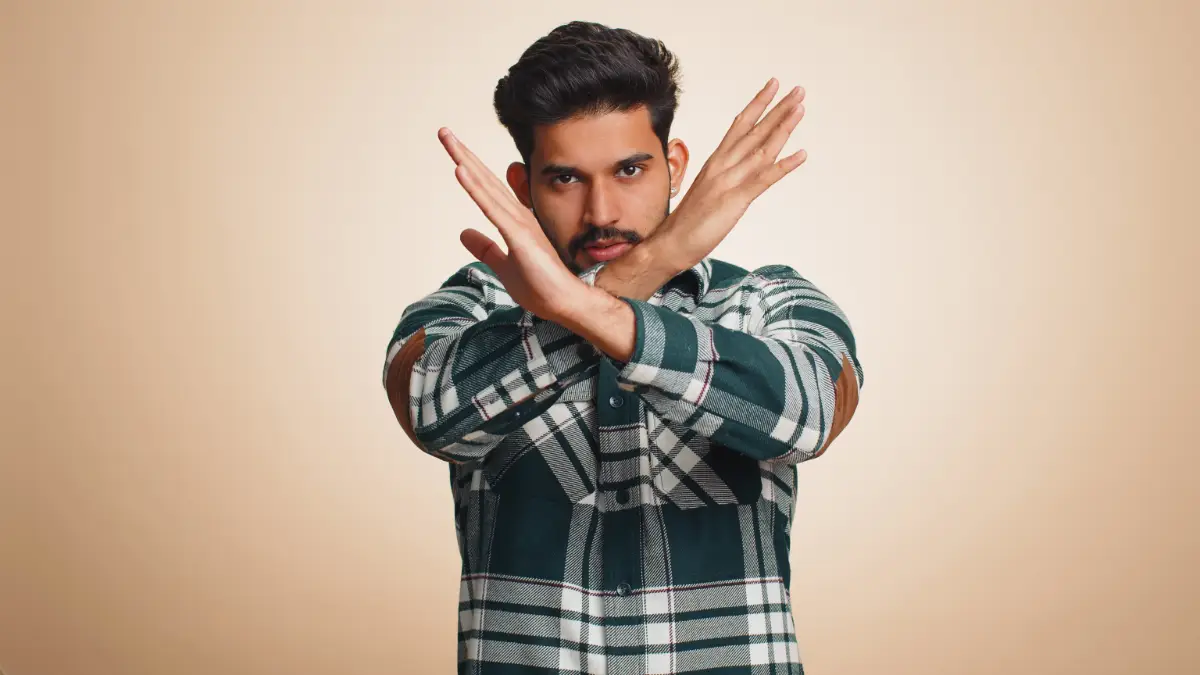
本項目では、やってはいけないSEO内部対策を解説します。
隠しテキスト・隠しリンク
隠しテキスト・隠しリンクとは、ユーザーに見えない形でテキストやリンクを設置し、検索エンジンだけに認識させる不正行為です。
例えば、白背景に白文字でキーワードを詰め込んだり、CSSでテキストを画面外に飛ばしたりといった手段が代表的です。
隠しテキスト・隠しリンクはGoogleのガイドラインに抵触し、検索順位の低下やペナルティが科されるリスクがあります。
クローキング
クローキングとは、検索エンジン(クローラー)と実際のユーザーに対して別々のコンテンツを表示させる行為です。
たとえば、クローラーにはテキスト中心のページを見せ、ユーザーには画像やFlashが多いページを表示するなど、それぞれに異なる情報を表示することが該当します。
クローリングは、明確なGoogleのガイドライン違反であり、隠しテキストなどと同様に、検索順位の大幅低下やドメイン全体のペナルティにつながります。
このような不正行為は、患者や医療従事者にとっても正しい医療情報へアクセスする妨げとなるため、絶対に行わないよう注意が必要です。
厳選!SEO内部対策チェックリスト21項目
| SEO内部対策:クローラビリティ関連 | |
| 1 | わかりやすいURL(パーマリンク)を設定する |
| 2 | パンくずリストを設置する |
| 3 | ページネーションを設置する |
| 4 | サイトの階層構造の最適化 |
| 5 | 内部リンク設置のポイント(アンカーテキストでリンク先の内容を示す) |
| 6 | 検索対象外のページ、低品質コンテンツはnoindex設定をする |
| 7 | noindex設定をしたページへの内部リンクはnofollow設定をする |
| 8 | robots.txtによる不要なクロールの制限 |
| 9 | リンク切れをチェックする |
| 10 | サイトの更新頻度を上げる |
| SEO内部対策:インデックス関連 | |
| 11 | タイトルタグを最適化する |
| 12 | メタディスクリプションを最適化する |
| 13 | 見出しタグを最適化する |
| 14 | 画像にalt属性を記述する |
| 15 | 構造化データをマークアップする |
| 16 | W3Cのガイドラインに即しコーディングを最適化する |
| 17 | URL正規化や重複コンテンツをなくす |
| 18 | XMLサイトマップを設置・送信する |
| SEO内部対策:ページエクスペリエンス関連 | |
| 19 | コアウェブバイタルを改善する |
| 20 | モバイルフレンドリーにする |
| 21 | ウェブサイトをSSL化(HTTPS化)する |
まとめ
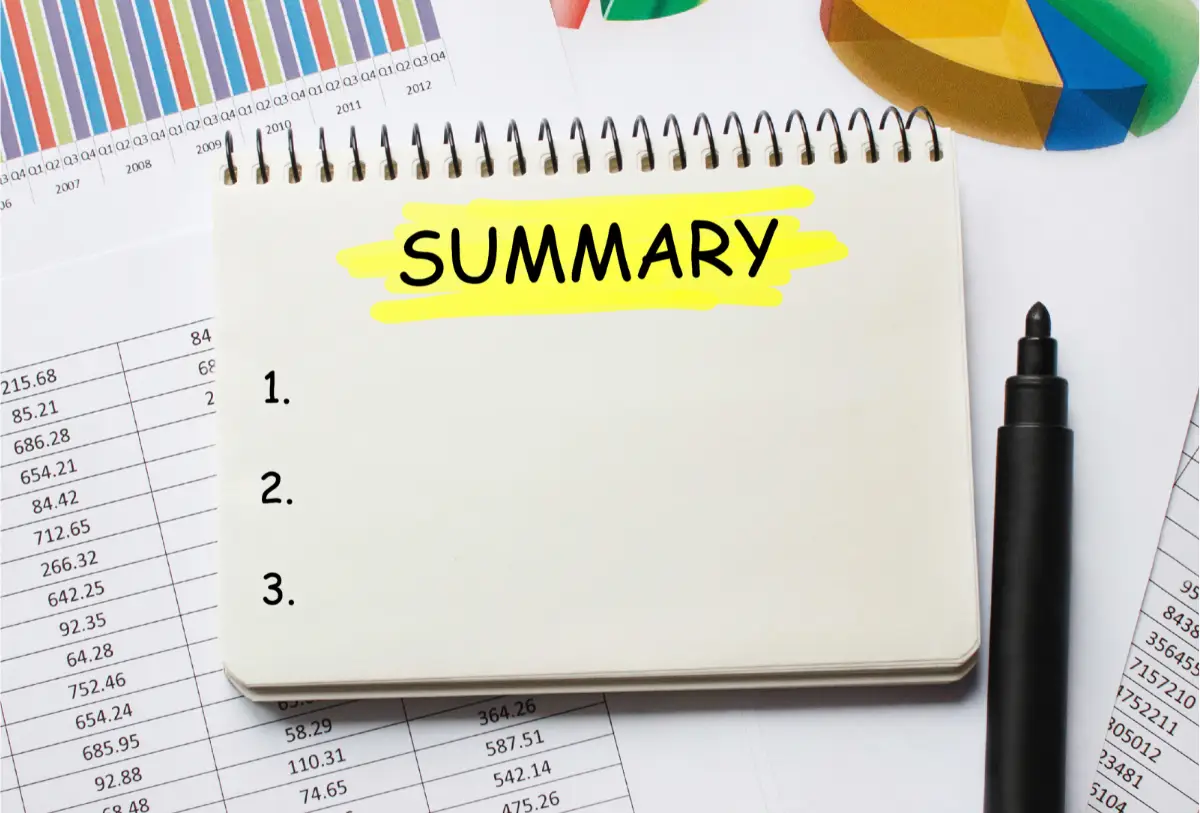
SEO内部対策とは、ウェブサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンのクローラーがサイトを効率的に巡回・理解できるようにする施策です。
HTMLコードの整備、適切なリンク階層、コンテンツの論理的配置などにより、検索評価の向上とユーザー体験の改善を図ります。
内部対策の主な目的は3つあります。
クローラビリティとインデクサビリティの向上、ユーザーエクスペリエンスの改善、そして検索順位向上の基盤構築です。
外部対策とは異なり、自サイト内でコントロールできる要素を最適化します。
医療サイトでは、クローラビリティ関連(わかりやすいURL、パンくずリスト、ページネーション、内部リンク最適化など)、インデックス関連(タイトルタグ、メタディスクリプション、見出しタグ、画像alt属性、構造化データなど)、ページエクスペリエンス関連(コアウェブバイタル改善、モバイル対応、SSL化)の各施策が重要です。
特に医療情報は信頼性が重視されるため、「隠しテキスト」や「クローキング」などの不正対策は避けるべきです。
適切な内部対策を実施することで、検索上位表示と患者からの信頼獲得が可能になります。
弊社では、医療機関に特化したウェブサイト制作や運用、集患や人材獲得のサポートを行っています。
ウェブサイトやSEO対策をはじめとして集患でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。

















