病院の待ち時間が長い理由と効果的な改善法・クレーム対策9選

「病院の待ち時間がどうしても長くなってしまう」「病院の待ち時間が長くクレームがすごい」など、医療の質が高くても患者の不満をまねく、病院の待ち時間問題。
本記事では、待ち時間が長くなる理由や生じる問題点、そして効果的な改善策とクレーム対応のポイントを詳しく解説します。
患者満足度とリピート率の向上に向けた具体的なヒントをご提供しますので、ぜひご一読ください。
Contents
病院の待ち時間は実際どれくらい?
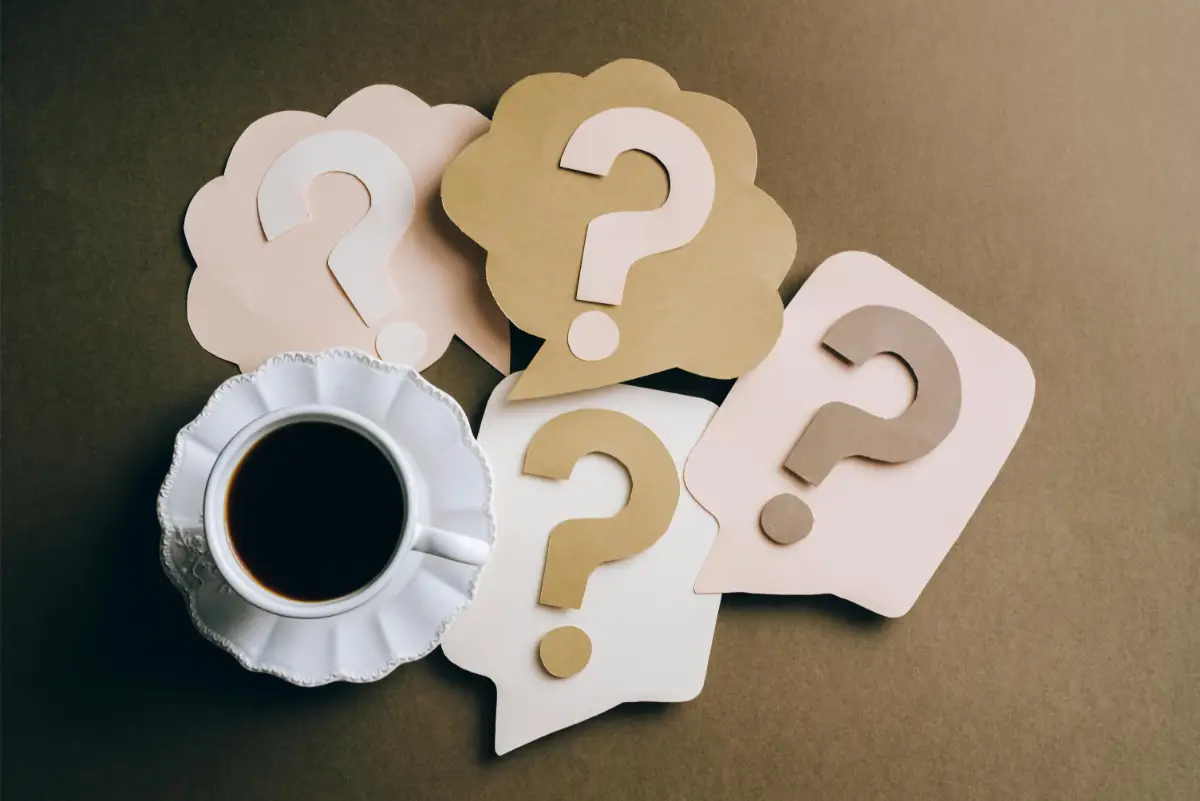
医療機関における待ち時間は患者にとって大きな関心事となっています。
一般的に診療所や病院では受付から診察までの間に15分から30分程度の待機が生じることが多いですが、これは診療科や医療機関の規模によって大きく異なります。
また診察後の会計待ちも平均で5分から15分ほどかかりますが、この時間は既に診察という目的を達成した後であるため、患者が最も長く感じる時間帯となっています。
近年はウェブ予約システムの導入により改善が図られていますが、予約していても実際には待たされるケースも少なくありません。
| 外来患者の待ち時間分布(全国・直近3回調査) | ||||
| 待ち時間カテゴリ | 2017年調査 (平成29年) |
2020年調査 (令和2年) |
2023年調査 (令和5年) |
|
| 1 | 15分未満 | 26.1% | 28.0% | 27.9% |
| 2 | 15~30分未満 | 23.1% | 25.7% | 24.9% |
| 3 | 30分~1時間未満 | 20.4% | 20.9% | 20.6% |
| 4 | 1時間~1時間30分未満 | 約10% | 10.1% | 10.5% |
| 5 | 1時間30分~2時間未満 | 約7% | 6.4% | 6.5% |
| 6 | 2時間以上 | 5.4% | 5.5% | 5.2% |
出典:厚生労働省「受療行動調査」結果(2017年・2020年・2023年)など
病院の待ち時間と患者の満足度の関係

本項目では、病院の待ち時間と患者の満足度の関係をご説明します。
平均的な病院の待ち時間
病院での待ち時間は診療科によって大きく異なります。
一般的な外来診療の場合、受付から診察までは15分から30分程度が平均的な時間とされています。
しかしながら、総合病院や高齢の患者が多く訪れる内科・整形外科などの診療科においては、受付から会計終了まで含めると1時間から2時間を超えることも珍しくありません。
患者が待つことのできる時間
各種調査データによれば、患者の多くは15分程度までなら許容範囲と感じているようです。
しかし待ち時間が20分を超えると「長い」と感じ始める傾向があり、さらに30分を超過すると不満を感じる患者が急激に増加する傾向が見られます。
一例として、小児科に子どもを連れてきた母親からは「子どもがすぐに飽きてぐずり始めるため、10分以上待つと不安になる。予約していてもこのように待たされるのは辛い」という意見もあります。
待ち時間は患者の不満につながりやすい
結論からいえば、病院での待ち時間は患者の強い不満につながる要素です。
特に以下のような条件が重なると、患者の不満はさらに強まる傾向があります。
それは体調が優れないときに長時間待たされる場合、待つ理由や状況についての説明がない場合、そして待っている間に特に何もすることがない場合です。
また診察が終わった後の会計窓口で20分以上待たされた患者からは「もう診察も終わっているのに、なぜここでまた待たされなければならないのか」という声が聞かれます。
診察という主目的が達成された後の待ち時間は特に不満を抱きやすい時間帯となっています。
病院の待ち時間が長くなる理由
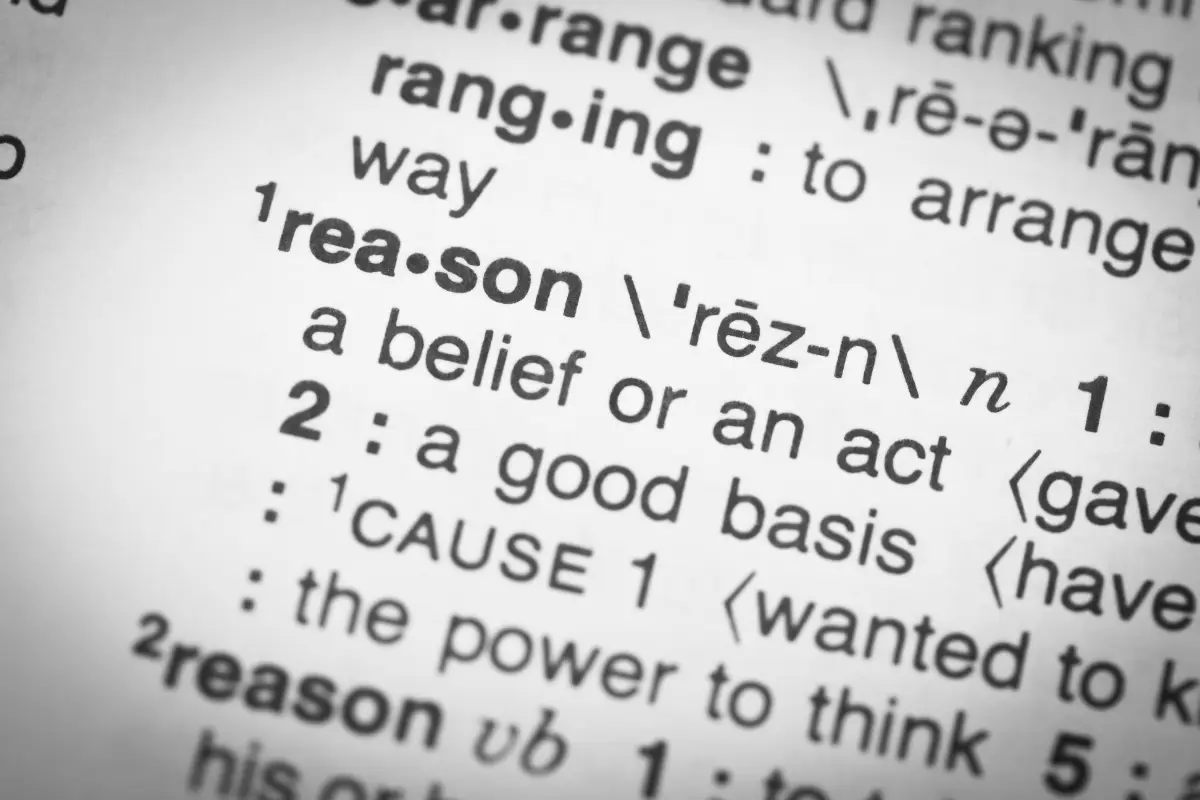
本項目では、病院の待ち時間が長くなる理由をご説明します。
端的に業務量や患者数が多い
言うまでもありませんが、診療能力、つまり医師数や診察枠に対して来院する患者数が大幅に上回ると、必然的に待ち時間の延長につながります。
特に午前中の診療時間帯や月曜日、連休明けなどは患者の来院が集中しやすく、待ち時間が長くなる傾向があります。
業務が効率化されていない
医療機関における患者の受付、問診、診察、会計などの各プロセスが手作業中心であったり、紙ベースの運用で非効率な場合、全体の流れが滞り待ち時間の原因となります。
また医療スタッフ間の連携不足やシステムの未整備も長い待ち時間を生み出す要因となっています。
例えば受付での問診記入に時間がかかるケースがあります。
初診の患者が紙の問診票に詳細な情報を記入し、その後看護師がその内容を手作業でカルテに転記し、さらに医師へ口頭で患者情報を共有するという流れです。
この一連のプロセスの間、他の業務が停滞しがちになり、結果として後続の患者の待ち時間が増加します。
近年ではウェブ問診や予約管理システムを導入する医療機関も増えていますが、これらのシステムを職員が十分に使いこなせていないケースもあります。
操作に不慣れな職員がいると、結局は従来の手作業に戻ってしまい、システム導入の効果が十分に発揮されないことがあります。
患者の来院時間に偏りがある(特定の時間に患者が集中する)
医療機関では午前の開院直後に来院する患者が多く、時間帯による来院数の偏りが非常に大きいという特徴があります。
「早く医療機関に行けば早く診察が終わる」と考えて開院前から並ぶ患者が多いため、皮肉にもこの時間帯が一日の中で最も混雑する時間帯となってしまいます。
一方で午後の診療枠は比較的空いていることが多いにもかかわらず、患者から選ばれにくい傾向があります。
「午後は学校や仕事があるから医療機関に行けない」「診療は午前中に終わらせたい」などの理由から、午後の診療枠が空いていても十分に活用されないケースが多く見られます。
この来院の偏りが、特定時間の待ち時間を長くする大きな要因となっています。
急患により順番が変わる
医療現場では生命に関わる緊急対応が優先されるため、一般外来の患者は診察順が後回しになることがあります。
特に内科や小児科、外科などの診療科では、通常の外来診療中に急患が搬送されてくるケースがあり、その都度予定が大きく変更されます。
患者側からすると「順番がずっと回ってこない」「後から来たはずの人が先に呼ばれている」といった感覚を抱きます。
医療機関側には緊急対応という正当な理由があっても、その説明が適切になされていないと患者の不満に直結しやすいという特徴があります。
病院の待ち時間が長いことによる問題点

本項目では、病院の待ち時間が長いことによる問題点についてお伝えします。
サービスの質および患者の満足度が下がる
医療機関での待ち時間が長引くと、診察を受ける前の段階で既に患者のストレスや不満が高まっている状態となり、その後の医療サービスに対する評価にも悪影響を及ぼします。
医師やスタッフの対応自体が丁寧であっても、「長時間待たされた」という最初の印象がそれ以降の良好な対応の効果を完全に打ち消してしまうこともあるでしょう。
患者のリピート率が下がる
一度「待たされた」と感じた患者は、次回は別の医療機関を選択しようと判断する傾向が強まります。
特に選択肢が多い都市部や、美容皮膚科や整骨院などの自由診療分野においては、この傾向が顕著に表れます。
皮膚科での自由診療(シミ取りレーザー)の事例では、予約をしていたにもかかわらず30分以上待たされた患者が「時間通りに治療を受けられないのであれば他の医院に行く」と判断してその場でキャンセルしたケースがありました。
このように長い待ち時間は患者の再来院意欲を低下させる重大な要因となり、結果的に医療機関の経営安定性にも悪影響を及ぼします。
特に競合する医療機関が近隣に複数存在する環境では、待ち時間の短縮は患者維持のための重要な要素となるでしょう。
ネガティブな口コミが増える
現代ではインターネット上の口コミサイト、Googleレビュー、SNSなどの普及により、「待ち時間への不満」がすぐに公開されるようになっています。
その内容が客観的事実に基づくものであっても誤解に基づくものであっても、一度「待ち時間が長い医療機関」というレッテルが貼られると、新規患者の来院に大きな影響を及ぼす可能性があります。
Googleマップのレビュー欄では「予約していたのに1時間以上待たされた」「受付の対応は普通だったが、待たされすぎてイライラした」などの評価が集中し、星一つや二つといった低評価が並ぶことがあります。
注目すべきはこれらの評価が医師の技術やスタッフの対応といった医療の本質的な部分には触れておらず、「待ち時間だけ」が原因となって低評価となっている点です。
こうした現象が示す問題点は、医療機関側がどれだけ医療の質を保っていても、待ち時間が長いという事実だけで評価が下がりやすいという傾向です。
一度広がったネガティブな口コミを払拭するには多大な努力と時間を要するため、待ち時間の短縮と適切な説明は現代の医療機関にとって避けて通れない課題となっています。
病院の待ち時間改善・クレーム対応策9選
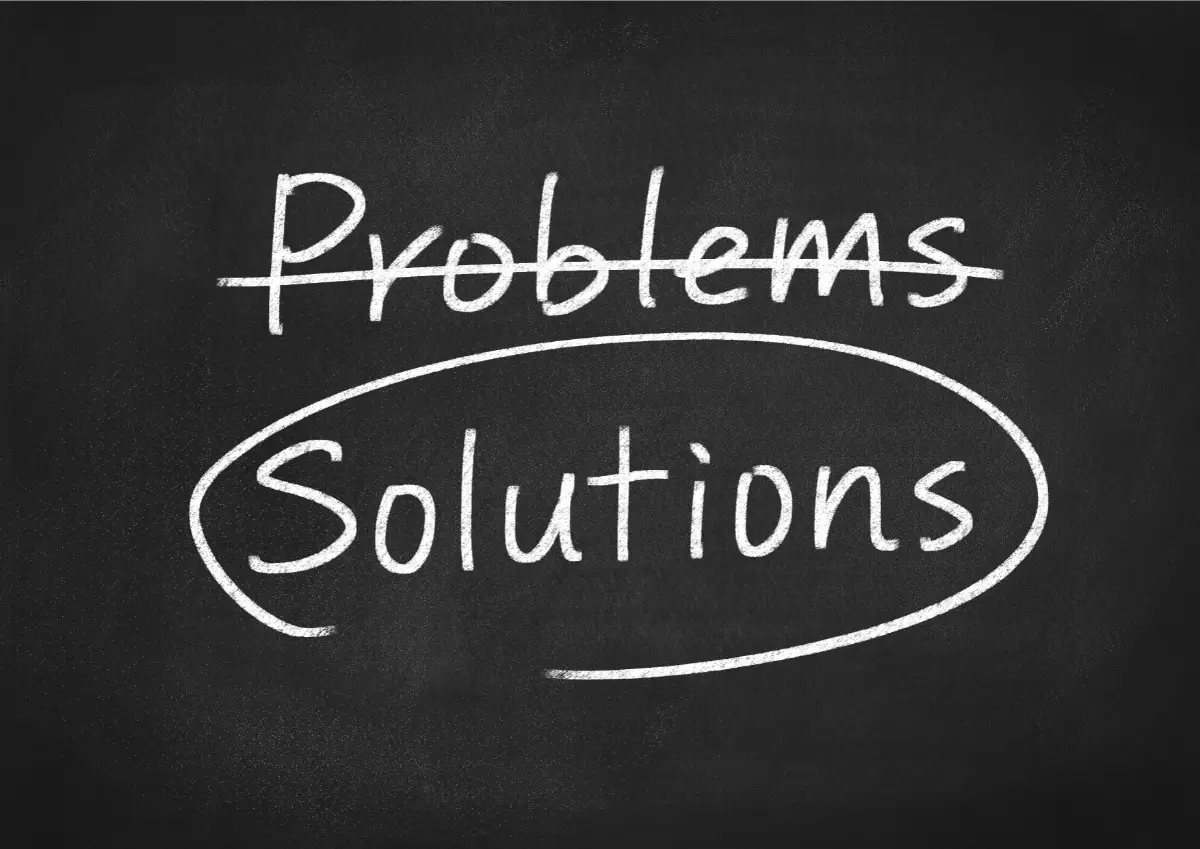
本項目では、病院の待ち時間改善・クレーム対応策をご紹介します。
病院の待ち時間改善①:予約制にする・診療予約システムを導入する
事前予約による患者の時間的分散は、待ち時間短縮のための最も基本的かつ効果的な手段の一つです。
従来の紙や電話による予約方法に加え、ウェブ予約やアプリケーションを活用した予約システムを導入することで、受付業務の負担も同時に軽減することができるでしょう。
クレーム対応の観点からも予約制の導入は効果的です。
「なぜこんなに待たされるのか」という漠然とした不満の声に対して、「●時予約の方が優先されています」と明確な理由を説明できるため、患者の納得を得やすくなります。
予約時間を明示することで待ち時間に関する期待値を適切に設定し、不満の発生そのものを予防する効果も期待できます。
病院の待ち時間改善②:待ち時間が可視化できるシステムを導入する
患者にとって「あとどれくらい待てば良いのか」が分からないという不確実性が、不安や苛立ちを引き起こす最大の要因となります。
現在の待ち人数や診察までの目安時間を明示することで、この心理的ストレスを大幅に軽減することができます。
具体的には例えば、待合室に「あと●人待ち」を表示するモニターを設置し、「現在5人待ち」「診察までの目安時間:25分」などの情報をリアルタイムで表示するとよいでしょう。
患者が現在の状況を具体的に把握できることで、「自分のことが忘れられているのではないか」という不安が解消され、待ち時間に対する精神的な負担が軽減されます。
さらに進んだ取り組みとして、スマートフォンで待ち状況を確認できるシステムを導入する医療機関も増えています。
これにより患者は院外からでも「あと何番目か」を確認できるようになり、一時的な外出が可能になり、ストレス軽減につながります。
ネガティブな口コミやクレームを未然に防ぐために
待ち時間対策は、院内オペレーションだけでなく「Webサイトでの事前の情報発信」も重要です。「予約が取りやすい」「混雑状況がわかる」サイト設計で、患者様のストレスを軽減しませんか?
▶ 歯科医院のホームページ制作・運用サポート詳細はこちら
病院の待ち時間改善③:受付など業務効率化をはかる
受付から問診、会計までの業務がアナログな方法に依存していたり特定の人物に集中していたりすると、どこかで滞留が発生して全体のプロセスに影響を及ぼします。
業務フローを見直し、可能な部分は自動化・省力化することが待ち時間の短縮に直接つながります。
例えば、自動精算機の導入により、会計窓口での行列形成を回避することができます。
混雑時でも支払い手続きがスムーズに進むようになり、診察後の「一番帰りたい時間帯」における患者のストレスが大幅に軽減されるでしょう。
スタッフ業務の分担明確化も重要な取り組みです。
受付スタッフが「問診対応」と「会計業務」に分かれて対応する体制を構築することで、同時並行での処理が可能になります。
一人のスタッフが全ての業務を担当する体制から脱却することで、全体の回転率が向上し、待ち時間の短縮につながります。
病院の待ち時間改善④:診療時間・曜日やスタッフを増やす
診療提供のキャパシティを拡大することで混雑時間帯を分散させる取り組みは、待ち時間削減のための根本的な改善策の一つです。
常勤医師を増やすことが難しい場合でも、非常勤医師の採用やパート看護師の増員によって補完できるケースもあります。
診療日の拡大は医療従事者の負担増加につながる面もありますが、患者満足度の向上と平日の業務効率化というメリットも生み出します。
病院の待ち時間改善⑤:患者に説明や声かけを行う
待ち時間の長さそのものよりも、「いつまで待たされるのか」「なぜ待たされているのか」という状況が分からないことへの不安が、患者のストレスを高めます。
こまめな声かけや適切な説明を行うことで、患者の納得感と安心感を大きく向上させることができます。
例えば、「ただいま混み合っており、20分ほどお待たせするかもしれません」と事前に伝えるだけで、「どのくらい待つのか分からない」という不満が顕著に減少するでしょう。
待ち時間の目安を示すことで、患者は心の準備ができ、限られた時間を有効に使うことができます。
病院の待ち時間改善⑥:新聞や雑誌を置いて待合室をより快適にする
患者が手持ち無沙汰で何もすることがない状態だと、実際の時間以上に体感時間が長く感じられ、不満が生まれやすくなります。
年齢層や関心に合わせた読み物を用意したり、テレビや動画配信サービスを導入したりするなど、待ち時間を有意義に過ごせるような工夫が効果的です。
例えば、シニア向けには、「週刊文春」や各種健康雑誌、地方紙などを配置することで大きな効果が得られるかもしれません。
適切な読み物は待ち時間の体感を短くするだけでなく、リラックス効果ももたらします。
また、小児科であれば、アンパンマンのキャラクターや乗り物をテーマにした絵本を配置することで効果を期待できるでしょう。
子どもたちが絵本や玩具に夢中になることで、親のストレスも同時に軽減されるという相乗効果も生まれます。
待合環境の快適性向上は、医療の質そのものとは直接関係しない要素ではありますが、患者満足度や医療機関全体の印象を大きく左右する重要な改善ポイントです。
病院の待ち時間改善⑦:病院内・待合室のWi-Fi環境を整える
待っている間に何もできない場合、実際の時間以上に「長さ」を体感するでしょう。
医療機関が無料Wi-Fiを提供することで、患者はスマートフォンでの動画視聴や電子書籍の閲覧、SNSの利用などを快適に行うことができるようになり、待ち時間の苦痛が軽減します。
デジタル環境の整備は初期投資や維持費用がかかる面もありますが、患者満足度の向上や評判の改善という点で大きな効果が期待できます。
また医療機関によっては、スポンサー広告やヘルスケア情報の提供などと組み合わせることで、付加価値を生み出す工夫も検討に値します。
クレーム対応①:待たせたことへの謝罪と不満の傾聴
待ち時間に関するクレームは、単に時間が長いという事実だけでなく、「無視された」「説明がない」「気持ちに寄り添ってもらえなかった」という感情的な要素にも起因します。
そのため、まずは丁寧な謝罪と患者の話をしっかりと「聞く」姿勢が非常に重要です。
「どうしてこんなに待たされるのですか?」という患者からの声に対しては、「本日は混雑しており、お待たせして申し訳ありません」と素直に謝罪の言葉を伝えることが基本です。
さらに「ご体調は大丈夫ですか?」「気分が悪くなったりしていませんか?」といった共感の言葉を添えることで効果的な対応となるでしょう。
謝罪と傾聴の姿勢は特別な技術ではなく、基本的な対人スキルですが、忙しい医療現場では疎かになりがちな要素です。
患者の声に耳を傾け、その不満や不安を受け止めることが、クレーム対応の第一歩であり、信頼関係構築の基盤となります。
クレーム対応②:対策とクレーム内容の共有
受けたクレームを「個別の出来事」として終わらせるのではなく、医療機関全体で共有し、再発防止策を明文化することが重要です。
また「改善のために具体的に動いている」ということを患者に伝えることで、信頼を回復することも可能です。
例えば、受付スタッフが受けたクレームを週次ミーティングで共有するとよいでしょう。
「午前の予約をしたのに30分以上待った」という声をもとに、予約枠の設定方法を見直したり、診察の進行状況を表示するモニターを設置したりするなど、具体的な改善策につなげることができます。
単なる苦情として処理するのではなく、サービス向上のための貴重な情報源として活用する姿勢が重要です。
患者に対して改善内容を説明することも効果的です。
次回来院時に「前回はお待たせしてしまい申し訳ありませんでした。現在はこのような対応をしています」と具体的に伝えることで、「ちゃんと対応してくれているんだ」という認識につながり、信頼の回復に効果を発揮します。
患者の声を真摯に受け止め、改善に活かしていることを示すことが、医療機関のイメージ向上にもつながっていきます。
まとめ

高品質な医療を提供していても、長い待ち時間によって患者満足度が低下する医療機関は少なくありません。
診察前の平均15~30分の待機時間、そして診察後の会計待ちは、患者にとって大きなストレス要因となっています。
特に待ち時間が30分を超えると不満が急増し、リピート率の低下やネガティブな口コミにつながりやすい傾向があります。
待ち時間が長くなる主な理由は、患者数に対する医師不足、業務の非効率化、来院時間の偏り、急患対応などが挙げられます。
これらの課題に対しては、ウェブ予約システムの導入、待ち時間の可視化、業務効率化、Wi-Fi環境の整備などが効果的な対策となります。
弊社では医療機関に特化したウェブサイト制作や集患対策をワンストップで提供しています。
専門のスタッフが、患者とのコミュニケーション改善、待ち時間問題などお悩みのご相談にも対応いたします。
ウェブサイトや集患でお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
予約システムやWeb問診票と連携した「使える」ホームページへ
業務効率化のカギは、ホームページと各種システムのシームレスな連携です。スタッフの負担を減らしつつ、患者様の利便性を高める最適なWeb導線をご提案します。
▶ 歯科医院のホームページ制作・運用サポート詳細はこちら
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。












