医科歯科クリニック必見!施設基準のホームページ掲載方法と見本例
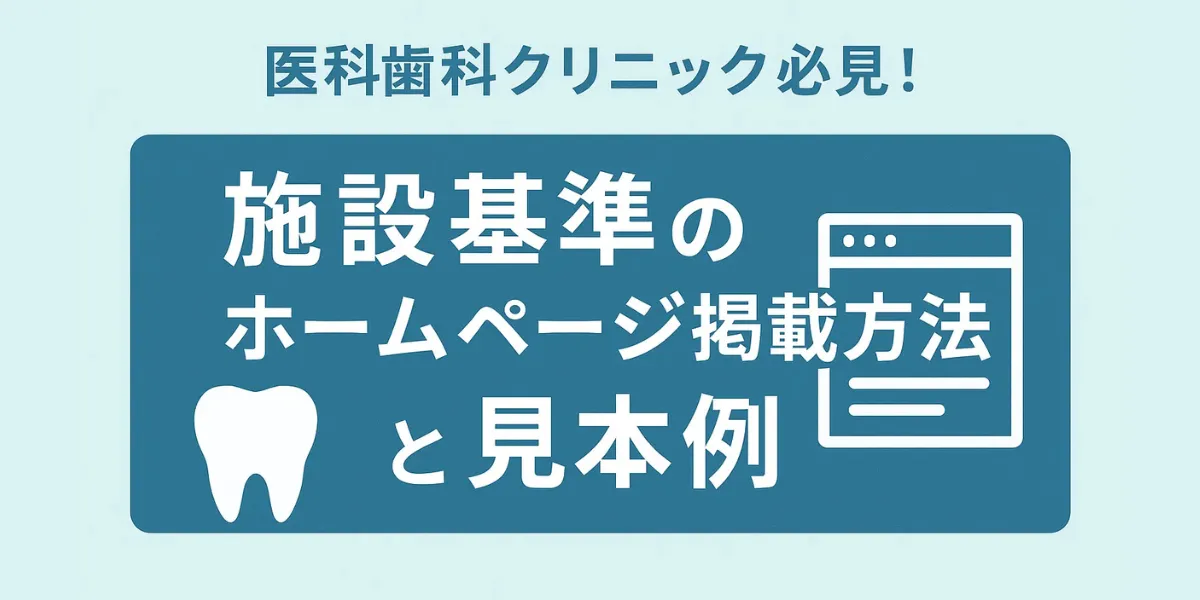
令和6年(2024年)の診療報酬改定で、医科・歯科クリニックなどの保険医療機関には、各種施設基準を自院のホームページに掲載することが義務付けられました。
しかし、クリニック・診療所を経営されている方の中には「何をいつまでに準備すればいいのか」「既存のホームページが更新不能な状態だが、どうしたらよいのか」と戸惑う声が多く寄せられています。
そこで本記事では、今回の改定の概要、対応しない場合のリスク、実際の記載見本例、そして当社がサポートできるポイントを詳しく解説します。
Contents
そもそも施設基準とは?今回の診療報酬の改定概要

そもそも施設基準とは、医療機関が診療報酬を算定するために必要な体制や設備、人員配置など、一定の条件を満たしているかを厚生労働省に届け出るための基準です。
たとえば「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」「外来感染対策向上加算」など、さまざまな項目が含まれます。
そして近年、このような施設基準については「患者への分かりやすい情報公開」が強く求められるようになってきました。
その流れを受けて、今回の診療報酬改定では“情報公開のあり方”が大きく変わった点が注目されています。
ホームページ掲載の義務化
では、今回の診療報酬改定によって、施設基準の情報公開は具体的にどのように変わったのでしょうか。
今回の診療報酬改定では、「一部の施設基準に関する情報は自院ホームページに掲載すること」が新たに義務付けられました。
従来は院内掲示で対応できていた項目や、そもそも掲示義務がなかった項目まで、インターネット上での公開が求められるようになっています。
ホームページを持つすべての医療機関が対象
ホームページ掲載義務の対象は、「すでにホームページを公開している医療機関」です。
規模や地域を問わず、すでにホームページを持つ全ての医療機関に影響します。
たとえホームページを長期間更新していなくても、外部から閲覧できる状態であれば掲載義務が発生します。
特に、管理会社や制作会社と連絡が取れなくなっている場合や、知人に作ってもらってそのまま放置しているケースでは、対応に手間取ることが予想されます。
対応期限は2025年5月末
掲載義務には、明確な対応期限が定められています。 それは2025年5月末までです。
新たに掲載が必要となる施設基準の数が増えているため、掲載内容の整理やホームページの改修・更新には意外と時間がかかる場合もあります。
施設基準のWeb掲載・広告ガイドライン対応は万全ですか?
施設基準の届出内容は、ホームページ上で正しく掲示することで、患者様への信頼だけでなくコンプライアンス対策にもなります。医療広告ガイドラインに準拠した「守りの強い」サイト制作ならお任せください。
▶ 歯科医院のホームページ制作・運用サポート詳細はこちら
施設基準の掲載を怠るリスク

「ホームページに載せ忘れただけで、そんなに大きな問題になるのか?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、この“小さな見落とし”がクリニック経営全体に影響を与えるかもしれないのです。
ここでは、具体的にどんなリスクが考えられるのかを、ひとつずつ紐解いてみます。
返還請求や算定停止の可能性
施設基準でホームページへの掲載が必須とされている場合、それを行っていないと要件を満たしていないことになります。
つまり、加算を算定する条件が整っていない状態です。
悪意がなく単純なミスであれば、すぐに厳しい処分を受けることは少ないと思われます。
しかし、適時調査や個別指導で指摘されて、返還請求や算定停止となる可能性はゼロではありません。
個別指導・適時調査での厳しい指摘
「院内掲示とWeb上の情報が矛盾していないか」「Web掲示の内容が適切か」などは、適時調査(個別指導や)でチェックされる可能性が高い項目です。
実際、厚生労働省の適時調査実施要領等内の資料によると、「医療DX推進体制整備加算」や「介護保険施設等連携往診加算」などは重点的に調査を行う項目として記載されています。
出典:厚生労働省の適時調査実施要領
もし整合性が取れていない場合、対応に追われる院長及びスタッフの負担が増大する恐れもあります。
患者トラブルやクレーム増
後発医薬品の使用体制加算や明細書発行体制など、患者の費用負担に関わる加算は事前周知が特に重要です。
ホームページで詳しく説明していない場合、「知らないうちに加算されていた」「費用が増えた理由が分からない」という不満が生じやすく、クレームにつながるリスクがあるといわれます。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、院内掲示とあわせてWeb上でも加算内容をわかりやすく説明し、患者さんが納得できるように配慮する必要があります。
施設基準の掲載が進まない理由と課題

掲載の必要性やリスクを理解していても、なぜ多くの医療機関が対応を後回しにしてしまうのでしょうか。
ここでは、医療現場が抱える業務負担や法令解釈の難しさ、医療広告ガイドラインとの兼ね合いなどが関係しています。
忙しすぎて手が回らない
診療・事務作業・スタッフ管理など、クリニックの日常業務は常に多忙です。
そこに加え、法令やガイドラインを読み込み、Webページを更新する時間を捻出するのは至難の業です。
結果として、「わかっているが手を付けられない」状態が長引き、期限直前まで放置されるケースが後を絶ちません。
どの施設基準がWeb掲載必須なのか不明
施設基準の項目は数百に及び、保険診療の加算要件も多岐にわたります。
院内掲示が必要な項目、Web掲載が必要な項目、そもそも掲載不要な項目の切り分けが難しく、また過去の情報が古かったり、間違っていたりすることが混乱を招いています。
正確な情報をまとめるだけでも、相当な時間と専門知識が求められるのが現状です。
医療広告ガイドラインとの両立が難しい
「機能強化加算」「歯科外来診療環境体制加算」などの施設基準を、国が特別に認定したように宣伝しすぎると、医療広告ガイドライン上の誇大広告に該当する恐れがあります。
実際に、医療広告の違反事例などをまとめた「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)」によると、「口腔管理体制強化加算」等の届出について誤認させる広告(誇大広告)があると指摘されています。
表現に注意しないと法令違反になる可能性があるため、ここで作業がストップしてしまう事例も見受けられます。
2年ごとの改定対応が重い負担
診療報酬は2年に一度改定され、疑義解釈も頻繁に出ます。
一度掲載して終わりではなく、改定のたびにホームページを見直し、院内掲示や届出内容と整合性を取らなければなりません。
こうした定期的なメンテナンスを「手間だ」と感じて、先送りしてしまうことが多いのです。
具体的な対処法と記載例

施設基準を適切に掲載するためには、公的文書の正確さと、患者にも分かりやすい表現を両立させることが重要です。
また、制度改定のたびに情報を見直せる体制づくりも求められます。
具体的にどのように対応すれば良いのかまとめました。
ホームページの見やすい場所に掲載する
施設基準の項目を見やすい場所に掲示することは、院内でもホームページでも重要です。
院内掲示では、掲示物が植木で隠れていたり、他のお知らせに埋もれていたりすると、「見えにくい」と適時指導の際に注意されるケースがあります。
そしてホームページに施設基準を掲載する場合も、専用ページやトップページの近くなど、目立つ場所にまとめて表示することが推奨されます。
実際に、弊社クライアントの中にも「お知らせページ」に掲載していて分かりづらいと指摘された例があり、トップページに近い位置へ移しました。
公的文書と患者視点のバランスを意識する
厚生労働省や自治体の通知をそのまま掲載しても、専門用語が多く患者には伝わりにくいことがあります。
一方で、内容を要約しすぎると、必要な要件が抜け落ちて、誤った解釈につながりかねません。
重要なのは、公的文書の内容を正確に反映しつつ、患者が何を知ることができるのか、どんなメリットがあるのかをわかりやすく説明することです。
改定ごとに見直す仕組みを作る
施設基準の掲載は、一度行えば終わりではありません。
診療報酬は原則2年ごとに改定され、疑義解釈通知などで要件が変更される場合もあります。
そのため、定期的な見直しと更新が欠かせません。
改定の際には、チェックリストを用意し、院内掲示・届出・Web掲載の内容をひとつずつ突き合わせて確認しましょう。
必要な修正点を整理する仕組みを作ることで、直前になって慌てることなく、確実な対応が可能になります。
施設基準掲載のテンプレート例
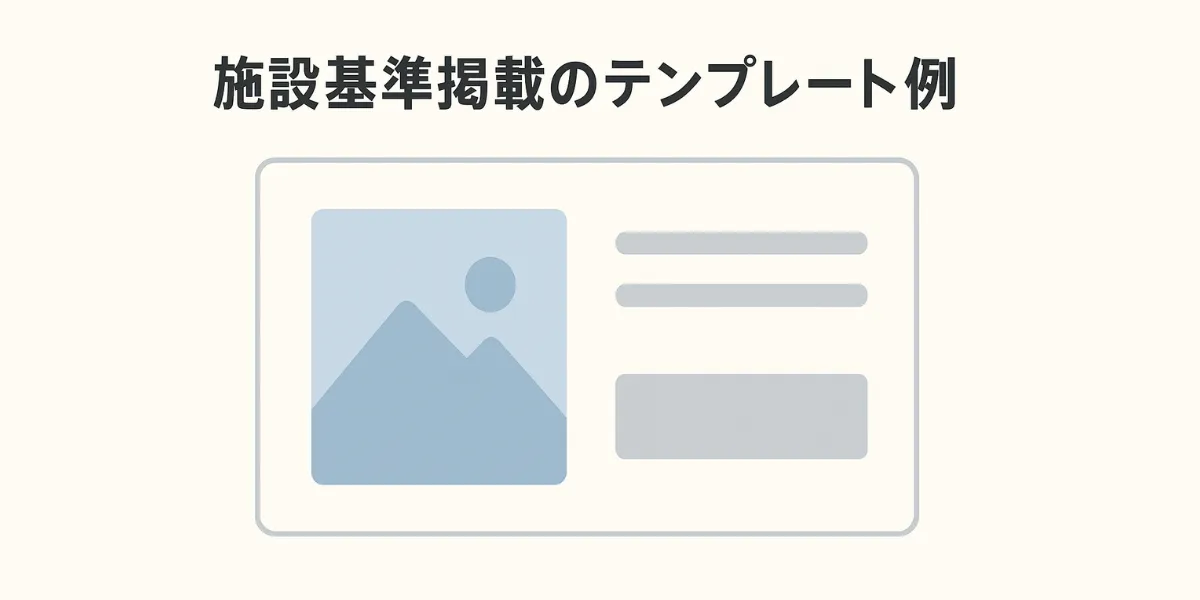
ここでは、実際にホームページへ掲載する際に活用できるサンプル文章を段落形式で示します。
公的文書のポイントを抑えつつ、“患者へのわかりやすさ”を大切にした構成です。
※この事例についての見解は弊社独自のものです。引用文によりトラブルが生じた場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
医療情報取得加算
要件 1.電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
ア)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
弊社作成文章の事例
厚生労働省の方針に基づき導入されたオンライン資格確認システムにより、当院ではマイナンバーカードの保険証利用や問診票を通じて患者さんの診療情報を安全に管理・活用し、より適切な医療サービスの提供に努めております。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用されるかどうかで診療報酬の計算が異なる場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
一般名処方加算
要件
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
弊社作成文章の事例
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合、薬の名前ではなく有効成分の名前で処方することがあります。
これを「一般名処方」といいます。 一般名処方には以下のメリットがあります:
・薬の選択肢が広がり、特定の薬が品切れの際も代替品をお渡しできます。
・患者様のご希望や状況に応じて、適切な薬を選びやすくなります。
・処方の際には、ご質問やご要望をお気軽にお申し出ください。
外来後発医薬品使用体制加算
要件 (1)
診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2)
当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20
年厚生労働省告示第60
号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。
(3)
当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品 ①
経腸成分栄養剤 エレンタール配合内用剤、エレンタールP
乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF
配合経腸用液、 ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF
配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液 ② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号510) ④ 漢方製剤(薬効分類番号520) ⑤
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590) (5)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
弊社作成文章の事例
当院では、患者様により良い医療を提供するために、先発医薬品と同等の効果が期待できる後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推進しています。
当院では、後発医薬品使用体制加算の算定要件を満たすため、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制を整えているのが特徴です。
万が一、医薬品の供給不足が発生した場合は、患者様に必要な医薬品を提供するために、以下のような対応を行います。
代替品の提供:供給不足のある医薬品に代わる、同等または類似の効果が期待できる別の医薬品を提供します。
用量、投与日数の変更:医薬品の用量を調整することで、現在の処方量での治療を継続することが可能な場合があります。医師が患者様に適切な用量を決定し、医薬品を調剤します。
明細書発行体制等加算
要件 ①診療所であること。
②レセプトオンライン請求またはCD-ROMなどの電子媒体による請求を行っていること。
③算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨を院内掲示していること。
弊社作成文章の事例
当院では、医療の透明性向上と患者様への情報提供を目的に、診療報酬の算定項目、使用した薬剤名、実施した検査名などが記載された診療明細書を、領収証とともに無料で発行しています。
明細書の発行を希望されない場合は受付にてお申し出ください。ご不明な点はお気軽にスタッフにお尋ねください。
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
要件 (1)
創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進することとしているところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしている。本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には、医療上の必要性がある認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することとしたものである。
(5)
長期収載品の処方等又は調剤を行おうとする保険医療機関又は保険薬局は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、(1)に示す本制度の趣旨及び特別の料金について院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく掲示しておかなければならないこと。また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関又は保険薬局については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている。
弊社作成文章
現在、厚生労働省の方針により、長期収載品の選定療養制度が始まっています。
この制度は、安全性や効果が同等の後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されているにも関わらず、患者様のご希望で先発医薬品(長期収載品)を処方・調剤した場合、その薬価差額の一部を選定療養費として患者様にご負担いただくものです。
ただし、以下の場合は選定療養の対象外となります。
・医師が医療上必要と判断した場合
・後発医薬品の供給が不安定で、処方・調剤が困難な場合
なお、この制度は新薬の開発を促進し、医療費の適正化を図ることを目的としています。
ご不明な点やご心配なことがございましたら、お気軽に医師または薬剤師にご相談ください。
歯科医院向け施設基準掲載のヒント:日本歯科医師会ポータルの活用

日本歯科医師会が運営する「全国の歯医者さん検索」は、施設基準掲載に役立つ情報源です。
日本歯科医師会会員の場合、必要な施設基準項目を登録すると、ポータルサイト上にホームページ掲載用のテキストを自動で生成できます。
そして日本歯科医師会は、会員の場合、自院サイトからこのポータル上の自院情報ページへリンクを設置するだけでも、施設基準のホームページ掲載要件を満たすという見解を示しています。
ここで重要なのが非会員の歯科医院も、ポータルサイトの情報を参考にできる点です。
他院の施設基準掲載例を自由に閲覧可能なので、どのような表現で施設基準を記載すべきか、自院のホームページ作成・更新時の参考になります。
また、歯科ならではの表現や、集患につながるデザインについては、多くの歯科医院様のサポート実績がある弊社の特設ページもぜひご覧ください。
▶ 歯科医院専門のホームページ制作・運用サポート詳細はこちら
まとめ:施設基準の掲載義務化で信頼性向上を

令和6年の診療報酬改定により、医療機関のホームページで一部の施設基準を掲載することが義務化されました(すべての項目が対象ではありません)。
対応期限は2025年5月末です。掲載義務を怠ると、適時指導などで是正を求められたり、最悪の場合は算定停止になったりするリスクもあります。
ただ、クリニックや病院が日常業務の合間に法令やガイドラインを常に確認し、ホームページを更新し続けるのは容易ではありません。
だからこそ、私たちは「ホームページを作って終わり」ではなく、改定ごとに的確かつ迅速に内容を見直し、運用・更新まで一貫してサポートする体制を整えてきました。
医療情報取得加算や後発医薬品使用体制など、診療報酬改定ごとに増える新たな施設基準への対応も豊富な実績があります。
また、医療広告ガイドラインにも細心の注意を払い、誤解を招かない分かりやすい表現と、貴院ならではの強みを正しく伝えることを得意としています。
単なる義務対応ではなく、施設基準の情報発信を“信頼度アップ”や“選ばれる医院づくり”につなげたい方は、ぜひご相談ください。
現場の負担を最小限にしつつ、貴院の魅力をしっかり発信するためのパートナーとして伴走いたします。
歯科クリニックの先生方へ
歯科特有の加算対応や、増患施策に強いWeb運用プランをご用意しています。
▶ 歯科医院専門のホームページ制作・運用サポート詳細はこちら
小宮山昇平 株式会社ゼロメディカル・主任Webライター
1988年生まれ。大学卒業後、教育分野と出版業界での経験を経て、2016年、株式会社ゼロメディカルにWebライターとして入社。これまでに、歯科医院、動物病院、クリニック、整骨院など、医療分野を中心に、200人以上の経営者を取材。1000以上の記事を執筆した経験を持つ。医療分野のほか、教育、法務、AI分野への造詣も深い。現在、人にしか書けない独自の記事を追求中。










